中教審は26年12月、新たな学校種の創設を含む「小中一貫教育」の制度化を答申した。
答申は既存の小・中学校に加え、➀一体的な組織体制の下で9年間一貫した系統的な教育課程による新たな学校種「小中一貫教育学校(仮称)」/➁独立した小・中学校が9年間の系統性を確保した教育課程で一貫教育を行う「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」といった2つの形態の小中一貫校の制度化などを提言した。
両形態とも、現行の小・中学校の学習指導要領に基づくことを基本としたうえで、独自教科の設定、指導内容の学年・学校段階間の入替え・移行など教育課程の特例や、学校施設の「一体」型、「分離」型等を問わない設置が可能となる。最速で28年度開校の予定である。
* * *
我が国の近代教育制度は、明治5(1872)年の「学制発布」に始まる。当時の教育行政区画は大学区(全国8区分)、中学区(各大学区内を区分)、小学区(各中学区内を区分)に区分され、小学校は小学区内に下等小学校(6歳~9歳)、上等小学校(10歳~13歳)などの設置が計画された。小学校段階の上には、下等中学(3年)と上等中学(3年)の中学校(旧制)段階、更に大学といった3段階からなる「単線型」の学校体系の土台が築かれていった。
義務教育については、明治30(1897)年代に尋常小学校4年の「義務制」が実現し、明治40年には義務教育年限が6年に延長された。昭和16(1941)年には小学校を国民学校に改め、初等科6年、高等科2年の8年を義務教育年限とした。ただ、この義務教育期間8年は戦時非常措置によって、その実施が延期されたまま昭和20(1945)年8月の終戦を迎えた。
◆ 「複線型」へと変化した戦前の多様な進路
上述のような学校体系は、その折々の社会・経済事情や社会の階層秩序との対応などによってしばしば修正・変更された。
進路・進学の面からみると、まず、尋常小学校での6年間の義務教育の後、そのまま社会に出る、あるいは2年間の「高等小学校」に進むといった初等教育機関のコースがあった。
他方、義務教育修了後、上級学校の旧制「中学校」(旧制中学)に進み、さらに旧制「高等学校」(旧制高校)などから、旧制「大学」(帝大、官立大、公立大、私立大)、あるいは「高等師範学校」や旧制「専門学校」などの高等教育機関へ進む進路があった。また、「高等女学校」や「師範学校」、「実業学校」などの進路も併設されていた。
このように、明治初期に「単線型」で始まった学校体系は、時代が進むにつれ、経済・産業社会の発展や学校教育の進展などに対応して「複線型」といわれる様々な学校種に分かれ、上級学校への進路も多様に分岐していった。
戦後の学校体系は昭和22年4月から、小学校6年-中学校3年-高校3年-大学4年の「6-3-3-4」制を基本とする「単線型」に転換された。
新しい学校制度は、当時、アメリカで中等学校(ハイスクール)への進学拡大を図って広く取り入れられていた「6-3-3」制(州によって異なる)を参考に、小学校6年・中学校3年の9年間を“義務教育”にし、高校3年間の教育課程にできるだけ多くの生徒を進めさせたいとして、極めて困窮していた財政状況の下で断行された。
この小・中学校9年間の教育課程は現在まで約70年にわたり、「6-3」制の下で児童生徒を育成してきた。
「6-3」制の小・中学校制度の創設から約70年が経過し、この間、社会環境や児童生徒の状況は大きく変化してきた。
義務教育期間における子供たちの心身の発達の早期化、価値観などの変化は著しく、特に小学校から中学校への新しい環境に移行する段階でのいじめ・不登校といった所謂「中一ギャップ」や小学校4~5年生段階での発達上の段差など、義務教育の学年区分や学校種間には教育課程等を含む接続の在り方に大きな課題があると指摘されている。
義務教育については、憲法(第26条第2項)の規定を受け、教育基本法(第5条)で義務教育の趣旨や目的/学校教育法で義務教育の目標及び義務教育期間9年と小学校6年、中学校3年の修業年限等/学校教育法施行規則で小・中学校の各教育課程編成などが規定されており、基本的にはこうした規定に則って小・中学校教育が施されている。
他方、上述のような義務教育段階における諸課題に対しては、小中連携や小中一貫教育などによって対処している自治体や学校も少なくない。小中一貫教育に取り組む自治体や学校では、児童生徒の発達状況や各地域の課題等を踏まえた弾力的で柔軟な教育課程編成の取組や、教育課程の基準の「特例措置」を活用した取組が行われている。
教育課程上の「特例措置」制度については現在、「研究開発学校制度」(研究開発校)や「教育課程特例校制度」(教育課程特例校)がある。これらの制度は、いずれも国の基準によらない柔軟な教育課程の編成が認められる一方で、各学校種の教育目標に照らして児童や生徒に教育上適切な配慮がなされるよう“文科大臣の指定”が必要となっている。これらの学校では、学習指導要領によらない「独自教科」の設置や指導内容を小・中学校間で「入替え・移行」することなどが可能である。
一方、教育課程上の「特例措置」制度を活用せず、学習指導要領の範囲内で各自治体や学校の創意工夫によって小中一貫教育に取り組んでいるところも多数みられる。
いずれにおいても、小中一貫教育は、義務教育9年間を一貫して捉える教育課程編成や系統的な教育・学習を目指して行われる教育で、所謂「小中連携」とは異なる(後述)。
◆ 研究開発校
「研究開発学校制度」は高校等も含めた教育課程に関する研究開発を行う学校として、昭和51(1976)年度からスタートし、平成12(2000)年度には公募型に改正されている。
公立の小中一貫教育は、12年に広島県呉市の小・中学校が文部省(当時)の指定を受けて、児童生徒の発達段階に適応した義務教育9年間を一貫する教育課程編成に取り組んだことに始まる。同市の小中一貫教育は、「中1ギャップ」の解消や自尊感情の育成等を目的に、9年間を「前期(4年)-中期(3年)-後期(2年)」に区分し、小中学校の合同授業や合同行事等を実施している。
◆ 教育課程特例校
ところで、17(2005)年10月の中教審答申『新しい時代の義務教育を創造する』(『義務教育答申』)は、「義務教育に関する制度の見直し」で次のように提言している。
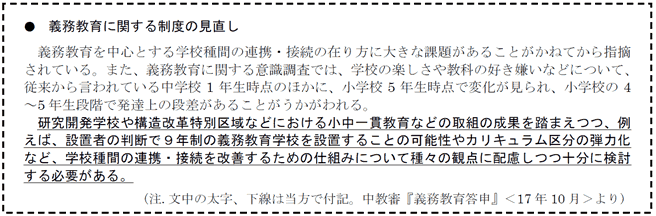
文科省はこの『義務教育答申』などを踏まえ、20年に「教育課程特例校制度」(教育課程特例校)を創設し、“文科大臣の指定”を受けることで教育課程の基準によらず、柔軟な小中一貫教育の実施を可能とした。
これにより、当時の規制緩和による政府主導型の「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」(学習指導要領の基準によらない教育課程編成・実施等の特例:総理大臣の認定)は当制度に移行し、小中一貫教育を実施する学校が全国的に拡大していった。
* * *
政府の教育再生実行会議(以下、実行会議)は26年7月初め、『今後の学制等の在り方について』(『第5次提言』)を安倍晋三首相に答申した。
『第5次提言』は、○幼児教育に関する無償教育や義務教育期間の見直し、小中一貫教育の制度化、実践的な職業教育を行う高等教育機関の制度化、高等教育機関への編入学等の柔軟化など新しい学校制度の構築/○教員免許制度の改革と教員養成等の見直し/○教育を「未来への投資」として重視する施策といった3部構成でまとめられた。
このうち、「小中一貫教育の制度化」に関しては、次のような事項が提言された。
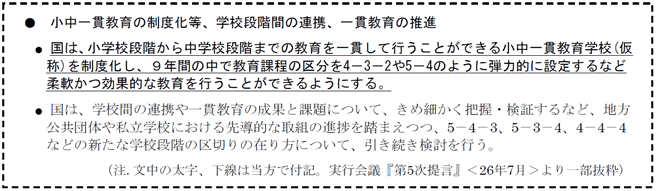
下村博文文科大臣は実行会議の『第5次提言』や教育システムの現状と課題等を踏まえ、26年7月末、「1.子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について/2.これからの学校教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方について」の2つの事項について中教審に諮問した。
諮問1.では、小中一貫教育を学校制度に位置づけ、9年間の教育課程の区切りを柔軟に設定できるようにすることと、それに伴う学校種を超えた教員免許状の創設などのほか、高校の早期卒業制度の創設、高校の専攻科や職業能力開発大学校、短期大学校等から大学への編入学等の進学についての審議を求めた。このうち、小中一貫教育に関する具体的な諮問内容(要旨)は、次のような事項である。
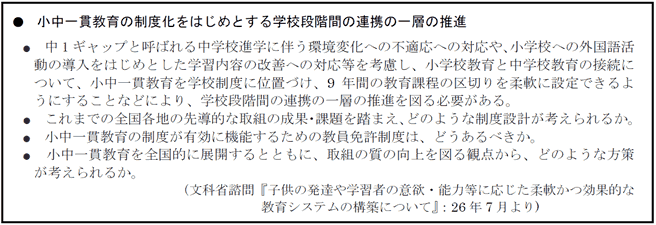
中教審は26年8月末、小中一貫教育に係る事項を審議する「小中一貫教育特別部会」を設置し、○小中一貫教育の目的/○現状の小中一貫教育の取組の成果・課題の分析/○小中一貫教育の制度設計の基本的方向性/○小中一貫教育の推進方策などについて、学習指導要領の在り方も含めて同年12月初めまで集中的に審議。12月末には小中一貫教育の制度化等をはじめとする『子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について』を答申した(以下、『柔軟かつ効果的な教育システム答申』)。
小中一貫教育には、現行の「6-3」制の下で「4-3-2」や「5-4」等の学年段階の区切りを設け、区切りごとに指導の重点を定めて一貫教育を実施するといった取組も増えている。
その背景には、児童生徒の心身の発達の早期化や「中一ギャップ」の問題などがある。
中教審の『柔軟かつ効果的な教育システム答申』では、「中一ギャップ」の背景について、およそ次のように記している。
小学校と中学校の指導に発達段階に応じた独自性があることは当然であり、その段差が学校段階間に存在することの教育効果も大きいものと考えられる一方、小・中学校間の教育活動の差異が、発達状況とのずれなどから過度なものとなる場合、「中1ギャップ」の背景になり得ることが指摘されている。
また、当『答申』では、「中1ギャップ」の要因にもなり得る学校教育や学習上の小・中学校間の主な差異として、次のような事項を挙げている。
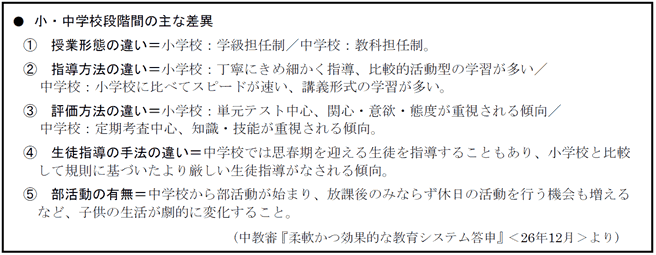
文科省は26年5月、全都道府県、全市区町村及び小中一貫教育を実施している全国の国公立小・中学校を対象に「小中一貫教育等についての実態調査」を行い、同年9月にその結果を中教審「小中一貫教育特別部会」に報告、公表した。
それによると、全47都道府県のうち、70%が国の検討や他の都道府県の取組を注視している状況で、小中一貫教育を積極的に推進又は推進を検討しているところは15%に留まる。
全市区町村(1,743)では、12%に当たる211市区町村が小中一貫教育に取り組んでいる一方、小中連携教育のみを実施しているところは1,147市区町村、66%に及ぶ。自治体での小中一貫教育の取組は、小中連携教育に比べ低調な状況が伺える。
また、小中一貫教育の実施件数は1,130件(小学校2,284校、中学校1,140校)で、そのうち87%が「成果があった」としているが、「課題があった」も同率であった。以下に、今回の実態調査の主な概要を紹介する。
なお、当「実態調査」や中教審の『柔軟かつ効果的な教育システム答申』では、「小中連携教育」と「小中一貫教育」について、次のように定義している。
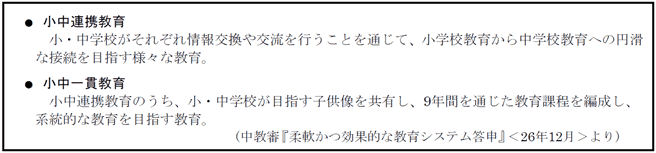
◆ 小中一貫教育に取り組む自治体の狙い
小中一貫教育の自治体の狙いは様々であるが、ほとんどの自治体は「学習指導上の成果を上げる」(95%:小中一貫教育実施件数1,130に占める割合。以下、同)/「生徒指導上の成果を上げる」(98%)/「9年間通して児童生徒を育てる教職員の意識改革」(92%)などを掲げている。
このほか、「教員の指導力の向上」(77%)/「異学年児童生徒の交流の促進」(63%)/「一定規模の児童生徒数の確保」(13%)/「特別支援教育における学校間連携体制の強化」(48%)などを挙げている。また、「特色ある学校作り」(49%)/「地域との協働関係の強化」(42%)などもみられる。小中一貫教育に取り組む自治体は、地域や児童生徒の実態を踏まえ、多面的な狙いを設定して取り組んでいることが伺える。(図1参照)
◆ 9年間の教育課程等の系統性・連続性の確保
小中一貫教育を行っている学校でも、9年間の教育課程や指導方法の系統性・連続性といった一貫性の確保についての取組は多様である。
小中一貫教育の中核をなす「9年間をひとまとまりと捉えた教育目標の設定」(47%:実施件数1,130に占める割合。以下、同)や「各教科別に9年間の系統性を整理した小中一貫カリキュラムの編成」(52%)の実施はいずれも半数程度に達している。
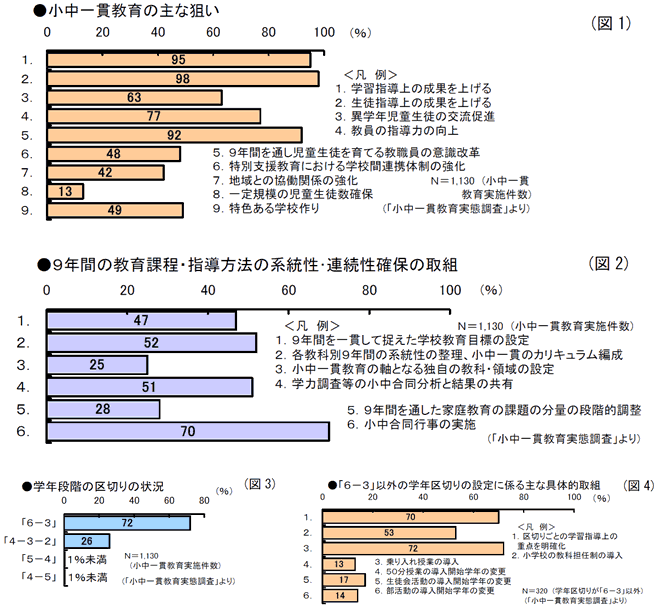
言語活動や食育、キャリア教育、ふるさと教育、情報教育といった「教科等横断的な事項」についての小中一貫カリキュラムの編成はおおむね20%未満である。小中一貫教育の軸となる「独自の教科・領域の設定」は25%である。
また、小・中学校間における「基本的な授業スタイルの緩やかな統一」(43%)/「9年間を見通して家庭学習の課題の分量を段階的に調整」(28%)/「9年間を見通した学習方法や学習時間のマニュアルの作成」(27%)などの取組も行われている。
他方、教育課程や指導の在り方と一体化すべき「評価」の側面については、「学力調査の小中合同分析と結果の共有」(51%)が半数を超えているほか、「学校評価の小中合同実施」(32%)/「9年間を見通した評価規準や評価方法の共有」(12%)などが行われている。また、「小中の合同行事の実施」(70%)は、小・中学校の接続の円滑化で最も多い取組になっている。(図2参照)
◆ 学年段階の区切りの設定
小中一貫教育の大きな特色の一つに、児童生徒の発達段階に応じて「6-3」制と異なる学年段階の区切りの設定がみられる。ただ、実態は現行制度の「6-3」制(72%:実施件数1,130に占める割合。以下、同)が70%以上を占め、これに「4-3-2」の区切り(26%)が続き、「5-4」や「4-5」などの区切りはいずれも1%未満の少数である。(図3参照)
●「6-3」以外の設定における具体的な取組内容
「6-3」以外の区切りを導入している小中一貫教育(320件)の具体的な主な取組内容としては、「区切りごとの学習指導上の重点を明確化」(70%:320件に占める割合。以下、同)/「小・中学校間の乗り入れ授業の導入」(72%)/「小学校における教科担任制の導入」(53%)/「習熟度別指導の導入」(28%)などとなっている。
また、中学校に特徴的な活動等を小学校高学年に前倒しして導入している例として、「50分授業」(13%)/「定期テスト」(12%)/「生徒会活動」(17%)/「部活動」(14%)などが10%台で実施されている。(図4参照)
◆ 教育課程の「特例措置」の活用状況
小中一貫教育の実施に当たっては、「研究開発学校制度」(1%:実施件数1,130に占める割合。以下、同)と「教育課程特例校制度」(19%)といった教育課程の「特例措置」を活用しているのは約20%で、65%は「特例を活用せず、今後も活用の予定なし」としている。
● 教育課程の「特例措置」を活用している具体的な取組状況
教育課程の「特例措置」を活用している小中一貫教育(224件)では、「小中一貫教育の軸となる独自教科等の設定」(72%:224件に占める割合。以下、同)/「指導内容の前倒し」(18%)のほか、「小学校における英語教育・外国語教育の導入」(82%)の高い取組状況が注目される。
◆ 小・中学校教員の「相互乗り入れ」と指導方法・指導体制の改善
小・中学校段階間の接続の円滑化に効果的といわれる小・中学校教員の「乗り入れ授業」の実施は、様々な教科等で行われている。「中学校教員が小学校で指導するケース」(39%:実施件数1,130に占める割合。以下、同)は40%近くに及ぶが、「小学校教員が中学校で指導するケース」は1%未満と低い。
他方、小・中学校教員による「相互乗り入れ授業」(21%)は20%程度で、「乗り入れ授業を実施していない」(39%)がその2倍近くに達している。
また、小学校段階からの「教科担任制の導入」は理科や音楽などを中心に、様々な教科等で行われているが、実施学年をみると第5学年から急増している。
中教審の『柔軟かつ効果的な教育システム答申』では、これらの状況について、例えば、子供の成長の状況等に即して、中学校段階の指導の特質と考えられてきたものを部分的・段階的に小学校高学年に導入することで、学習内容の量的・質的充実に対応する狙いがあるとしている。
更に、このような取組により、小学校の児童が入学前に中学校の教師に出会っておくことは進学後の新しい環境への適応の観点から有効であるとしている。また、逆に、小学校における指導の特徴を中学校入学後にも部分的に継続することにより、学習内容の高度化によるつまずきへの対応やきめ細かな生徒指導を実施する狙いもあるという。
こうした教育活動は、小・中学校の教員がそれぞれの良さを相互に学び合う契機にもなっているとしている。
◆ 小中一貫教育の施設の形態等
中教審の『柔軟かつ効果的な教育システム答申』は、小中一貫教育を実施している校舎等の施設形態について、次のように分類している。
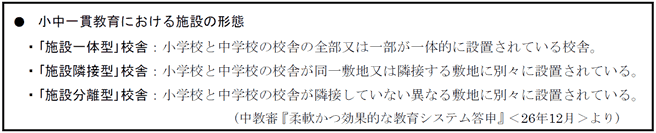
今回の「実態調査」によると、小中一貫教育の施設状況は、「施設一体型」(13%:実施件数1,130に占める割合。以下、同)/「施設隣接型」(5%)/「施設分離型」(78%)となっており、この順で「小中一体となった学校マネジメント体制」の実施率が高い。(図5参照)
当『答申』では、小中一貫教育は施設の一体性が高く、指揮系統が一本化されている場合に小・中学校間の取組の一体性が高まるのは必然であるとしている。
その一方で、「施設分離型」校舎で小中一貫教育を行っている場合や、学校ごとに校長が配置されている場合でも様々な工夫により、教職員が一体感を持って一貫教育を行っている例も多くあることに留意する必要があると指摘している。
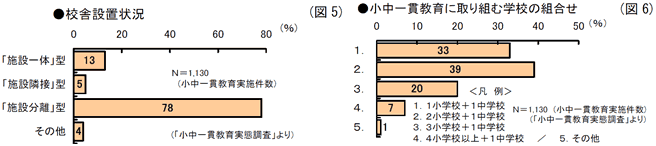
また、小・中学校の組合せは、「2小学校+1中学校」(39%)が最も多く約40%、「1小学校+1中学校」(33%)が約30%で、この2タイプが大半を占めている。このほか、「3小学校+1中学校」(20%)/「4小学校以上+1中学校」(7%)などもみられる。(図6参照)
◆ 小中一貫教育の取組評価:「成果」
今回の「実態調査」では全体として、小中一貫教育の実施によって「大きな成果が認められる」(10%:実施件数1,130に占める割合。以下、同)と「成果が認められる」(77%)とを合わせると87%が「成果があった」と評価している。(図7参照)
報告されている具体的な成果は様々であるが、当『答申』では、おおむね次のようにまとめている。
【学習指導上の成果】
○各種学力調査の結果の向上/○学習意欲の向上、学習習慣の定着/○授業の理解度の向上、学習に悩みを抱える児童生徒の減少など。
【生徒指導上の成果】
○「中1ギャップ」の緩和(不登校、いじめ、暴力行為等の減少、中学校進学に不安を覚える生徒の減少)/○学習規律・生活規律の定着、生活リズムの改善/○自己肯定感の向上、思いやりや助け合いの気持ちの育成/○コミュニケーション能力の向上など。
【教職員に与えた効果】
○指導方法への改善意欲の向上、教科指導力・生徒指導力の向上/○小・中学校間における授業観や評価観の差の縮小/○小学校における基礎学力保障の必要性に対する意識の高まり/○小・中学校で共通に実践する取組の増加や小・中学校が協力して指導に当たる意識の高まり/○仕事に対する満足度の高まりなど。
当『答申』は、これらの「成果」について、小中一貫教育の実施による小・中学校段階の接続の円滑化、9年間を通した一貫性・継続性のある指導、異学年交流の大幅な増加、それらを通した教職員の意識の改革が相互に影響し合って生じているものであると分析している。
◆ 小中一貫教育の取組評価:「課題」
「実態調査」によると、小中一貫教育の実施に関する「課題」の状況については、「大きな課題が認められる」(7%:実施件数1,130に占める割合。以下、同)と「課題が認められる」(80%)とを合わせると87%が「課題があった」と回答している。(図8参照)
報告されている具体的な課題は様々であるが、当『答申』ではおおむね次のようにまとめている。
【一貫教育の実施に伴う準備に関わる課題】
○9年間の系統性に配慮した指導計画作成/○小・中学校合同の行事の内容設定/○時間割や日課表の工夫、施設の使用時間調整/○小学校間の取組の差の解消など。
【一貫教育の実施に伴う時間の確保等に関する課題】
○小・中学校間の打合せ時間の確保/○小・中学校合同の研修時間の確保/○小・中学校の交流を図る際の移動時間・手段の確保/○教職員の負担の軽減、負担感・多忙感の解消、負担の不均衡など。
【児童生徒に与える影響に関する課題】
○転出入者への学習指導上・生徒指導上の対応/○児童生徒の人間関係が固定化しないような配慮/○中学校における生徒指導上の問題の小学生への影響/○小学校高学年におけるリーダー性や主体性の育成など。
【教職員の意識改革等に関わる課題】
○管理職や教職員間の共通認識の醸成/○小・中学校が接続する学年等以外を担当する教職員の意識向上/○成果や課題の可視化と関係者間での共有、そのための手法の確立など。
【人事・予算面に関わる課題】
○教員の所有免許の関係で兼務発令を拡大できないこと、兼務発令の趣旨に関する教職員の理解/○小・中学校間のコーディネート機能の充実/○小・中学校の教職員人事の一体的な運用/○必要な予算の確保、小学校費・中学校費の一体的な運用など。
最も多くの学校が「課題」として認識しているのは、小中一貫教育の実施のための時間の確保や負担の軽減及び負担感・多忙感の解消であるという。
当『答申』では、小中一貫教育の導入は特に初期段階を中心として業務量の増加につながる可能性もあるため、小中一貫教育の制度化に当たっては、各学校における教職員の負担軽減の取組が効果的に行われるような支援についても併せて検討することが必要であると指摘している。
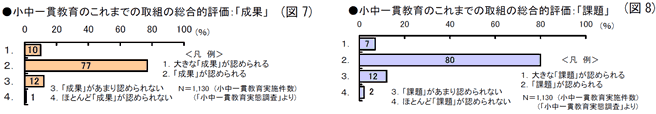
* * *
小中一貫教育は、現行制度下でも運用上の様々な取組によって実施されている。
他方、主体をなす小学校と中学校が法制上別々の学校として設置されていることを前提にしているため、研究開発校や教育課程特例校等で教育課程上の特例が認められているにせよ、9年間の一貫教育を効果的、継続的に実施していくうえで、一定の限界があるという。
中教審の『柔軟かつ効果的な教育システム答申』は、前述した「実態調査」結果なども踏まえ、小中一貫教育の取組の仕組みを総合的・効果的に整備するために、小中一貫教育の制度化の意義を次のようにまとめている。
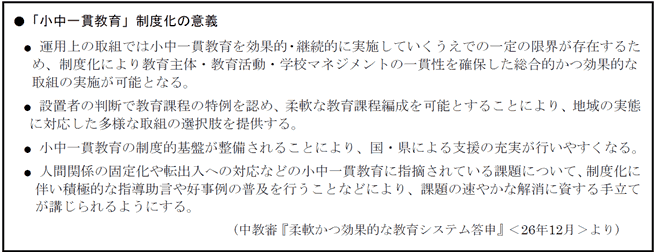
中教審の『柔軟かつ効果的な教育システム答申』は、小中一貫教育の制度化の目的として、次のような点を挙げている。
小・中学校の一体的な組織体制の下、9年間一貫した系統的な教育課程を編成することができる“新たな学校種”を設けるなどして、設置者が地域の実情を踏まえて小中一貫教育が有効と判断した場合に、円滑かつ効果的に導入できる環境を整えるためである。
これにより、小中一貫教育の優れた取組の全国展開と既存の小・中学校における小中連携の高度化が促進され、義務教育全体の質向上が期待される。
当『答申』は、小中一貫教育が各地域の主体的な取組によって多様な形で発展してきた経緯に鑑み、地域の実情に応じた柔軟な取組を可能とする必要があることから、次のような「小中一貫教育学校(仮称)」/「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」といった2つの形態を制度化すべきであると提言している。(表1、図9参照)
◆「小中一貫教育学校(仮称)」
小中一貫教育の基本形として、1人の校長の下で1つの教職員集団が9年間一貫した教育課程を編成・実施する単一の“新たな学校種”である「小中一貫教育学校(仮称)」を現行制度の小学校、中学校とは別に学校教育法(第1条:所謂「1条校」)に位置付ける。そして、一定の範囲で、文科大臣による個別の指定によらず、設置者の判断で教育課程の特例を活用することを認めるべきであるとしている。
また、当『答申』は「小中一貫教育学校(仮称)」について、次のような事項についても提言している。
● 既存の小・中学校と同様に、市町村の「学校設置義務」の履行対象とするとともに、「就学指定」の対象とし、市町村立の場合、“入学者選抜は実施しない”こととすべきである。
●「小中一貫教育学校(仮称)」の小学校段階を終えた後、希望する場合には他の学校への転校が円滑に行えるよう配慮することも必要であり、「小中一貫教育学校(仮称)」の修業年限の9年間を「“小学校段階”と“中学校段階”の2つの課程に区分」し、6学年修了の翌年度から中学校等への入学を認めるべきである。
●「小中一貫教育学校(仮称)」においては、「“原則”として“小・中学校教員免許状を併有”した教員」を配置することとするが、「“当面”は“小学校教員免許状で小学校課程、中学校教員免許状で中学校課程”を指導可能」としつつ、免許状の併有を促進すべきである。
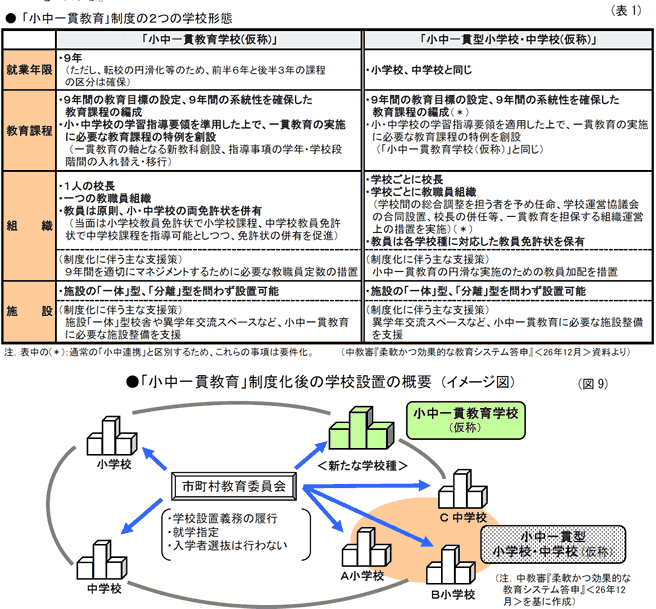
◆「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」
小中一貫教育の多様な取組の実態を踏まえ、組織上独立した小学校と中学校が前述の「小中一貫教育学校(仮称)」に準じた形で一貫教育を施す形態として、「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」についても制度上明確に位置付け、「小中一貫教育学校(仮称)」と同様の教育課程の特例の活用を認めることが必要であるとしている。
また、当『答申』は通常の小・中学校における連携教育と区別するために、次のような事項の要件化を求めている。
● 「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」については、一般的な「小中連携」と明確に区別するとともに、複数の小学校が中学校に接続する形態も想定し、一貫教育の実質を適切に担保する観点から、小中一貫した教育課程と、その実施に必要な組織運営体制などに関して、一定の要件を課すことが適当である。
具体的には、設置者の定めるところにより、小中一貫教育の中核的な要素となる「➀9年間の教育目標の明確化/➁当該教育目標に即した教科等ごとの9年間一貫した系統的な教育課程の編成・実施(年間指導計画の策定含む)」を要件として求める。
また、これらを実現するために、学校間の意思決定の調整システムの整備も要件として求めることが適当であるとしている。
当『答申』は、「小中一貫教育学校(仮称)」及び「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」における一貫教育と学習指導要領との関係などについて、次のように提言している。
● 「小中一貫教育学校(仮称)」など、新たな「小中一貫教育」制度に対応した独自の学習指導要領は作成せず、既存の小・中学校の学習指導要領に基づくことを基本とする。
● そのうえで、教育課程の一貫性を強化したり、学年段階の区切りを柔軟に設定したりしやすくするための特例措置の活用を可能とすることが適当である。
● 「小中一貫教育学校(仮称)」と「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」では、小・中学校の学習指導要領における内容項目を全て取り扱う形で教育が施されることから、既存の形態の小・中学校と新たな形態の学校が併存することで「義務教育の機会均等」が果たされなくなる事態は想定されない。
● 小中一貫教育を全域実施するか、一部実施するかなど、導入の形態については、児童生徒の実態や地域・保護者のニーズを踏まえ、設置者が適切に判断すべきである。
また、「小中一貫教育」における新たな2つの形態を制度化するに当たっては、柔軟な取組を可能とする観点から、施設の「一体・分離」といった施設形態にかかわらず設置を可能とすることが適当であるとしている。
現在行われている小中一貫教育では、前述したような研究開発学校制度や教育課程特例校制度の下で、様々な教育課程上の特例の活用がみられる。
当『答申』は、今回提言した「小中一貫教育学校(仮称)」と「小中一貫型小学校・中学校(仮称)」においても、小・中学校の学習指導要領に基づくこと及び各教科等の特性に応じた系統性・体系性に配慮することなどを条件としたうえで、「独自教科」の設定や指導内容の「入替え・移行」など、一定の範囲でおおむね次のような教育課程の特例を認めるべきであるとしている。
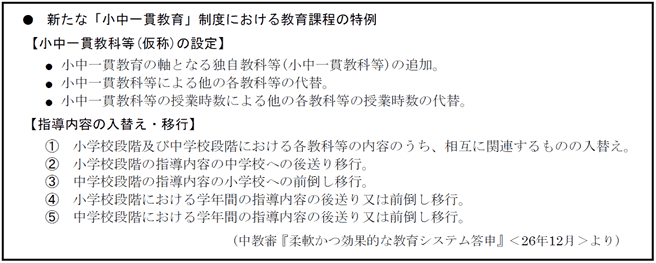
◆ 児童生徒の負担過重への配慮
上記のような教育課程上の特例を活用することは、小中一貫した指導の軸を設け、特色ある取組を行ったり、小・中学校段階の教職員が一体的に教育活動を行う契機を作ったりする意味でも有意義であるとしている。
ただ、特例の活用に際しては、児童生徒の負担過重にならないよう配慮を求めている。
当『答申』は、小中一貫教育の実施を希望する設置者が財政的理由から実施できないといった事態を防ぐため、国に対して必要な予算を確保し、適切な財政的支援を含めた条件整備を行うとともに、都道府県・市町村等との連携協力の下、取組の質の向上を不断に図っていくための方策を総合的に講じていく必要があるとしている。
具体的には、次のような方策を求めている。
○ 小中一貫教育の制度化及び推進に当たっての適切な教職員定数の算定/○ 小中一貫教育に必要な施設・設備の整備への支援/○ 小中一貫教育と学校運営協議会の一体的な導入推進など、義務教育の9年間の学びを地域ぐるみで支える仕組み作り/○ モデル事業等を通じた小中一貫教育の好事例の収集・分析・周知/○ 小中一貫教育に応じた学校評価の充実と市町村における評価・検証/○ 都道府県教育委員会による現場のニーズを踏まえた積極的な指導・助言・援助/○ 教職員の負担軽減の取組の推進など。
「小中一貫」教育における取組の中には、「小中連携」教育にも適用できるものも多数含まれているという。このため、小中一貫教育の効果的な推進方策を継続的に実施し、様々なタイプの好事例を普及させていくことで、一般の小・中学校における小中連携の高度化も促進され、義務教育全体の質の向上が期待されるとしている。
* * *
小中一貫教育は、「中一ギャップ」解消などのために、既に一部の小・中学校で教育課程の「特例措置」等の活用も含めて先行して進められてきており、いじめ・不登校の減少、学力の向上などで一定の成果が報告されている。
一方、小中一貫教育を行うに当たっての指導計画作成準備や教職員の研修等の時間の確保、人事・予算面など、様々な課題も指摘されている。
また、英語教育などの小中学校共通のカリキュラム編成など、教育課程の基準によらない小中一貫教育の取組には、研究開発校や教育課程特例校として文科大臣の指定を受けなければならない。
今回の中教審『答申』は、こうした小中一貫教育の実態を踏まえ、前述したような新たな「小中一貫教育」制度を創設し、市町村などの教育委員会が地域のニーズなどに対応して独自の判断で小中一貫教育を導入しやすくする手立てを提言したものといえる。
文科省は当『答申』を受け、「小中一貫教育学校(仮称)」創設などに向けた関連法の改正等を行うとしており、早ければ28年度にも新たな「小中一貫教育」制度がスタートするとみられる。
◆ 15年前に創設された「中高一貫教育」制度
小・中・高校の学校体系については、前述したように戦後間もなく制定された「小学校6年-中学校3年-高校3年」(6-3-3制)の「単線型」が基本とされてきた。
そうした中、中教審は平成9年、中等教育の一層の多様化を推進し、生徒の個性をより重視した教育の実現を目指すために「中高一貫教育」を導入することが適当であるとする答申『21世紀を展望した我が国の教育の在り方について』(『第二次答申』)を提出した。
文部省(当時)はこの答申を受け、従来の中学校と高校のそれぞれの制度に加え、中学・高校6年間の一貫した教育課程や学習環境の下で学ぶ機会をも選択できるようにするために関連法を改正し、11年度から「中高一貫教育」制度を導入した。
「中高一貫教育」制度には、一つの学校(前期課程=中学の教育課程/後期課程=高校の教育課程)として6年間一体的に中高一貫教育を行う「中等教育学校」のほか、「併設型中学・高校」(中学・高校の設置者が同一)と「連携型中学・高校」(中学・高校で異なる設置者でも可能)の3つの実施形態がある。26年度の設置状況(速報値)は「中等教育学校」51校(創設当初1校)/「併設型中学・高校」403校(同、2校)/「連携型中学・高校」86校(同、1校)の合計540校(同、4校)である。最近は25年度まで頭打ちの設置状況であったが、26年度は「併設型中学・高校」が一気に85校(27%)増え、全体で初の500校超えとなった。
◆「学制」改革への端緒
今回提言された「小中一貫教育」制度は、上記の「中高一貫教育」制度に続くもので、学校体系の「複線化」が小・中・高校段階において図られることになる。
小中一貫教育の制度化で、「小中一貫教育学校(仮称)」等の設置が一気に進むとは考えにくい。ただ、地域の実態や社会の変化に柔軟に対応して、「小中」や「中高」の一貫教育がより拡大していけば、本格的な「学制」改革の議論につながっていくことはあり得る。
