政府の教育再生実行会議は25年5月、大学入試などへのTOEFL等の外部試験活用、小学校英語の早期化と教科化、中学校での英語による基本授業など、英語重視のグローバル人材の育成を提言した(『第3次提言』)。文科省は25年12月、こうした提言等を踏まえ、小・中・高校を通じた『グローバル化に対応した英語教育改革実施計画』を策定した。
この実施計画の具体化に向けて検討、議論してきた文科省の有識者会議は26年9月、英語の指導と評価の改善、「聞く」「話す」「読む」「書く」の“4技能”を測る資格・検定試験を大学入試等に活用する受験英語の改善など、英語教育改革の“5つの提言”を『今後の英語教育の改善・充実方策について』(報告)にまとめた。
* * *
『今後の英語教育の改善・充実方策について』 (以下、『報告』:26年9月)
~ グローバル化に対応した英語教育改革の5つの提言 ~
文科省はこれまで、英語教育の改革・改善について様々な具体的施策を打ち出してきた。
「英語教育の在り方に関する有識者会議」(26年2月設置:以下、有識者会議)は今回の英語教育改革の背景として、社会の急速なグローバル化の進展の中での英語力の重要性/これまでの英語教育改革の進展や課題を踏まえた更なる取組の充実の2点を挙げている。
有識者会議はまず、急速に進展するグローバル化において、英語力の一層の充実は我が国にとって極めて重要な問題であると位置づけている。
これからは、異文化理解や異文化コミュニケーションがますます重要になり、国際共通語である英語力の向上は我が国の将来にとって不可欠で、アジアでトップクラスの英語力を目指すべきであるとしている。今後の英語教育改革において、英語の基礎的・基本的な知識・技能とそれらを活用して主体的に課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成することは、児童生徒の将来的な可能性の広がりのために欠かせないという。
グローバル化への対応は英語の習得だけでなく、我が国の歴史・文化等の教養とともに、思考力・判断力・表現力等を備えて情報や考えなどを積極的に発信し、相手とのコミュニケーションができなければならないとしている。
特に、東京オリンピック・パラリンピックを迎える2020(平成32)年はもちろんのこと、現在の児童生徒が社会で活躍するであろう2050(平成62)年頃には、多文化・多言語・多民族の人たちが協調と競争するような国際的な環境におかれ、外国語を用いたコミュニケーションの機会が格段に増えることが想定されるという。
有識者会議はまた、これまでの英語教育の成果と課題を踏まえつつ、小・中・高校が連携して一貫した英語教育の充実・強化のための改善を図っていくことを求めている。
その際、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を活用した英語によるコミュニケーションが一層重視されるべきであるとし、小・中・高校を通じて積極的に英語を使おうとする態度を育成することと、英語を用いてコミュニケーションを図る体験を積むことが必要であるとしている。
改革1 国が示す教育目標・内容の改善
〇 『報告』は、国に対し、学習指導要領において小・中・高校を通し、➀各学校段階の学びを円滑に接続させる/➁「英語を使って何ができるようになるか」という観点から一貫した教育目標(4技能に係る具体的な指標の形式の目標を含む)を示すことを求めている。例えば、高校「英語」の4技能に係る目標の「話すこと」の“発表”(Spoken Production:SP)では、「必履修科目」(SP1~SP3)/「選択科目」(SP4~SP6)ごとに目標を段階的に表示する。「話すこと」の“やりとり”(Spoken Interaction:SI)においても同様に、「必履修科目」(SI1~SI3)/「選択科目」(SI4~SI6)ごとに目標を段階的に表示する。
こうした目標を設定し、○ 伝える ⇒ スピーチをする ⇒ プレゼンテーションをする/○ 伝えあう:相手の発話に反応する ⇒ ディベートをする ⇒ ディスカッションをする、といった「話す」技能を段階的に育成する。
ただし、具体的な学習到達目標は、各学校が設定する。
〇 また、高校卒業時に、生涯にわたり4技能を積極的に使えるようになる英語力の習得を目指すことや、生徒の英語力の目標を設定し、調査・分析を行い、きめ細かな指導改善・充実、生徒の学習意欲の向上につなげることも求めている。
既に設定されている英語力の目標-中学卒業段階:英検3級程度以上/高校卒業段階:英検準2級程度~2級程度以上を達成した中高生の割合50%-だけでなく、高校生の特性・進路等に応じて、高校卒業段階で例えば、英検2級~準1級、TOEFL iBT60点前後以上等を設定し、生徒の多様な英語力の把握・分析・改善を行うことが必要であるとしている。
◆ 小学校:中学年から“外国語活動”を開始し、音声に慣れ親しませながら、コミュニケーションの素地を養うとしている。
高学年では身近なことについて基本的な表現によって「聞く」「話す」に加え、積極的に「読む」「書く」の態度の育成を含めたコミュニケーション能力の基礎を養う。そのため、学習に系統性を持たせることから“教科”として行うことが適当であるとしている。
なお、小学校の外国語教育に係る授業時数や位置づけなどは今後、次期学習指導要領に向けた教育課程全体の改訂についての議論(中教審教育課程部会など)において更に専門的に検討する必要があるという。
◆ 中学校:身近な話題についての理解や表現、簡単な情報交換ができるコミュニケーション能力を養う。「文法訳読」に偏ることなく、互いの考えや気持ちを英語で伝えあう学習を重視するとしている。
◆ 高校:幅広い話題について発表・討論・交渉など言語活動を豊富に体験し、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能力を高めるとしている。
◆ 中学・高校の取組:「文法訳読」に偏らない言語活動の高度化
『報告』は、中学・高校の英語教育の取組の現状について、英語教育の目標がコミュニケーション能力の習得でありながら、「英語を用いて何ができるようになったか」よりも、「文法や語彙等の知識がどれだけ身に付いたか」という観点で授業が行われ、コミュニケーション能力の育成を意識した取組が不十分な学校もあるという指摘を挙げている。
このため、中学校では小学校との学びの連続性を図りつつ、身近な話題について理解したり表現したりするコミュニケーションを図ることができるようにすることが適当であるとし、「文法訳読」に偏らず、互いの考えや気持ちを英語で伝えあう学習を重視すべきとしている。
高校では、中学校との円滑な接続を図りながら、国際社会の多様性に対応した目標・内容を設定し、幅広い話題について発表・討論・交渉などを行う言語活動の高度化を図ることが適当であるとしている。それにより、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能力の向上を図るという。
改革2 学校における指導と評価の改善
◆ 外国語の目標と言語活動
現行の学習指導要領における外国語の目標は、外国語を通じて、
➀言語や文化に対する理解を深め/➁積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し/➂中学校では「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」などのコミュニケーション能力の基礎を養うこと、高校では情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能力を養うこと、とされている。
学習の過程では、発音・表現・文法等が曖昧であったり間違ったりするのは当然のこととした上で、失敗を恐れず、積極的に英語を使おうとする態度を育成するためにも、授業において実際に英語を使う言語活動をより一層重視する必要があるという。
◆ 「英語の授業は英語で行う」を基本に
『報告』では、中学校において、英語教科書の本文やその題材、言語材料について、生徒が関心を持てるように指導すべきであるとしている。例えば、他教科での学習内容、学校生活における活動、地域行事、生徒の体験等と関連付けることで、「文法訳読」に偏ることなく、互いの考えや気持ちを英語で伝えあう言語活動を中心とする授業が可能になるという。
このように、授業を実際のコミュニケーションの場面とする観点から、高校では「授業を英語で行うこと」を“基本”としており、中学校と高校の学びを円滑につなげる観点から、中学校でも「授業を英語で行うこと」を“基本”とすることが適当であるとしている。
中学・高校では、学習指導要領を踏まえ「英語を用いて何ができるようになるか」という観点から、学習到達目標(CAN-DO形式)を設定し、指導と評価方法を改善する取組が進んでいる。
この学習到達目標(CAN-DO形式)を指導に活用することで、高校の英語の授業のかなりの部分が英語で行われ、自信を持って英語で発言する生徒が増えているという。
◆ 学習到達目標=「CAN-DO形式」の作成と効果
『報告』は、各学校では4技能に関し、「英語を使って何ができるようになるか」という観点から、生徒に求められる学習到達目標(CAN-DO形式)を作成することが望まれるとしている。
その際、教科書・教材、生徒の学習状況、授業時数等を踏まえながら、学校及び学年・科目ごとの学習到達目標をできるだけ分かりやすく具体的に設定し、その目標に到達するための指導方法を工夫・改善することが期待されるという。
また『報告』では、学習到達目標=「CAN-DO形式」の効果として、次のような点を挙げている。
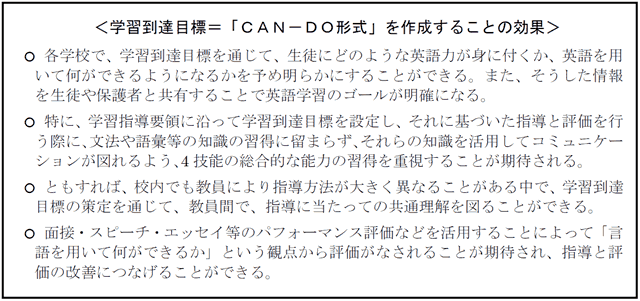
● 「CAN-DO形式」の目標は、もともとヨーロッパ共同体における複言語主義を背景とするCEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment:外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠)において学習到達指標として提案されたものである。それが、我が国では学習到達目標として用いられている。
有識者会議では、「CAN-DO形式」の目標を積極的に学習指導要領の中に導入するのであれば、「CAN-DO形式」の目標設定をどのように位置付けていくのか体系的な議論が必要であるとの指摘もあった。
◆ 学習評価
学習評価は、主体的な学びにつながる「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」を重視し、観点別学習状況の評価において、例えば、「外国語を用いて~ができる」とする観点を「外国語を用いて~しようとしている」とした評価を行うことによって、生徒自らが主体的に学ぶ意欲や態度などを含めた多面的な評価方法等を検証し、活用することが必要であるとしている。
◆ 過度の負担とならない「パフォーマンス評価」
小学校の中学年では、外国語学習の初期段階であり、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成に重点を置いて、発達段階を踏まえた具体的な学習評価の在り方を検討する必要があるとしている。
高学年では、“教科”として位置付けるに当たり、英語の特性と高学年の発達段階を踏まえつつ、文章記述による評価や数値等による評価など、適切な評価方法については先進的取組を検証し、引き続き検討することを求めている。
その際、外国語学習の初期段階であることを踏まえ、語彙や文法等の知識の量ではなく、「パフォーマンス評価」等を通して、○ 言語や文化に関する気付き/○ コミュニケーションへの関心・意欲/○ 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度/○ 「聞くこと」「話すこと」などの技能を評価することも考えられるとしている。ただ、評価が学習者への過度の負担とならないような配慮も求めている。
有識者会議では、中学校における入学者選抜に外国語を課すことは望ましくないとの指摘があった。今後、小学校における外国語学習の趣旨を踏まえ、学習者に過度の負担とならないように十分に配慮して検討することが必要であるとしている。このことは、小学校と中学校の接続の在り方を検討する際にも極めて重要であるという。
改革3 高校・大学の英語力の評価と入学者選抜の改善
〇 『報告』は、英語力の評価と入学者選抜における英語力の測定について、“4技能”の総合的なコミュニケーション能力が適切に評価されることを促している。
入学者選抜については、各大学のアドミッション・ポリシーとの整合性を図ることを前提に、4技能測定の「資格・検定試験」を促進。そのため、新たに設置される「協議会」(後述)による適切な「資格・検定試験」の情報提供、指針づくり等を早急に進めることを求めている。
また、中教審で審議されている高大接続の構築に係る“新テスト”(「高等学校基礎学力テスト(仮称)」/「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」:中教審高大接続特別部会提言、26年10月)の具体的な検討を行う際には、「協議会」の取組を参考に英語の「資格・検定試験」の活用の在り方も含め検討することが必要であるとしている。
◆ 英語力の4技能測定と学習状況の把握・分析
生徒の4技能の英語力の測定と学習状況に関する現状・課題を把握・分析し、それらの結果を活用することにより、教員の指導改善や生徒の英語力向上に生かすことにつなげることが必要であるとしている。
◆ 4技能評価と入学者選抜の改善
現行の大学入学者選抜では、4技能全てを測定する試験はほとんど行われていない。高校の入学者選抜では、一部の学校で面接・適性検査と併せて「話す力」を確認しているところがあるという。
高校・大学への進学希望者の英語力については、4技能からなるコミュニケーション能力の適切な評価を基本にした入学者選抜に改善していくことが重要であるとしている。
◆ 4技能の適切な測定と指針づくり:「協議会」の設置
『報告』は、各大学等の入学者選抜の改善を促しつつ、各大学のアドミッション・ポリシーとの整合性を図ることを前提に、入学者選抜において、英語力を測定する「資格・検定試験」のうち4技能を適切に測定する試験の活用が奨励されるべきであるとしている。
そのため、大学、高校及び中学校の学校関係団体、テスト理論等の専門家、「資格・検定試験」の関係団体等からなる「協議会」を設置し、入学者選抜に際し、「資格・検定試験」が適切かつ効果的に活用されるような指針づくりを早急に進めることを求めている。
有識者会議は、国に対して4技能測定の指針づくりに向けた検討が迅速に進むよう、専門的な助言などの情報提供等に努めることを求めている。そして、『報告』では4技能の適切な測定に資する指針づくりにおける検討項目として、次のような例を挙げている。
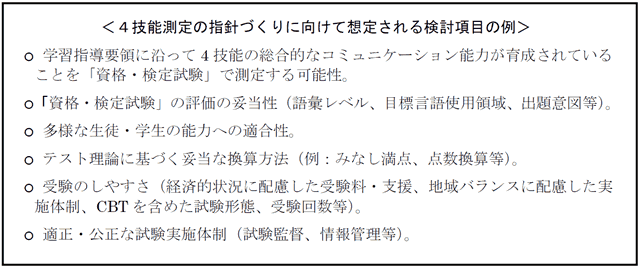
『報告』では、「協議会」において、現状の学力検査等における英語問題の在り方の調査・分析等を行い、得られた結果が大学、高校等において活用が図られるよう広く情報発信などを行うことを求めている。
改革4 教科書・教材の充実
◆ 小学校の教科書
小学校高学年では英語の“教科化”に伴い、教科書が整備されるまでの間、国において新たな教材を開発・検証・配布する必要があるとしている。
また、小学校高学年では、中学年での外国語活動を継承し、中学校での学習への円滑な接続を踏まえながら、アルファベット文字の認識、日本語と英語の音声の違いやそれぞれの特徴、語順等への気付きを促す指導に有効な教科書等の教材が必要であるという。
◆ 中学・高校の教科書
現在の中学・高校の教科書は、文法事項を中心とした言語材料の定着を図る様々な活動に分量の多くがとられている。そのため、言語材料を活用しながら、説明・発表・討論を通じて、思考力・判断力・表現力等を育成するような言語活動の展開が十分に意識されていないものも見られるという。
教科書等の作成・活用に当たっては、次期学習指導要領の改訂で、そうした課題を見直し、英語力育成の趣旨をより徹底するとともに、「教科用図書検定基準」の見直しに取り組むことが適当であるとしている。
ICTを効果的に活用することによって教育上の効果が期待されることから、今後、国は“デジタル教科書・教材”の導入に向けて検討を進めるべきだとしている。
また、デジタル教科書・教材が導入される際には、教科用図書検定の対象となる教科書には“音声や映像データ”が含まれるという考え方を明確にすることを求めている。
改革5 学校における指導体制の充実
〇 23年度に小学校高学年に外国語活動が導入されて以降、多くの学校で学級担任と外国語指導助手(ALT)をはじめ、英語が堪能な外部人材とのティーム・ティーチングによる指導体制の整備・充実が図られてきた。
一方、授業準備等の時間確保、教員の指導力、小・中学校の連携の具体的な工夫が課題として指摘されている。
〇 『報告』は、小学校では中学年と高学年の接続が円滑に行われることを前提に、
○ 中学年では、主に学級担任が、外国語指導助手(ALT)や英語が堪能な外部人材とのティーム・ティーチングも活用しながら指導し、
○ 高学年では、学級担任が英語の指導力に関する専門性を高めて指導するとともに、専科指導を行う教員を活用することにより、専門性を一層重視した指導体制を構築する必要があるとしている。
〇 小・中・高校の教員免許状取得に関し、大学における教職課程において英語力・英語指導力を充実する観点からの改善を求めている。
今後、教員養成全体の議論(中教審教員養成部会、小中一貫教育特別部会など)の中で検討が必要であるとしている。
〇 教員免許状を有しない者のうち、十分な英語力・指導力を有する人材に「特別免許状」を積極的に授与した上で活用するとともに、英語が堪能な地域人材や英語担当教員の退職者等を非常勤講師として活用する方策を講じることを検討すべきであるという。
また、現職教員の研修を充実させ、きめ細かな指導が行われる環境整備も求めている。
* * *
小・中・高校の各学校における教育課程編成の基準となる学習指導要領は、昭和22(1947)年の「試案」発行(「告示」は昭和33<1958>年から)以降、高校では平成21年3月「告示」まで、8回改訂されている。
その間の外国語(英語)についても、各時代の社会的要請や教育環境の変化などを背景に、英語教育の目的や目標、指導内容、科目編成などが改訂されてきた。高校「英語」を中心に、これまでの英語教育の変遷を概観してみる。(以下、図1参照)
1 「文法訳読」主流の昭和30年代後半~昭和終期
昭和30(1955)年代の学習指導要領は、高度経済成長に向かって、それまでの生活経験、生活学習に重点を置いた「経験主義」から、系統的知識の習得を重視する「系統主義」へと転換されていった。
高校「英語」についても系統学習、知識教育が主体で、指導内容では「読み方の分野」に重点が置かれ、「聞き方・話し方の分野」の学習量は学年進行とともに漸減されていた。
昭和31年度実施の学習指導要領では、英語はドイツ語、フランス語などの外国語とともに、「第一外国語」(3~15単位)及び「第二外国語」(2~4単位)に位置づけられ、「聞き方、話し方、読み方、書き方」の基本的な知識・技能を養うことが目標に掲げられた。この時点では、外国語(英語)は“選択教科”であった。
昭和35(1960)年告示の学習指導要領(以下、英語)では、「英語A」(9単位:4技能使用に重点)と、“大学進学希望者”を主な対象とした「英語B」(15単位:文字言語に重点)に再編され、外国語は“必修教科”となった。大学進学者を主な対象とした「英語B」にみるような「文法訳読」主流の英語教育は、基本的に平成元(1989)年の学習指導要領改訂まで続くことになる。
そうした大勢の中で、昭和45年告示の学習指導要領では、「音声」や「語法」などの能力の育成とともに、選択科目として「英語会話」(3単位)が登場した。
2 「コミュニケーション」重視の平成時代
1.国際理解とコミュニケーション能力の育成(平成元年3月告示)
平成元年3月告示(6年度実施、9年“新課程入試”実施)の学習指導要領には、言語の構成要素として「コミュニケーション」という用語が登場し、国際化に対応した資質・能力を養う観点から、外国語(英語)によるコミュニケーション能力の育成が盛り込まれた。
具体的には、「オーラル・コミュニケーションA」(O.C.A:会話)/「オーラル・コミュニケーションB 」(O.C.B:聴解)/「オーラル・コミュニケーションC」(O.C.C:討論)の3科目(各2単位)を新設し、このうち1科目を選択履修にした。
なお、昭和35年(告示)で必修教科となった外国語(英語)は、45年(告示)に再び選択教科になり、53年(告示)・平成元年(告示)とも選択教科に位置付けられていた。
2.「英語」必修化/「実践的コミュニケーション能力」の育成(11年3月告示)
11(1999)年3月告示(15年度実施、18年“新課程入試”実施)の学習指導要領では、“実践的なコミュニケーション能力”の育成を明記するとともに、「オーラル・コミュニケーションⅠ」(O.C.Ⅰ:2単位)又は「英語Ⅰ」(3単位)のいずれか1科目を“選択必履修科目”とし、「英語」を“必修教科”に位置づけた。
また、11年の改訂では、「生きる力」(中教審『21世紀を展望した我が国の教育の在り方について』<第一次答申:8年7月>)の育成が盛り込まれたが、その基本理念の一つである「自ら学び、自ら考える力」の育成を英語教育においても具現化させ、従前以上に実践的なコミュニケーション能力の活動を推進していく狙いが伺える。
3.共通必履修科目:「コミュニケーション英語Ⅰ」設定/英語による授業(21年3月告示)
21(2009)年3月告示(25年度全面実施、28年“新課程入試”全面実施)の学習指導要領では、「生きる力」の理念を継承するとともに、高校教育の共通性と多様性のバランスを重視し、学習の基盤となる国語、数学、外国語に「共通必履修科目」を設定した。外国語は「コミュニケーション英語Ⅰ」(3単位。2単位まで減単可)を全ての高校生が履修する共通必履修科目とし、「積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成」の観点などから、「授業は英語で指導すること」を基本としている。
高校の学習指導要領の流れをみると、英語教育の根底には「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能の習得をおくものの、各時代の社会的な背景の下で言語観や指導法などによって、英語教育はその内容を変てきたといえる。
高校「英語」は前述したように、昭和30年代~40年代の大学進学者用の「英語B」に代表される“文法訳読”中心の系統的な知識教育と、昭和40年代の「英語会話」にみるような言語行動に視点を当てた技能教育の昭和時代を経て、4技能活用(総合)の所謂“コミュニカティブ”な4技能・伝達教育の平成時代へと移り変わってきたことが伺える。
もちろん、4技能・伝達教育においても、系統的知識教育や技能教育は内包されているとみるべきであろう。(図1参照)
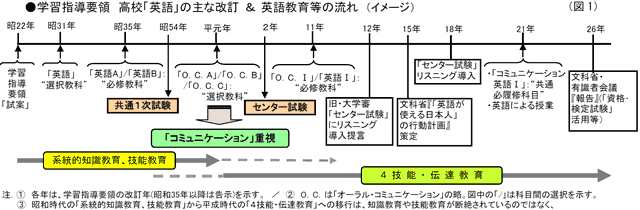
* * *
学習指導要領は、英語の“4技能”を総合的に育成することを前提としており、大学入学者選抜で各技能を総合的に評価するようなバランスのとれた入試が求められる。
しかし、大学入学者選抜における英語力の評価をみると、「読む・書く」の“ペーパーテスト”が大勢で、「聞く・話す」の“音声テスト”は少数である。そして、「読む・聞く」の“受信技能”の評価が主流で、「書く(自由作文等)・話す」の“発信技能”の評価は少なく、アンバランスな4技能評価である。
他方、高校側や受験生はこうした大学入試に対応した受験対策上、英文の理解や語法・文法といった「文法訳読」に学習時間の多くを費やしているのが現状である。
つまり、学習指導要領に準拠した教科書による“表の授業”では4技能の総合的な習得を目指しつつ、「受験英語」のために“裏の授業(学習)”では「読む・書く」(ペーパーテスト対策)主体の知識・技能の向上を目指すといったいわば“二重学習”が学年の進行とともに、あるいは進学校ほど多くみられる。
なぜ、「受験英語」の多くは、「読む」「書く」の2技能中心なのか。その背景としては、大学側の英語教育についての考え方や試験実施上の課題(音声テスト)などが挙げられる。
高校での英語教育は前述したように学習指導要領に則って、「知識教育」主体からコミュニカティブな「伝達教育」(実践的なコミュニケーション能力の育成)主体へと移ってきた。
他方、一般的に大学の英語教育は、「実践的コミュニケーション能力」よりも、高度な英文読解力や英作文力、英文による研究論文の作成などの知識・技能の育成に重きを置いているところが多いようだ。大学での“伝統的な英語力”育成の背景には、「実践的コミュニケーション能力」の育成を消極的に捉える傾向が少なからずあるのではないか。
こうした英語教育に関する高校側と大学側とのギャップが、中学や高校の英語教育に大きな影響を及ぼし、受験生には「受験英語」として二重の負担となっている。
ただ、最近は大学側にも旧来型の「文法訳読」に替えて、新たな英語力の評価システムを開発する動きがみられるようになってきた(後述)。
◆ 「共通1次試験」創設時から構想されていた「音声テスト」
大学入学者選抜に直接的に関わり、学校での英語教育や受験対策にも大きな影響を与えている英語の「音声テスト」としては、センター試験の「リスニング」が挙げられる。
英語教育の改善には、大学入学者選抜に「音声テスト」を導入するのが効果的であるとの観点から、まず、センター試験の前身である「共通1次試験」(昭和54<1979>年~平成元<1989>年)の準備段階で英語の出題の一部として「音声テスト」(聴解テスト)の試行が行われていた。
しかし、共通1次試験には導入されず、その後も「音声テスト」の実施条件等の調査・研究が行われ、「試験室の広さに応じて適当な数のスピーカーを適切に配置すれば、受聴(座席)位置による音響的な差を有意差以下に抑えることが可能」とする報告も出された。
こうした中、平成元年の学習指導要領改訂で「オーラル・コミュニケーション」に係る3科目が創設され、言語の音声面や発信・受信能力がより一層重視されるようになった。
これを受け、9年の“新課程”(当時)入試ではセンター試験「英語」にいよいよリスニングが導入されるのかという見方もあったが、結局、導入には至らなかった。
◆ ICプレーヤーの登場で、「リスニング」導入
センター試験に「リスニング」が導入されたのは「共通1次試験」開始から27年、「センター試験」開始から16年経った18年“新課程”(当時)入試からである。それは、「オーラル・コミュニケーション」3科目創設の改訂告示から、20年近く後である。
それほどセンター試験「リスニング」導入に時間を要したのは、50万人以上の受験者を対象に、全国一斉・同時間帯に公平性を確保して実施することが難しかったためといえる。
前述したように、スピーカーを適切に配置するなどして音響条件をある程度整えることは可能とされたものの、“音声”という物理的な制約を受ける「音声テスト」は「筆記試験」と異なり、試験の公正・公平性の観点から直ちに実施に踏み切れなかったようだ。
因みに、音響条件を整えやすい高校教室での実施も一時検討された。
他方、英語のコミュニケーション能力重視の下で、50万人以上が受験するセンター試験でのリスニング(「聞く力」の測定)の必要性が当時の大学審議会答申『大学入試の改善について』(12年11月)で提言され、さらに15年3月には英語教育を抜本的に改善するための『「英語が使える日本人」の育成のための行動計画』の策定(文科省)において、18年センター試験から「リスニング」導入の目標が明記された。4技能の一つである「聞くこと」の能力測定をセンター試験に導入する機運は、一気に高まった。
そうした状況の中、試験実施の公平性などの課題に対しては、スピーカー方式に替えてICプレーヤーを使った個別音源方式の試験実施が可能になり、音響条件の均一性の問題がほぼ解消されたことで、18年センター試験から「リスニング」が導入された。(図1参照)
◆ センター試験「英語」の「筆記試験」と「リスニング」
ところで、センター試験の「筆記試験」の標準配点は200点満点、「リスニング」は50点満点である。両者の最近の得点率をみると、「筆記試験」はほぼ6割以上を維持しているが、「リスニング」は最近上昇傾向にあるものの、過去9回の試験で4割台が2回ある。
センター試験の「リスニング」導入は受験生に英語の“音声”についての関心度を高め、英語学習における音声技能の重要性を認識させているとみられる。
ただ、受験生にとっては、配点の高い「筆記試験」(各大学の個別試験にもつながる)を意識した長文読解(速読即解)や語彙・文法といった「文法訳読」優先の学習が行われているとみる。センター試験の「筆記試験」と「リスニング」の得点率の推移をみると、「筆記試験」の比較的“安定”に対し、「リスニング」の“アップ・ダウン”からも受験生の英語学習の傾向が伺える。(図2・図3参照)
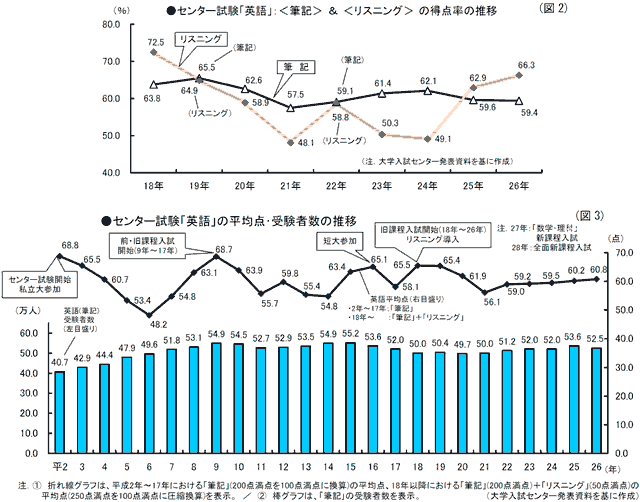
「音声テスト」における「聞くこと」の能力測定はセンター試験をはじめ、各大学の個別試験でも少数ながら実施されている。特に最近はグローバル化に対応し、難関・上位の国立大-理系学部の前期試験でもリスニングを課す傾向が高まっている。
しかし、「話すこと」の「音声テスト」の実施は、センター試験はもとより、各大学でもほとんど実施されていない。
また、学校現場でも「話すこと」の音声学習は他の3技能に比べて少ないとみられ、生徒(受験生)にしてみれば「リスニング」対策として「聞く力」を付けても、結局、「話す力」を評価する試験がなく、「聞く ⇔ 話す(返す)」といった“生きた”音声学習につながらないという実感もあるようだ。「音声テスト」が抱える大きな課題といえる。
英語教育の改善は、前述した学習指導要領の改訂を基軸にこれまで度々、様々な観点から行われてきた。特に高校「英語」は、平成元年の学習指導要領改訂告示以降、従前の「文法訳読」主体から「実践的コミュニケーション能力」の育成へと大きく舵を切った。
これに伴い、センター試験に18年から「リスニング」が導入されたものの、「スピーキング」の導入には至っていない。また、各大学の入学者選抜においても前述したように、英語の“4技能”全てをバランスよく評価するような選抜はほとんどみられない。
コミュニカティブな学習指導要領実施(平成6年)から20年、「聞く・話す」能力を含むコミュニケーション能力を適切に評価する大学入学者選抜の具体的な改善策を提起した『「英語が使える日本人」の育成のための行動計画』から11年経つが、生徒(受験生)、学生の英語学習の意識や意欲、教員の指導の在り方等に大きな影響を与えている大学入学者選抜はほとんど変わらず、4技能をバランスよく評価する「資格・検定試験」の活用も十分には進んでいない。
有識者会議は上記のような状況を抜本的に改善するために、同会議の下に英語教育に係る入学者選抜の在り方を検討する「英語力の評価及び入試における外部試験活用に関する小委員会」(以下、小委員会)を設置し、①英語力の評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用に関する基本的考え方/②具体的な今後の活用推進方策についての検討、議論を集中的に行った。その提言内容は先述の「改革3」(英語力の評価と入学者選抜の改善)に盛られているが、ここでは大学入学者選抜を中心に「資格・検定試験」の活用の意義や具体的方策など、小委員会の提言をさらに詳細にみてみる。
小委員会では、グローバル化が急激に進展する中で、“総合的な英語力”を向上させるためには、世界標準を視野に入れた目標設定を行うとともに、小・中・高校を通じてコミュニケーション能力に必要な「聞く」「話す」「読む」「書く」の“4技能”が総合的に育成され、その各技能が適切に評価されることが必要であるとしている。
そして、学習指導要領を踏まえた中学・高校における英語教育と、大学及び高校入学者選抜との整合性を確保しつつ、コミュニケーション能力の育成に必要な4技能をバランスよく伸ばすことができるよう、各大学・高校の教育理念・内容等に応じたアドミッション・ポリシーを踏まえつつ、既に広く認められている「資格・検定試験」を活用することは意義のあることであるとしている。
「資格・検定試験」を活用する際は、その有効性と課題を明確にした上で、生徒・学生が自ら主体的に学び、英語によるコミュニケーション能力の向上を図る一つの客観的な指標として4技能をバランスよく測ることができる効果的な試験を活用することを提言している。小委員会が例示した「資格・検定試験」の有効性と課題は、次のとおりである。
◆ 有効性
○ 4技能の総合的な測定 / ○ 試験の一貫性、実施可能性の確保
○ 生徒・学生の英語学習への動機づけとして活用(生涯にわたり主体的に学習に取り組む態度の育成) / ○ 「聞く」「話す」を中心に教員の指導改善の手段となる 等
◆ 課 題
○ 目的、難易度、換算方法、受験環境、実施場所、実施時期、受験費用 等
小委員会は、「資格・検定試験」の入学者選抜等への具体的な活用促進策として、次のような事項を挙げている。
◆ 「資格・検定試験」の活用では、学習指導要領に沿って中学・高校卒業までに学習した4技能が総合的に育成されているかという観点からの適正な評価が必要。
そのような観点から、生徒等の英語力を客観的に把握するため、
○ 国による資格・検定試験団体と連携した生徒の英語力調査を進めるとともに、
○ 4技能を測定する「資格・検定試験」のうち、CEFR(前述の「学習到達目標(CAN-DO形式)」の項参照)との関連を考慮しつつ、
・国際的に広く受け入れられている試験 / ・国内で開発され広く受け入れられている試験を、在学中の英語力の評価や入学者選抜において積極的に活用することを促進。
◆ 資格・検定試験団体と連携した生徒の英語力調査を通じて、日常学習による生徒の英語力の測定と学習状況に係る現状や課題を把握・分析し、それらの結果を活用して、生徒の学習意欲を喚起するとともに、教員の指導改善にいかすことにつなげる。
このほか、各大学のアドミッション・ポリシーとの整合性を図ることを前提にした「資格・検定試験」の活用促進や4技能測定の指針づくりに向けた検討項目、「協議会」の設置などを挙げており、それらは先述の「改革3」に明記されており、参照されたい。
◆ 「資格・検定試験」の比較、換算
様々な「資格・検定試験」を入学者選抜に活用するに当たり、それらの試験をどう客観的に比較するのか。その妥当な換算方法などを検討する「協議会」の設置が提起されているが、文科省は今回の有識者会議の入学者選抜改善に係る小委員会において、各試験団体のデータによるCEFRとの対照表を提示している。
例えば、「英検1級」はCEFRの「熟練した言語使用者」 (C2・C1レベル)のうち「C1レベル」に相当/TOEFL iBT(120点満点)では「110点~120点」に相当するなどとしている。
◆ 「みなし満点」制度
センター試験や大学の個別試験などの「本試験」の英語において、満点に匹敵すると推定できるような高い実力を、指定の「資格・検定試験」の4技能試験で示すことができた生徒(受験生)には、申告により“英語に満点を与える”という「みなし満点」制度が今回の小委員会でも提起されている。
当制度では、例えば、TOEFL iBT80点(4技能それぞれ最低15点以上クリア)を1年以内に取得していれば、本試験の「英語」は“満点とみなす”という措置である。
文科省は毎年、各国公私立大に当該年度の入学者選抜に係る基本事項、実施上のガイドライン等を明記した『大学入学者選抜実施要項』を通知している。この中で「資格・検定試験等の成績の利用」について、次のように奨励している。
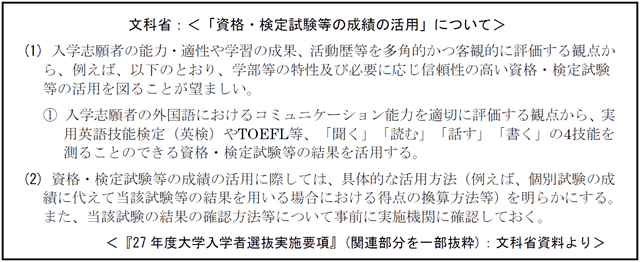
「資格・検定試験」を大学入学者選抜に活用している大学は、740大学中265校、35.8%(25年度大学入学者選抜:文科省調べ。以下、同)である。
大学設置別では国立82大学中16校(19.5%)/公立81大学中18校(22.2%)/私立577大学中231校(40.0%)で、私立大の活用度は国公立大の2倍ほど高い。
また、入試形態別の活用をみると、「一般入試」が34校(国公私立740大学に占める割合4.6%)/「推薦入試」が206校(同27.8%)/「AO入試」が142校(同19.2%)で、「推薦・AO入試」に比べて「一般入試」での活用は低調である。これは、「推薦・AO入試」がその出願要件に「資格・検定試験」の成績を挙げている場合があるためとみられる。
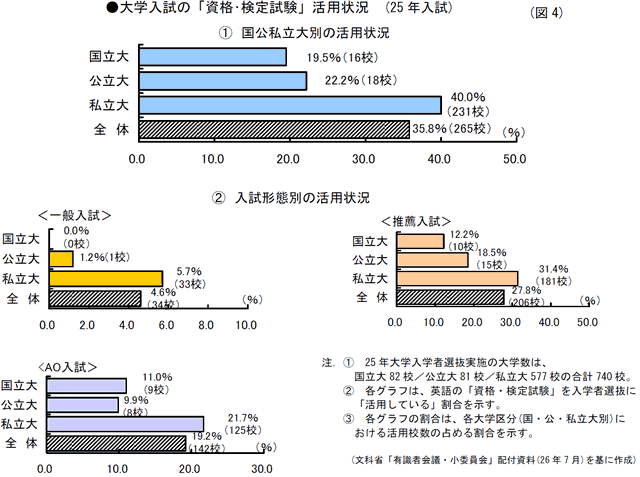
* * *
グローバル化の進展に伴い、国際共通語である英語との関わりは、様々な分野においてこれまで以上に増している。これから先、学校・大学以外、日常生活や仕事などにおいて、どれほど多くの人間が英語と直接関わっていくかはわからない。
しかし、少なくても経済・産業社会で活躍していくためには、現状のような受験のためだけの所謂「受験英語」では、将来、立ち行かなくなることは確かであろう。
「受験英語」は、かつてないグローバル化の大波に晒されている。
大学で学習や研究をする際に必要とされる、英語で資料や文献を読む/英語で講義を受ける/英語で意見を述べる/英語で文章を書くなど、アカデミックな場面での総合的な「英語運用力」をより正確に測定するテストが開発されている。
このテストは、大学入学者選抜を想定したもので、上智大及び英検を実施・運営する日本英語検定協会が共同開発した4技能型アカデミック英語能力判定試験「TEAP(ティープ)」(Test of English for Academic Purposes)で、レベルは英検準2級~準1級程度とされる。
こうした大学と資格・検定試験団体とのアカデミックで総合的な「英語力」測定の共同開発テストは、今後、大学入学者選抜の評価尺度として、その導入拡大が期待される。
大学入学者選抜の英語が「聞く」「話す」「読む」「書く」の“4技能”をバランスよく評価することになれば、高校をはじめとする英語教育全体に好影響を及ぼすことになろう。
しかし、センター試験の「リスニング」導入の経緯からもわかるように、現状で特に「スピーキング・テスト」をセンター試験からかわる“新テスト”や個別試験に直ちに導入することは難しいとみる。そのため、「資格・検定試験」やTEAPのような大学と資格・検定試験団体との共同開発テストを大学入学者選抜に活用することは有意であるといえよう。
ただ、現状の英語教育、学習環境で大学入学者選抜に4技能評価の「資格・検定試験」を導入することについては、次のような問題点も指摘されている。
例えば、「聞く・話す」の音声技能は、生徒(受験生)が置かれている音声に関する物理的環境(ALTの配置や音響機器も含めた音響面の整備)に大きく左右されがちで、特に学校での学習が十分とはいえない「スピーキング」の評価を“選抜”に使うことに対する公平性の問題などがある。こうした課題を解消していくためには、ALTの配置を増やしたり、ICTを整備・活用したりするなど、国の更なる財政支援が必要だ。
いずれにしろ、「受験英語」は現在、中教審で検討、議論されている高大接続の構築に係る“大学入試改革”と相俟って、当分の間は「資格・検定試験」の活用などによって“使える英語”へと変身していくものと期待したい。
