25年4月、大学は3年ぶりの高卒者数・大学受験生数増の下で実施した入試を終え、60万人程度の新入生を迎える。
ところで、25年国公立大「一般入試」の志願者数は、センター試験志願者数・受験者数がともに前年比3.2%増加したにもかかわらず、1.0%減少した。特に国立大では、後期試験が4.9%も減少し、前・後期試験全体で2.3%減少した。
これはセンター試験(1次試験)の成績によって各大学・学部への「2次出願」を決める際、センター試験の平均点の大幅ダウンが強く影響した結果とみられる。中でも「国語」は、第1問(評論)に出題された難解な『鐔』(つば)や第2問(小説)の難化で過去最低の平均点となり、受験生は“国語ショック”で、「弱気・慎重」の2次出願に走ったようだ。
* * *
大学進学適齢期である18歳人口は、平成4(1992)年の204.9万人を直近のピークに、途中、13年と22年に若干の増加があったものの、24年まで減少の一途をたどってきた。
高卒者数も18歳人口とほぼ同様の傾向で推移してきた。大学受験生数(以下、受験生数)についても18歳人口や高卒者数と同じような動向である。
こうした状況において、25年は18歳人口が123.1万人(前年比3.4%増:旺文社推定。以下、同)、高卒者数が109.0万人(同、3.2%増)、受験生数(実数)が2.7%増の68.2万人と、いずれも3年ぶりの増加が見込まれている。
志願者の動きをみると、国公立大「一般入試」志願者数(以下、「一般入試」に限定)は、一般的には18歳人口や高卒者数の増減に連動し、受験生数の動向にも連動している。
ただ、最近では、23年に高卒者数・受験生数がともに減少したにもかかわらず、国公立大志願者数が増加。また、25年は23年と逆で、高卒者数・受験生数の増加(旺文社推定)に対し、国公立大志願者数は減少した。(図1参照)
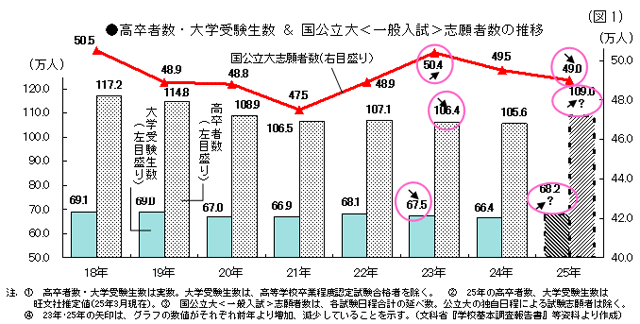
23年の国公立大志願者数は、リーマンショック(20年秋の世界同時不況)以降の一段と拍車がかかった国公立大志向、前年のセンター試験(以下、セ試)難化によるリベンジ組(難関・上位国公立大への初志貫徹組など)も含めた既卒者の増加、セ試志願者数の増加(セ試現役志願率アップ)と平均点アップ(易化)、及び公立4大学の「分離分割方式」(一般入試)への新規参入などで2年連続の増加となり、5年ぶりに50万人を超えた。
25年の国公立大志願者数減の要因は、後述する。
国公立大志願者数の増減は、一般的に18歳人口や高卒者数の増減がベースになるが、セ試平均点(難化、易化)、経済事情、大学への現役志願率、既卒者の志願動向、セ試の現役志願率・志願者数、入学定員・募集枠の変更、前年の入試動向(倍率アップ・ダウンの反動等)など、様々な要因が組み合わさった結果である。
国公立大への進学志望者は、セ試を受験した後、「自己採点」結果とセ試受験科目の全国平均点等との比較、志望大学(学部)の合格可能性、個別試験(2次試験)の入試科目・配点などを基に受験大学(学部)の出願先(「2次出願」)を決める。
こうした国公立大個別試験への「2次出願」に当たっては、セ試の平均点アップ・ダウンによる影響が大きい。一般に、平均点アップだと“強気出願”、逆に平均点ダウンだと“弱気・慎重出願”の傾向がみられる。
国公立大への「2次出願」は、一般にセ試平均点の“アップ・ダウン”によって影響されることを前述したが、「国立大志願者」の動きを基軸に公立大や私立大も含めて、セ試平均点のアップ、ダウンそれぞれの志願者の動向パターンを概観してみる。
セ試の平均点がアップ(易化)すると、受験生は“強気”となり、国立大の「中堅大」志望者は「準難関大」へ、「準難関大」志望者は「難関大」へと、合格の難易ランクを順次上げていく“強気出願”の傾向がみられる。
また、「中堅大」の国公立大志望者は都市部の「難関公立大」へ、国立大の「準難関大」志望者においては国公立大「医学部」への出願(初志貫徹)もみられる。
この結果、国立大・公立大とも全体としては“志願者増”の傾向となる。
他方、私立大では、国立難関大志願者の「難関私立大」併願や私立大専願組の「安全志向」などにより、「難関私立大」→「準難関私立大」への流れがみられる。(図2の①参照)
前述の23年入試は、ほぼこのパターンに当てはまる。
ただ、最近はセ試平均点がアップしても、長引く経済不況で「安全志向」「現役志向」などから“慎重出願”が強まり、“強気出願”に繋がらない“安全・確実出願”も目立つ。
セ試の平均点がダウン(難化)すると、受験生は“弱気”になり、上記とは逆の動きがみられる。
すなわち、国立大の「難関大」→「準難関大」→「中堅大」、及び国立大の「中堅大」→ 地元「公立大」、「難関公立大」→「地元公立大」、国公立大「医学部」→ 国立大「準難関大」(歯・薬学部等)といった、難易ランクを落とす“弱気・慎重出願”の傾向がみられる。
そのため、全体としては“国立大で志願者減、公立大で志願者増”の傾向が現れる。
私立大については、「国立難関大」志願者の「準難関私立大」併願などから、「準難関私立大」→「中堅上位私立大」といった動きがみられる。(図2の②参照)
25年入試はこのパターンに当たり、志願者数は国立大で前年比2.3%減少したのに対し、公立大では2.7%増加、国公立大全体では1.0%減少した。
また、難易ランクの高い国立大ほど減少率は高く、25年の場合、所謂「難関大」では前年比4%以上、「準難関大」で1%以上、「中堅大」で1%未満のそれぞれ減少である。なお、いずれも医科系、工・技術系、教育系、芸術・体育系等の単科大は除く。
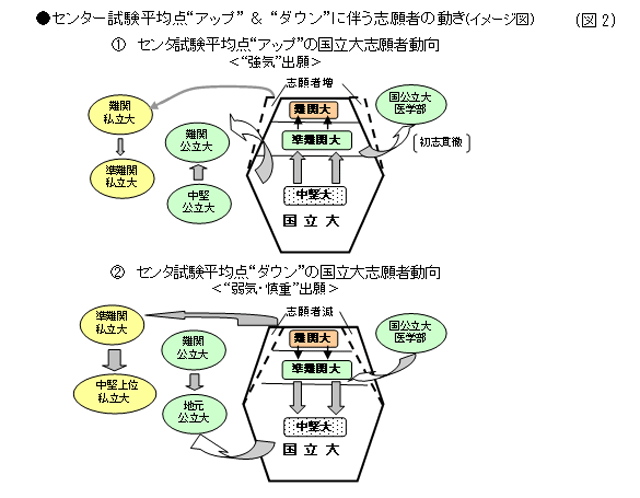
* * *
セ試は大学志願者の「高等学校段階における基礎的な学習の達成度を判定する」という“目的”(目標準拠型の“達成度テスト”=絶対評価)と、セ試を利用する大学(短大含む)に対し「当該大学入学者を選抜するための基礎資料を提供する」という“機能”(集団準拠型の“選抜テスト”=相対評価)といった“二面性”をもっている。
すなわち、セ試は「大学や短大の志願者」の高校段階での基礎的な学習の達成度を測る試験で、「全ての高校生(高3生)」を対象にした基礎的な学習の達成度を測る試験ではない。そのため、出題教科・科目も現行では6教科・29科目(英語は筆記、リスニング出題)の多岐にわたり、出題レベル(難易度)は“平均点6割程度”を目安に出題されている。
セ試は、全ての国立大及び公立大(セ試を課さない試験方式も併用する1大学・1学部を除く)の「一般入試」受験者にとって必須の共通試験であるだけに、セ試平均点のアップ・ダウンは例年、前述したように志願者動向に大きな影響を与えている。
そこで、現行課程入試の始まった18年以降のセ試平均点の動きをみてみる。
セ試は例年、1月13日以降の最初の土曜日及び翌日の日曜日に「本試験」、その1週間後に「追・再試験」が実施される。「本試験」の平均点等は実施された週の半ば(水曜日)に「中間集計」が大学入試センターから発表され、2月初旬には「本試験」の各科目の受験者数、平均点、最高点、最低点、及び標準偏差の「確定値」が発表されるほか、「追・再試験」も含めた各教科・科目の受験状況等、セ試実施結果の概要が発表される。
◆ 「基幹3教科」の平均点
● 地歴、公民、理科の「第1解答」と「第2解答」
24年セ試から、地理歴史(以下、地歴)と公民の「試験枠」が統合され、試験枠[地歴、公民]の10科目から最大2科目の選択、受験が可能になった。
また、理科も科目選択の弾力化を図るため、24年から3グループの試験枠が統合され、試験枠[理科]の6科目から最大2科目の選択、受験が可能になった。
これに伴い、志望大学(学部)のセ試利用が“1科目利用指定”の場合、当該受験生は“本命1科目”に絞って「2科目選択・受験」(2科目試験枠)を「事前登録」し、「第1解答科目」の解答時間(60分)を、「第2解答科目」(本命科目)の解答に充てることもできる(国立大では1科目利用指定の場合、全て「第1解答科目」の成績を利用)。
このため、地歴、公民、理科の各科目の得点には「第1解答」と「第2解答」の得点が混在し、これら3教科においては各科目の平均点の実態が把握しにくい。
● 国語・数学・英語の「基幹3教科」の平均点合計
上記のような状況を踏まえ、旺文社ではセ試平均点の動向をみる一つの視点として、国公立大の文系・理系に共通の“基幹3教科”である「国語」、「数学」(数学Ⅰ・Aと数学Ⅱ・Bの2科目)、「英語」(筆記とリスニング)の平均点合計(600点満点)を大学入試センターから発表される科目別平均点等の確定値を基に算出している。
* 25年「基幹3教科」の平均点合計
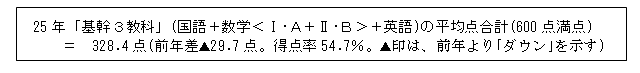
* 「基幹3教科」平均点の推移
18年~25年の「基幹3教科」の平均点合計をみると、現行課程入試が開始された18年の高得点(376.6点、得点率62.8%)から25年の低得点(328.4点、同54.7%)まで、18年のピークを除くと、22年を中心にほぼM字カーブを描いて推移している。
18年~25年まで8回実施されたセ試で「基幹3教科」の得点率が60%以上になったのは18年と20年(362.7点、同60.5%)の2回のみである。(図3参照)
● 国語、数学、英語の平均点
18年~25年までの「国語」(200点満点)/「数学」(数学Ⅰ・A+数学Ⅱ・B:200点満点 )/「英語」(筆記+リスニング<250点満点>を200点満点に圧縮)の各教科の平均点をみてみる。
3教科の中では、「英語」が一番高く(最高131.0点<18年>~最低111.2点<21年>)、過去8回の得点率の平均は60%を超えている(得点率60%以上は8回のうち4回)。
「国語」(最高125.5点<18年>~最低101.0点<25年>)と「数学」(最高121.1点<24年>~最低103.0点<19年>)は過去8回の得点率の平均がともに50%台後半で、60%以上の年は「国語」(18年、20年)、「数学」(18年、24年)とも2回に留まる。
なお、「国語」の平均点については、<古文>(配点50点)と<漢文>(同50点)の成績を合否判定に利用しない大学・学部が国公立大の一部、セ試利用私立大の多くにみられるが、それらの大学・学部を志望するセ試受験者の得点も含まれていることに留意する必要がある。(図3参照)
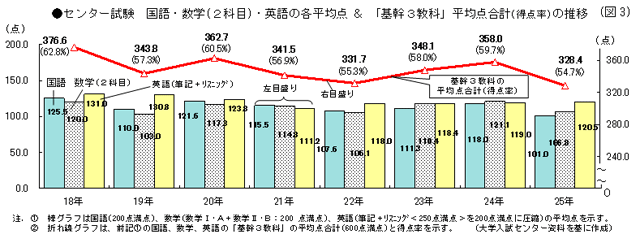
◆ 「5教科6科目」の加重平均点
国立大ではセ試「5教科7科目以上」(文系型:国語+地歴・公民から2科目+数学2科目+理科1科目+外国語/理系型:国語+地歴・公民から1科目+数学2科目+理科2科目+外国語)が定着しており、大学・学部ベースで9割以上、募集人員ベースで8割近くに達している。
公立大でのセ試は3~5教科に分散しており、「5教科7科目以上」を課す大学・学部は3割台、募集人員ベースで2割台に留まる。
こうした状況を踏まえ、国公立大の文・理系型に共通のセ試「5教科6科目」(上記の「5教科7科目以上」において、地歴と公民を合わせて1教科・1科目とした加重平均点<100点満点>、理科1科目とした加重平均点<100点満点>などの合計800点満点)の加重平均点も算出した。
* 25年センター試験「5教科6科目」の加重平均点
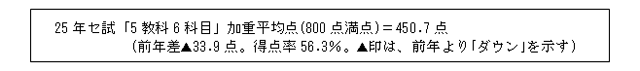
* 「5教科6科目」加重平均点の推移
セ試「5教科6科目」の18年~25年の推移をみると、平均点のアップ・ダウンの形は前述した「基幹3教科」とほぼ重なる。すなわち、「5教科6科目」の加重平均点における得点率60%以上は、18年(503.7点、得点率63.0%)/20年(485.7点、同60.7%)/24年(484.5点、同60.6%)の3回である。そして、25年は前年より33.9点(四捨五入の関係で図4の「25年-24年」と一致しない)もの大幅ダウンとなる450.7点(得点率56.3%)で、18年以降最低になった。(図4参照)
● 25年センター試験の主な科目の平均点と前年との得点差
25年セ試の主な科目の前年との平均点差(+印は前年より「アップ」、▲印は「ダウン」を示す)は次のとおりで、軒並み平均点ダウンになっていることが見て取れる。
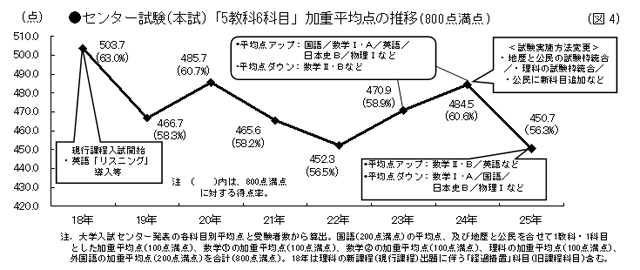
・平均点アップの主な科目:現代社会=+8.4点/数学Ⅱ・B=+4.5点/英語=+1.5点(<筆記+リスニング>:「筆記」▲5.0点、「リスニング」+6.9点)/世界史B=+1.5点など。
・平均点ダウンの主な科目:数学Ⅰ・A=▲18.8点/国語=▲16.9点/倫理=▲10.2点/「倫理、政治・経済」=▲6.5点/日本史B=▲5.8点/物理Ⅰ=▲5.3点/生物Ⅰ=▲2.7点/政治・経済=▲2.5点、/化学Ⅰ=▲1.5点/地学Ⅰ=▲0.8点など。
例年、セ試では英語に次いで受験者の多い国語(25年受験者約51.6万人)が25年の平均点を大幅に下げて、国公立大志願者減の引き金にもなった。 そこで、「共通1次試験」(昭和54<1979>年~平成元<1989>年)と「セ試」(平成2年~)を通して、昭和54年~平成25年までに実施された35回(共通1次試験=11回、セ試=24回)に及ぶ国語の得点率の推移を図5に示した。 国語の得点率は、概して「共通1次」時代と「セ試」時代の前半(平成9年まで)はほぼ60%以上(昭和62・63年はわずかに60%割れ)の高得点率、それ以降は、現行課程入試開始(18年~)当初はやや高かったが、ほぼ50%台半ば~後半で推移している。 因みに、「共通1次」時代における国語の得点率の平均は60%台半ばで、得点率60%未満の試験は11回中、2回のみ。一方、「セ試」時代における国語の得点率の平均は60%未満で、得点率が60%未満だった試験は24回中、14回に及ぶ。(図5参照)
最近の国語の平均点は、22年の平均点107.62点(得点率53.81%)をボトムとして23年111.29点(同、55.64%) → 24年117.95点(同、58.97%)と、2年連続アップ。得点率も60%直前まで回復していた。
しかし、25年は前年より16.91点ダウンの101.04点で、得点率も50.52%まで低下。
共通1次試験も含め、これまで実施された35回の国語の試験では、平成15年(国語Ⅰ・国語Ⅱ)の平均点101.08点(得点率50.54%)を0.04点(得点率で0.02ポイント)下回り、過去最低となった。(図5参照)
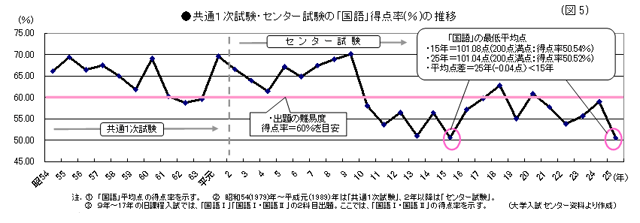
セ試「国語」の出題は、「近代以降の文章」 (第1問<評論>:配点50点、第2問<小説>:配点50点)/「古典」(第3問<古文>:配点50点、第4問<漢文>:配点50点)の大問4題(200点満点)の構成が定着している。
前述したように、<古文>と<漢文>については国公立大の一部、及びセ試利用私立大の多くで合否判定に用いない大学(学部)がみられる。そのため、国語の受験者にとって必須であり、セ試の得点にも大きく影響する「近代以降の文章」、つまり第1問、第2問の平均得点率をみてみる。
なお、ここでのデータは、大学入試センターでは各科目の大問別の平均点等を公表していないため、旺文社の調査(セ試受験者の自己採点による「大問別平均点」集計)による。
18年~25年の第1問、第2問の平均得点率をみると、調査対象者の水準等を反映し、全体に高い得点率を示しているといえよう。
そうした中で、25年の平均得点率は第1問、第2問とも、18年以降8回実施された試験で最低を示しており、特に第1問は60%を切っている。(図6参照)
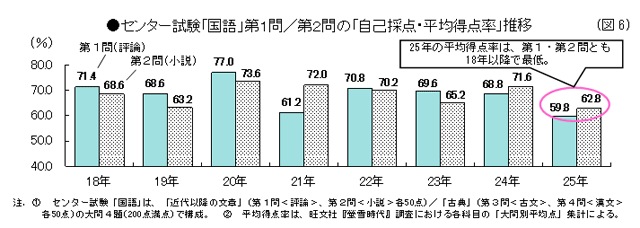
25年セ試「国語」の第1問は、幅広い分野の近代批評家として知られる小林秀雄(明治35<1902>年~昭和58<1983>年)が60歳(昭和37年)のとき、総合芸術雑誌の連載に発表した随想『鐔』(つば)を題材にしている。小林秀雄は焼き物や骨董にも熱中し、鐔も手許において、その美の世界を独自の鑑賞眼で綴っている。
小林秀雄の文章は、その難解さでかつては受験生泣かせであったが、最近はあまり出題されていなかった。第1問に出題された『鐔』は、全文(24年セ試より約600字多い約4,200字)が掲載され、「注」が冒頭の鐔についての“図解”も含めて21箇所にも及ぶ。
セ試受験者にとって馴染みのない刀の鐔をテーマにした難解な問題文が試験初日の国語の第1問に配置され、受験者の多くは出鼻をくじかれたのではないか。
また、『鐔』はこれまでの“セ試の「評論文」の傾向”と異なり、独創的な文体と詩的な表現は筆者の論理の分析や要旨の把握、出題者の意図をくみ取った選択肢の演繹的な選定などといった解答手法も一筋縄ではいかず、戸惑った受験者も多かったとみられる。
なお、25年は小林秀雄誕生111年、没後30年の節目で、当の総合芸術雑誌はセ試実施の6日後、『鐔』の一節と小林旧蔵の桃山時代の鐔の写真を掲載した特集を出している。
第2問は、小林秀雄とも交流のあった小説家・牧野信一(明治29<1896>年~昭和11<1936>年)の『地球儀』(初出:大正12<1923>年)の全文を掲載している。
『地球儀』は、小説の中に“小説”を挿入する重層的な構成で、登場人物の状況把握、当時の英語教育を反映したカタカナ英語の台詞回しなど、受験者には馴染みの薄い題材で、設問も難しかったようだ。
* * *
国公立大の「一般入試」(以下、「一般入試」に限定)は、セ試(1次試験。以下、「1次」)の得点(ごく一部の大学・学部等では第1段階選抜のみに使用)と、各大学・学部等で実施される個別試験(2次試験。以下、「2次」)の得点の合計で合否を判定する。
1次と2次の「配点比率」は各大学・学部、試験日程等で異なるが、募集人員の約80%を占める前期試験では、1次の比率が2次より高いところが多い。また、小論文・面接等を主体とする、あるいは2次を課さない後期試験では、1次の比率がより高くなっている。
ただ、難関大(学部)では「2次比率」50%以上が多く、中には80%以上のところもある。
国公立大入試では、セ試の得点が多くの場合、決め手となる。そのため、今回のようにセ試平均点が大幅に低下すると、セ試の配点比率の高い大学・学部、特に国立大後期試験などでの志願者減(25年国立大:前期=0.4%減、後期=4.9%減、全体=2.3%減)が目立つ。
ところで、前述したセ試の前身である「共通1次」時代、「1次試験の結果が大事!」という受験対策における教訓と、「一事が万事」(一事を見れば他もすべて同様だと想像できる)の諺をかけて、「1次が万事!」といわれていた。これは、単に共通1次試験の得点が高い、低いだけでなく、教科・科目に偏らない基礎・基本的な学習の習得が大切で、「1次試験の結果を見れば2次試験も推して知るべし」といった教訓でもあった。このことは、現在の「セ試」と「個別試験」の関係についても同じことがいえる。
「1次(センター試験)が万事!」において、前述したようなセ試の目的と難易度を鑑みたとき、今回の国語の第1問や第2問の出題はセ試受験者にとってどうだったのだろうか。
セ試受験者にとって初日の“国語ショック”はセ試平均点大幅ダウンの引き金ともなり、その後の入試にも影響したとみられ、特に国立大「2次出願」の減少にもつながったようだ。
