田中眞紀子文科大臣は、大学設置・学校法人審議会(以下、設置審)が設置「可」と答申した25年度設置認可申請の秋田公立美術大(公立)、札幌保健医療大(私立)、岡崎女子大(私立)の3大学について、24年11月初め、突然“不認可”を表明した。設置審の「可」とする答申を文科大臣が覆したことは過去30年間に例がなく、社会的にも波紋を広げた。
田中文科大臣は当初、大学の数の多さや質の低下、設置審の見直しなどを挙げて不認可としていたが、最終的には3大学の新設を認め、今回の設置認可“騒動”はひとまず落着した。
そこで、ここでは大学の量的規模等に係るこれまでの推移、それに関わる施策や設置認可、背景、及び大学の“量”と“質”の関係などについてまとめた。
* * *
現在、大学数で8割近く、学生数で7割以上を占める私立大を中心に、戦前の旧制大学時代、及び戦後の新制大学発足から18歳人口激増期の昭和40(1965)年代頃までの大学の量的規模に係る施策、その背景などをたどってみる。
まず、私立大創設の歴史を紐解いてみると、大正7(1918)年の「大学令」公布により、それまでの「私立学校」(専門学校)が次々と「大学」への昇格を果たし、大正15(1926)年までの大正年間だけでも総計22大学が昇格している。これらの私立大には、法律学校や宗教系の系譜をひくものが多い。
そして、昭和15(1940)年頃の旧制「大学」(帝大、官立大、公立大、私立大)の数は50校(旧外地に設置した大学含む)近くで、学生数約8万人であった。
昭和20(1945)年8月の太平洋戦争終結によって、日本は連合国軍の占領下に置かれた。連合国軍の総司令部の要請を受けアメリカから派遣された「教育使節団」は、昭和21年3月、日本の教育改革の基本方策をまとめた『報告書』を総司令部に提出。総司令部では、教育・文化担当部局のCIE(民間情報教育局)を通して、『報告書』に示された教育理念や改革方策によって戦後の教育改革を進めるよう日本側に求めた。
日本政府はこれを受けて「教育刷新委員会」(文部大臣の諮問機関となる中央教育審議会<中教審>の前身)を内閣に設置し、昭和22年には戦後教育の柱となる「教育基本法」や「学校教育法」を制定し、戦後教育の体制をつくりあげた。
占領期の新教育制度の下、昭和24(1949)年度には新制の私立大92校(23年度に11校)が誕生し、国立大は24年度70校、公立大は23年度1校、24年度17校が発足した。
ところで、当時の私学(私立大)行政に関しては、文部省(当時)やCIEだけでなく、私学関係団体、組織も政策形成等に関与していたようだ。その結果、私立大は建学の精神や特色が尊重され、国(文部省)の監督・権限が縮小されて私立大の自主的な運営による健全な発展に期待がかけられた。こうして、私学の発展を制度的に保障した「私立学校法」が昭和24年11月に制定されたのである(昭和25年3月施行)。
私立学校法の制定により、私学(私立大)の設置は戦前に比べて容易になり、私学行政は所謂“レッセフェール”(放任主義)的政策からの再出発となった。
ただ、その半面、以後の私立大の量的拡大の許容、高等教育全体のグランドデザイン策定の難しさなどを招き、その影響は今日に至るまで少なくないとみる。
◆ 中教審の『三八答申』、『四六答申』の指摘
昭和30(1955)年代~昭和40年代にかけ、私学に対する“レッセフェール”的政策は、当時の急増する大学進学志望者の受け皿と相俟って、私立大の急激な新増設をもたらし、受益者負担(学生の学費負担)による私立大依存型の高等教育機関を拡大させた。
また、この時代の私立大は大幅な定員充足率の上昇(所謂、“水増し入学”)などで教育環境や教育の質の低下を招き、“マスプロ教育”などと酷評された。そして、学生の大学教育への批判・不満や私立大の学費値上げ反対運動は、昭和40年代に国公立大も巻き込み全国の大学で激しく吹き荒れた「大学紛争」の引き金ともなった。(図1参照)
こうした状況は、昭和30年代後半には大学関係者や教育関係者の間で懸念されていた。この時代の大学教育や学校教育全体についての様々な課題に対し、中教審は『大学教育の改善について』(昭和38年1月答申:『三八答申』)で「高等教育機関の全体的な規模(学校数、学生数)、配置、及び設置についての計画的な検討」など、また『今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について』(昭和46年6月答申:『四六答申』)で「高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助・調和の必要性」など、それぞれの答申で高等教育の“計画的整備”を指摘した。
◆ “レッセフェール”的政策の大転換 ~ 私立大の新増設抑制 ~
文部省は上記のような中教審答申、とりわけ『四六答申』の指摘を受け、昭和51(1976)年3月には戦後初の“高等教育計画”(後述)である『昭和50年代前期計画』を策定した。
他方、昭和40年代に入ると、私立大の急激な拡大、経営基盤の脆弱さ、学生の学費負担などが問題とされ、私学行政は大きな転換期を迎えることになる。
まず、昭和50年には、「国は私立大等の教育研究に係る経常的経費について、その“2分の1以内”を補助することができる」などとする「私立学校振興助成法」(昭和51年施行)が制定された。
そして、当法律の制定に伴い、私立大等の“量的拡大を抑制”するため、私立学校法の一部改正が行われ、「昭和51年4月~56年3月までの5年間は、私立大学、学部、学科の“新増設及び収容定員の増加を認可しない”こと」とされた。
こうした私学への国庫補助の制度化と私立大等の新増設抑制策は、私立大の量的拡大よりも質的向上を目指すもので、それまでの私立大に対する“レッセフェール”(放任主義)的な政策を大きく変えることになった。
文部省は、前述の中教審『四六答申』で指摘された「高等教育の全体規模、地域的配置などについての長期的見通しに立った国の計画策定の必要性」を受け、昭和51年度~平成16年度まで、5回にわたる「高等教育計画」を策定、実施した。
当計画では、18歳人口の増減等を踏まえた高等教育規模を想定し、大学等の新増設は原則、“抑制”とする措置が講じられた。(下記の概要、図1参照)
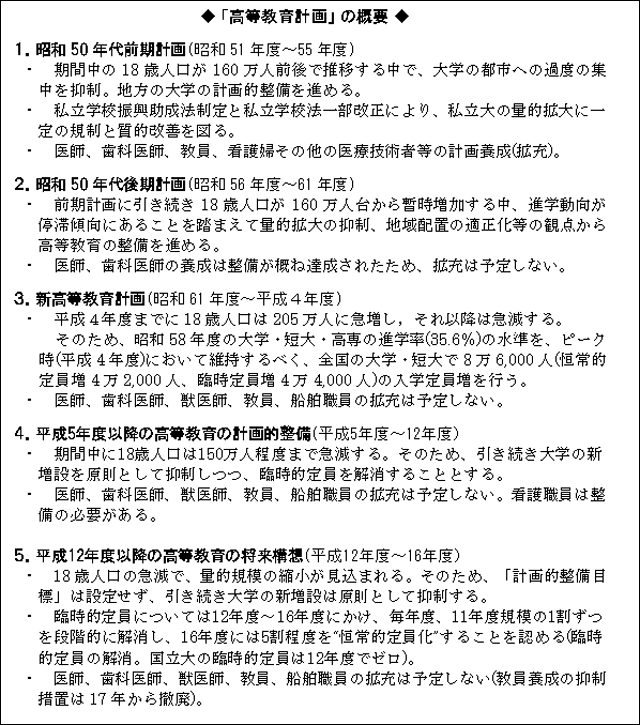
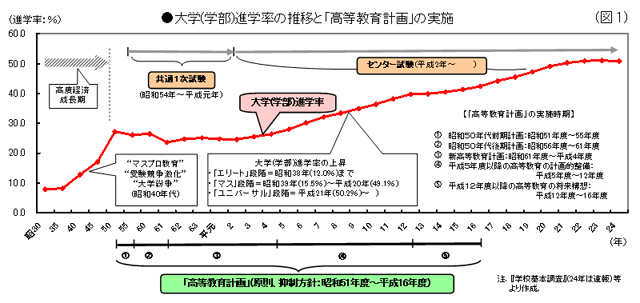
平成10年代には規制緩和をめぐる動きが活発化し、教育行政にも大きな影響を与えた。政府の「総合規制改革会議」の「高等教育における自由な競争環境の整備」(大学・学部設置等の認可に対する抑制方針見直し:13年12月)、中教審答申『大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について』(14年8月)における“量的規制の撤廃”及び“設置認可の弾力化”(15年4月から実施)等に加え、14年7月には「工業(場)等制限法」(首都圏と近畿圏の一部区域での大学等の新増設を制限)が“撤廃”(15年4月から実施)された。
文科省はこれらを踏まえ、「高等教育計画」以降、つまり平成17年度以降は、大学等の全体規模及び新増設についての“抑制的対応”の基本方針を“撤回”することになる。
◆ 中教審の『将来像答申』と政策転換
中教審は『我が国の高等教育の将来像』(17年1月答申:『将来像答申』)において、17年以降、27年~平成32(2020)年頃までに想定される高等教育の将来像(グランドデザイン)の内容と実現に向けた取り組むべき方策を提言した。
その中で、・18歳人口は約120万人規模で推移/・大学や学部等の設置に関する抑制方針が基本的に撤廃/・19年には大学・短大の「収容力」(入学者数÷志願者数<受験生数で実数>)が100%(志願者・入学者数とも67.4万人)になる、所謂“全入”を試算(19年の実績は90.5%)/・高等教育の量的側面での需要はほぼ充足/・今後は、分野や水準の面でも誰もがいつでも自らの選択で学べる高等教育(ユニバーサル・アクセス)の整備が課題などと指摘した。
また、大学設置に関する抑制方針の撤廃、大学の新設や量的規模の拡大、教育の一層の多様化に対しては、大学教育の「質の保証」が重要であると提言している。
文科省は前述の14年の中教審答申を受け、15年には大学・学部等の設置に関する抑制方針を基本的に撤廃した。そして、17年の『将来像答申』を踏まえ、先述のような「高等教育計画の策定と各種規制」から、「高等教育のユニバーサル段階における大学の緩やかな機能的分化と大学教育の質保証に向けた政策誘導」に政策手法を転換したといえよう。
◆ 公・私立大の量的拡大
ここまで、中教審の高等教育に係る提言や国の高等教育政策などを概観してきたが、平成期に入ってからの公・私立大もそうした政策の中で、看護・医療系を主体とする人材養成や地域の高等教育需要などへの対応から、大学・学部の新増設や短大から大学への改組・転換(短大=縮減、大学=拡大)といった“スクラップ&ビルド”による公・私立大の量的拡大が目立つ。
24年度現在、全国の大学数(24年度『学校基本調査速報』による。以下、同)は783校で、そのうち国立大86校(構成比11.0%)、公立大92校(同11.7%)、私立大605校(同77.3%)である。また、全学生数(学部、大学院、専攻科・別科等)は約287.6万人で、国立大生約61.8万人(構成比21.5%)、公立大生約14.5万人(同5.1%)、私立大生約211.2万人(同73.5%)。国・公・私立大に占める私立大の割合は、大学数で8割近く、学生数で7割強に達している。
なお、24年4月現在、学生募集停止や放送大学を除く大学数は771校(大学院大学含む)で、“学部募集”を行っている大学は741校(国立大82校、公立大80校、私立大579校)である。(図2・図4参照)
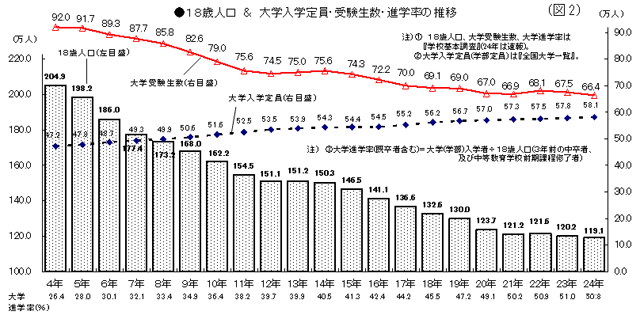
◆ 私立大の「入学定員割れ」
私立大の量的規模は前記のような状況にあるが、24年度に「入学定員割れ」となった私立大は264校、45.8%(集計数577校)に悪化し、全私立大(集計校)の「入学定員充足率」(以下、充足率)も過去最低の104.2%に低下している。(図3参照)
ここで注目されるのは、大学の規模や地域と充足率との関係である。
大学規模別の充足率をみると、小中規模校の入学定員割れが目立ち、24年度は「入学定員800人未満」の私立大は“入学定員割れ状態”に陥っている。また、地域別にみると、「大都市圏」ではほぼ入学定員を充たしているのに対し、「地方」では一部を除き、“未充足”地域となっている。なお、24年度の場合、「入学定員3,000人以上」の大規模私立大23校(全校数の4.0%)の志願者数は約148.8万人(延べ数)で、全私立大志願者の46.5%を占め、“強い大規模校の寡占化”を浮き彫りにしている。
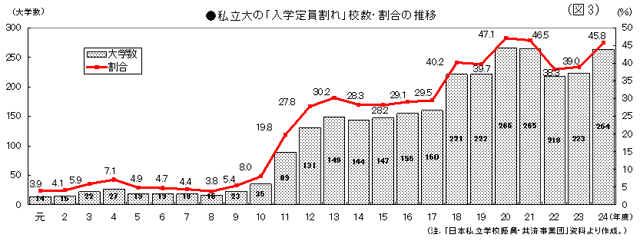
* * *
ここでは、大学受験動向から大学(学部。以下、同)の量的規模の側面を概観してみる。
● 大学進学率(大学入学者数÷大学進学適齢者数<18歳人口>。既卒者含む)は、昭和39(1964)年に15.5%と、それまでの高等教育の発達段階(高等教育研究の第一人者であるアメリカのマーチン・トロウによる)における“エリート型”(進学率15%まで)から“マス型”(同15%~50%)に移り(大学・短大では昭和38年に15.4%)、以降、昭和47(1972)年に20%台、平成6(1994)年に30%台、14年に40%台と上昇を続けて、21年には50.2%で最終段階の“ユニバーサル・アクセス型”(進学率50%以上)に達した(大学・短大では17年に51.5%)。24年は23年より0.2ポイント低下の50.8%で、22年ぶりに低下している。(図1・図2参照)
● 大学進学希望者(受験生)の増減率や進学率のアップ・ダウンには、高校生の「現役志願率」によるところが大きい。
近年の現役志願率(現役の大学受験生数<実数>÷高卒者数)は、19年51.8% → 20年53.5% → 21年54.9% → 22年55.7% → 23年55.4% → 24年55.0%と、最近は2年連続やや低下。それでも、高校生の2人に1人は大学を受験している。
因みに、センター試験の現役志願率は20年39.3% → 21年40.5% → 22年41.1% → 23年41.6%→ 24年41.6% → 25年42.1%で、25年は2年間の停滞から上昇に転じている。
● 大学の「収容力」は、19年89.0% → 20年90.6% → 21年91.0% → 22年91.0% → 23年90.8% → 24年91.1%と、最近は9割を超えている。
なお、24年度の大学数、学生数については、前述のとおりである。
● 大学進学適齢期である18歳人口は、平成4年の204.9万人を直近のピークに、途中、13年と22年に若干の増加があったものの、24年まで減少の一途をたどっている。
25年の18歳人口は前年比3%ほどの増加となる123.1万人が予測されるが、その後、平成32(2020)年頃までは後半に漸減するものの120万人前後で推移するとみられる。
● 24年度大学入試について、受験から入学までの人員規模は、およそ次のような流れだ。
24年3月卒業の高校生105.6万人のうち、大学志願者(受験生数。実数)58.1万人(現役志願率55.0%)と既卒者等8.3万人の合計66.4万人が、学部募集を行っている741大学・2,188学部(国立82大学・381学部/公立80大学・173学部/私立579大学・1,634学部)を受験した。
そのうち、60.5万人が入学(国立大10.1万人/公立大3.0万人/私立大47.4万人)を果たしている(収容力91.1%)。(図2・図4参照)
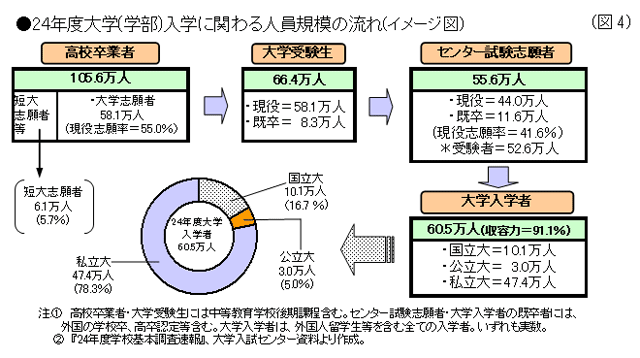
15年の“量的規制の撤廃”や“設置認可の弾力化”、及び「高等教育計画」終了(16年度)に伴う“抑制方針の撤廃”以降、大学政策は量的規模の規制から、教育の質保証に向けた施策へと軸足を移したとみる。
◆ 中教審の大学規模に関する検討
前記のような状況で文科省は20年9月、『中長期的な大学教育の在り方について』を中教審に諮問。その中で、大学の質保証と深く関わる大学の量的規模(人口減少期における我が国の大学の全体像)や組織・経営(ガバナンス、行財政システム等)などについての検討、審議を求めた。中教審は21年4月、大学分科会に「大学規模・大学経営部会」を設置して検討、議論し、23年1月までに4回の『報告』と『審議経過』を取りまとめている。それらの中で、大学の量的規模に関しては、次のような点を挙げて現状(当時:20年度)を分析している。
・人口減少期を迎えた一方で、国際的にも大学教育の改善・充実が大きな課題/・我が国全体としての進学率は上昇したが、依然として地域格差が大きく、国際比較でも高いとはいえない/・社会人・高齢者・留学生など多様な学生層の受入れの割合が欧米に比べて低い/・大学数は増加したが、大学と短大を合わせると平成13年度のピークより45校減少(20年度1,183校)/・大学の入学定員は増加傾向にあるが、これは短大から大学への転換による面もあり、大学と短大を合わせた入学定員は、11年度のピークより4万3,260人減少(20年度65万7,827人)など。
そして、今後は人口構造や産業構造、社会構造等が大きく変わる中での大学の果たすべき役割、大学の国際競争力の向上が重要な課題となることを踏まえ,“必要な規模”あるいは“政策的に望ましい規模”に着目した検討(分野別・地域別等)が必要であるとしている。
また、18歳人口が横ばい状態から再び減少傾向になるまでの間に、「ユニバーサル・アクセス」の充実とあわせ、「教育の質保証・向上」「組織・経営の基盤強化」といった課題に着手し、具体的に進めていくことを求めている。
◆ 公的な質保証システムと設置認可制度
大学教育の質保証・向上は、各大学の主体的な取組と実行に期待されるが、国としては「設置基準 → 設置認可審査 → 認証評価」といった公的な質保証システムを確立している。
ところで、大学の設置認可制度は、「大学」としての教育研究機関に相応しいことを公的に認定する制度といえる。
認定に当たっては、国際的に通用(グローバル・スタンダード)する「学位」を授与する機関として、それに相応しい「仕組み」(組織、経営など)や「質」を有していることを担保する必要がある。また、学生が安心して学修や研究の場として選択できるようにするためにも、それらを公的に担保する必要がある。
●「設置認可」の仕組み
大学の質保証の観点から、大学が“最低限満たすべき基準”として「大学設置基準」等を設け、それに基づき、公・私立大の設置や廃止等について、文科大臣が「認可」する。
具体的には、文科大臣は公立大や私立大の「設置認可申請」を受けると、「大学設置・学校法人審議会」(設置審)に諮問する。
設置審は大学設置基準等に適合しているかどうかなど、教育研究に関することを審査する「大学設置分科会」、及び私立学校法等に適合しているかどうかなど、財産・運営管理体制に関することを審査する「学校法人分科会」とで組織されている。
設置審が教育課程や教員組織、施設・設備、資金・財産状況などを審査し、問題がなければ設置を「可」とする答申を出す。文科大臣は答申を受け、設置認可を決める。
●「設置審査」の弾力化
大学の設置審査に関しては、平成3(1991)年の「大学設置基準の大綱化」を経て、「大学設置の原則、抑制方針の撤廃」や15年度審査から適用されている「届出制の導入」、「設置審査の準則化」(審議会内規等の審査基準を明確化して法令に規定し、内規を廃止)、16年度から適用されている「認証評価制度」の導入(全大学は7年ごとに国の認証を受けた第三者評価機関の評価を受けることを義務付け)などによる、所謂“「事前規制」から「事後チェック」へ”という“規制緩和”を基本とする審査体制が敷かれてきた。そのため、大学の設置等が増大するとともに、一部には質保証に関して懸念される点もみられるという。
このように、大学の質保証については、設置認可制度とも深く関わっている。
【速報: 「大学設置認可」 検討会の設置 】 ~ 「審査基準」、「事前規制」厳格化の方向感!
24年11月初めの田中文科大臣の設置審査に係る問題提起等を検討、議論する「大学設置認可の在り方に関する検討会」が24年11月下旬、文科省に設置された。
当検討会の委員は、大学関係者5名のほか、高校関係者2名、自治体の首長2名、企業関係者2名、公認会計士・NPO法人各1名の総勢13名。
検討事項は大学等の設置認可に関し、①「審査基準」の在り方/②「審査体制」の在り方/③「審査プロセス、スケジュール」の在り方、の3本である。
11月下旬の初会合に出席した委員の意見からは、教育は「規制緩和」に馴染まないとして、「審査基準」や「事前規制」の“厳格化”の方向感が伺える。
検討会では、1か月程度(年内)で提言をまとめたいとしている。
18歳人口・高卒者数の減少傾向の中、大学設置の原則、抑制方針の撤廃、大学設置基準や設置認可の弾力化などによって、公・私立大は急増してきた。
その一方で、私立大の4割以上(24年度45.8%)が“入学定員割れ”状態に陥り、入学金・授業料等の帰属収入で消費支出を賄えない“赤字”の私立大も4割程度(22年度39.2%)に達している。
また、大学受験生の9割以上(24年度「収容力」91.1%)が大学入学を果たす“全入”状態で、私立大では学力試験を原則として課さず、小論文・面接・実技などによる「推薦・AO入試」の入学者が5割を超えている(24年度50.5%)。大学の受験環境は、以前に比べて一部を除き大幅に緩和され、学生の学力低下にもつながっているとみられる。
大学過剰論の多くは、大学のこうした“負”の側面を捉え、大学の「需要」(受験生数、学生数)と「供給」(大学数、定員)のアンバランスや大学の質の低下などを指摘している。
政府の行政刷新会議(23年11月)の「提言型政策仕分け」では、大学の数や規模の過大を指摘し、その適正化を求めている。今回の田中文科大臣の設置認可をめぐる発言、問題提起はこうした大学過剰論によるとみられる。
大学の“量”と“質”の関係については、前述したように中教審でもこれまで議論、提言されてきた。最近では大学の量的規模に関して、『学士課程教育の構築に向けて』(20年12月答申。『学士課程答申』)と、『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて』(24年8月答申。『質的転換答申』)で、次のように提言している。
◆ 『学士課程答申』 ~ 「量か、質か」の“二者択一”論議は人材育成に不適 ~
『学士課程答申』では、大学教育が量的に拡大する中で質の維持・向上を図るという、重大な課題に直面しているとの認識を示している。そのうえで、大学教育の社会的意義や効用、その可能性を過度に低く評価して大学教育の規模を論ずることは“失当”であると断じている。
そして、大学教育の規模等を「量か、質か」といった二者択一で議論することは、人材育成等に関する国家戦略を誤ることにもなりかねないとしている。
ただし、大学の在り方について、大学教育の質の維持・向上に向けた努力を怠り、社会からの負託に応えられない大学は、“淘汰”を避けられないと断じている。
◆ 『質的転換答申』 ~ “ 大学減らし”は社会経済の停滞・萎縮に ~
『質的転換答申』は大学の量的規模に関して、大学進学率の水準が「過剰であるとの立場はとらない」と断じている。
そして、経済協力開発機構(OECD)データ(2009年)による日本の大学進学率(49%)は、OECD加盟国の平均(59%)を下回り、最近20年間では主要国で唯一、高等教育への進学者数が減っていると指摘。そのうえで、高等教育の規模の縮小は、社会経済の停滞・萎縮につながるばかりでなく、社会人の学び直しの場の提供など、大学の果たすべき役割の達成が難しくなるとしている。
* * *
先の「高等教育計画」(昭和51年度~平成16年度)以降、大学政策は大学等の量的規模に対する“抑制的対応”を解除し、大学教育の質の保証・向上/機能別分化・大学間連携の促進/大学組織・経営の基盤強化、といった施策を柱に据え、全体としての量的規模の目標設定を行わずに進められてきた。
他方、急速に進む超少子高齢社会とグローバル化の中にあって、大学の「役割・使命」と「量的規模」はどうあるべきなのか。新たな課題も生じている。
◆ 大学の役割・使命
大学の役割・使命についてはこれまで様々な側面で捉えられ議論されてきたが、それらは大学の設置形態によっても異なる。
国立大は国からの財政措置に大きく支えられ、国家的見地に立った人材養成、教育研究の国際競争力の強化、国家戦略上の中長期的な教育研究、最先端技術の研究開発、大規模施設・設備(経費)を要する教育研究などを担う。公立大は主に地方自治体の公的資金に依存しており、地域社会の特質に応じて、地域医療や看護・福祉の充実、産業の活性化などに対応している。私立大は、受益者負担を前提にしつつ、建学の精神に基づいて自主的・自律的に多様な教育研究を展開し、大学教育の7割以上を担っている。
こうした設置形態によって大学の役割・使命はそれぞれ異なるものの、その共通理念は教育基本法(大学条項)や学校教育法などで裏打ちされている。
ところで、大学進学率50%を超えた「ユニバーサル・アクセス」型の社会には、多種多様な大学が混在しており、大学の“質”と“量”を一律に論じるのは現実的でない。
この点に関し、たとえば、アメリカのカリフォルニアで“大学大衆化”に向けて制度化された「カリフォルニア高等教育計画」(マスタープラン)の高等教育システムは、今後の大学の役割・使命などを検討、議論するうえで参考になろう。
◆ “アクセル”と“ブレーキ”で計画的整備を!
大学の量的規模については、かつての「高等教育計画」のような“具体的な目標設定”を行う時期にきているのではないか。
量的規模の具体的な目標設定に当たっては、知識基盤社会(成熟社会)で想定される今後の社会・産業構造における人材育成/学問分野の継承(教育)・発展(研究)/地域社会・産業との連携(貢献)/ユニバーサル・アクセス(生涯学習、リカレント教育)や留学生受入れなど、大学の果たす多様な役割・使命等を十分考慮する必要がある。
こうした高等教育のグランドデザイン策定の下、大学教育の“質保証・向上”を大前提として、“設置認可・認証評価の厳格化”、“組織・経営の基盤強化”を進めていくべきである。
大学の数を減らして、大学の質を上げるといった単純な発想では解決できない課題が山積している。大学進学の受け皿を減らし、大学の「入り口」(入学者選抜)のハードルを高めれば一時的な“受験学力”は上がるにしても、それだけで学生の汎用的能力など、所謂「学士力」が高まり、教育の質が保証され、大学の役割・使命が十分果たせるようになるとは思えない。
これからの大学政策には、レッセフェール的な市場原理に任せるだけでなく、新たな「高等教育計画」の下で分野別、地域別など、きめ細かな量的規模の計画的整備をいわば“アクセル”(促進)と“ブレーキ”(抑制)を使い分けながら進めていくことが求められよう。
