23年3月11日の東日本大震災と福島第一原発事故では、“自然のメカニズム”を解明する「科学」の限界、“文明”を促進する「科学技術」の未熟さが浮き彫りになった。
また、個別の専門分野に特化した「科学」研究だけでは太刀打ちできない“自然の威力”や、「科学技術」がもたらす“ベネフィット”(恩恵)には“リスク”(危険)も潜んでいることを未曽有の災害によって思い知らされた。
次代を担う大学進学志望者は、今回の災厄であらわになった課題と向き合い、「地球科学」「原子力」「エネルギー」などの分野へ進み、一層の研究・技術開発への取組が期待される。ここでは、それらの分野に関係する学部・学科等を開設している大学・学部等を紹介する。
他方、被災した東北大や原発事故に直面した福島大などでは、全学横断的な新たな“災害科学”の研究拠点を創設し、安全・安心な社会の創生を目指す。
* * *
3・11の“予測を超えた”巨大地震と大津波、“収束困難”な原発事故では、地球科学、物理学、化学、工学等々の「科学」(ここでは専ら自然科学)と「科学技術」に対する人々の期待や信頼を失墜させてしまった。
「科学」(自然科学)の使命は“真理の探究”であり、“自然のメカニズム”を解明すること、つまり多様で複雑な自然現象を普遍的に(法則に則って)説明することであり、“未来を予測”する学問ともいえる。
一方、「科学技術」は“科学の成果”を“社会に活かす技術”であるといえよう。
そして、「科学」と「科学技術」は一体となって、これまで人間社会(文明)の発展に大きく貢献してきた。人々は「科学」や「科学技術」に過大ともいえる期待と信頼を寄せて、両者から身の丈を超えた“危うい恩恵”のみを享受してきたところに“3・11ショック”があるのではないか。
“3・11ショック”は、自然を相手に未来を予測することの難しさ、つまり現代「科学」の限界と、「科学技術」のもつベネフィット(恩恵)とリスク(危険)といった二面性を我々の前にあらわにした。
先ず、「地球科学」に係るこれまでの研究内容等の変遷を大まかにたどってみる。
我が国で「地球科学」(当初の地球科学は、惑星科学や気候・気象学等を除く、所謂、固体地球科学の分野を主体とする)という学問領域が確立したのは数十年前からで、それまでは産業を支える地下資源(鉱床)探査に専ら視座をおく鉱山地質学や資源地質学、構造地質学などの“地質学”を主体に、岩石学、鉱物学、古生物学などの分野と組み合わせて主に地質構造を調査、研究してきた。
地震学については、明治13(1880)年の横浜地震を契機に世界最初の地震学会「日本地震学会」が創設され(明治25<1892>年解散。昭和4<1929>年に現学会創立)、地震の計測や地学的諸現象、地震災害などについて研究されていたが、「地球科学」としての形をとるまでには至っていなかった。
他方、欧米では100年ほど前にドイツのウェゲナーが提唱した「大陸移動説」(大西洋をはさむ南・北アメリカ大陸とヨーロッパ・アフリカ大陸とがパズル合わせのようにはまることから、元は一体であった大陸が分裂、移動したとする説)に端を発する「プレートテクトニクス」理論が、1960年代以降に次々と提唱された。それとともに、地球内部の構造や物性等を研究する“地球物理学”が飛躍的に進展し、それまでの“固定された地球観”から“動く地球観”へといった“新しい地球観”が広まり、地球物理学的な見地に立った「地球科学」が確立、発展してきた。
「プレートテクトニクス」理論では、地球内部の深さ約100km以上の粘弾性をもつマントル(固体:岩石)内では放射性元素の崩壊熱などを熱源とする熱対流、すなわち「マントル対流」が起きており、その上に載る「プレート」(地殻と上部マントルからなる岩板)はマントルが沸き上がる海洋底の海嶺付近で誕生して水平方向に移動し、大陸縁の海溝付近でマントル内に沈み込んでいくという。プレートが沈み込んでいく際、陸側と海洋側のプレートの境界付近に“歪(ひず)み”がたまり、その弾性反発力によって、岩盤が破壊されてずれる(断層)。これが、陸と太平洋のプレートの境界付近で起こる震源の比較的浅い地震の大まかな仕組みで、今回発生した我が国観測史上最大の「東北地方太平洋沖地震」(マグニチュード<M>9.0)もこうしたメカニズムで起きた。
また、今回の巨大地震によって海底が上下方向に大きく動いたため、大津波も発生した。
日本列島は、陸のプレートの周縁で複数の海洋プレートがマントル内に沈み込んでいくという地球物理学的に特異な位置にあり、地震や火山活動などの地殻変動が活発で、地質構造も複雑である。そのため、日本でも1970年代に入ると「プレートテクトニクス」理論に基づく「地球科学」の重要性が認識され、地震学は急速に発達した。
地震や津波、火山噴火といった地殻変動に伴う自然災害、資源・エネルギー問題、地球温暖化や酸性雨、オゾンホールなど、人間生活と深く結び付いた「地球科学」として、「地球環境学」や「地球システム学」などの分野も発展している。こうした、地球規模の課題は、全地球的な視野に立ってそれぞれの専門分野と協働して研究に取り組む必要がある。
さらに最近では、“惑星としての地球”を研究する「地球惑星科学」など、「地球科学」の領域は以前のような固体地球科学の分野に留まらず急速に拡大している。
◇ 注目される「再生可能エネルギー」の研究・開発
原発事故を境に、「再生可能エネルギー」あるいは「自然エネルギー」といった用語がマスコミなどにも度々登場し、エネルギー問題に注目が集まっている。
「再生可能エネルギー」は太陽光や風力、水力、地熱、潮力、バイオマス(再生可能な生物由来の有機性の資源・エネルギー)など、資源の枯渇や発電時の二酸化炭素排出の心配がないエネルギーである。
化石燃料や原子力に代わるこれらのエネルギー資源は、いずれも「地球科学」と深く関わっており、この分野の今後の研究・開発が期待される。
原子力利用の歴史は110年余り前のレントゲン(放射線:エックス線発見)やキュリー夫妻(放射能、及び放射性元素:ポロニウム、ラジウム発見)などによる放射線や放射能の発見に始まり、これらは医学・医療分野における各種検査、診断、治療等のほか、工業、農業、文化(考古学などの年代測定等)など、幅広い分野で利用されている。
また、70年余り前にドイツでウランの核分裂現象が発見され、さらに核分裂反応で得られた原子力エネルギーは、第二次世界大戦の軍事目的として最初に利用された。
我が国では広島・長崎における世界で唯一の原爆被爆国という不幸な体験を踏まえ、原子力の開発と平和利用を目的とする『原子力基本法』(昭和30<1955>年12月)のもと、昭和41(1966)年に最初の商業用原子力発電所が稼動した。その後、石油代替エネルギー源としての原子力発電の導入が積極的に進められて各地に原発が設置され、21年度には全国の発電電力量の約3割を占めている。
菅首相は、“深刻な事故”(レベル7)を引き起こした福島第一原発事故を目の当たりにし、さらにM8程度の想定東海地震の30年以内の発生確率が87%とされていることなどから、浜岡原発(静岡県)の“全面停止”を電力事業者に要請した(23年5月中旬、全炉が停止)。また首相は、総電力に占める原発の割合を高めるとしていた政府の『エネルギー基本計画』(22年6月閣議決定)も白紙に戻して見直すことを表明している(23年5月中旬)。
ただ、我が国には現在54基(福島第一原発や停止中等を含む)の原発があり、菅首相は『基本計画』見直し表明で今後の電力供給について、「原子力については一層の安全性を確保する」などと述べており、直ちに原発が全廃されることはないとみる。
とはいえ、今回の原発事故で原発への不安・不信が一気に高まっており、化石燃料による地球温暖化問題と「再生可能エネルギー」論議などとが相俟って、今後のエネルギー政策の行方は不透明な状況にある。
* * *
未曽有の東日本大震災と甚大な被害を今なお及ぼしている福島第一原発事故では、地震予知や津波、防災科学、原子力工学、放射線医学、放射線被曝治療、原子力エネルギー、再生可能エネルギー、危機管理システム等、関連する様々な分野で人々の関心はこれまでにない高まりを見せている。特に原発事故については原発の当事者(事業者)はじめ、関係機関や専門家、マスコミなどがそれぞれの立場で情報の提供と解説等を盛んに行っている。
このような状況の中で大学進学志望者は、将来の進路選択に際して今回の災厄をどう捉えるであろうか。
地震・津波などの「地球科学」、原発・原子力エネルギーなどの「原子力」、再生可能エネルギーなどの「エネルギー」関係をそれぞれ扱う理学、工学分野を開設している大学・学部(学科)等は、もともと他の理学・工学系分野に比べて少ないうえ、特に「地球科学」や「原子力」関係の分野は国立大に偏っている。それだけに、これらの分野への進学志望者はこれまで多くなかった。
今回の災害と原発事故を踏まえ、「地球科学」や「原子力」、「エネルギー」分野への進学志望者が増え、地震・津波・火山など地球活動のメカニズムの解明と防災、地球環境の保全、既存する原発の安全・危機管理、使用済み核燃料や放射性廃棄物の処理等の技術開発はじめ、今後も拡大が予測される医学・医療、農業、産業等における安全・安心な原子力及び再生可能エネルギーの技術開発等の教育研究が一層促進されることを期待したい。
「地球科学」分野や「原子力工学」関係、「資源工学」分野への進路選択(進路指導)の参考に、それらに関係した学部・学科等や講座等を開設している主な大学・学部等を表1~表3にまとめた。
なお、「原子力工学」系は原子・原子核といった“ミクロの科学”から原子炉・加速器などの“巨大な工学システム”まで扱う、工学部でも特異な分野である。そのため、学部段階では主に基礎的な講義や演習を主体に行い、大学院で原子炉や核融合炉、加速器などの巨大システムを対象に専門的な研究、技術を修得していくところが多いようだ。
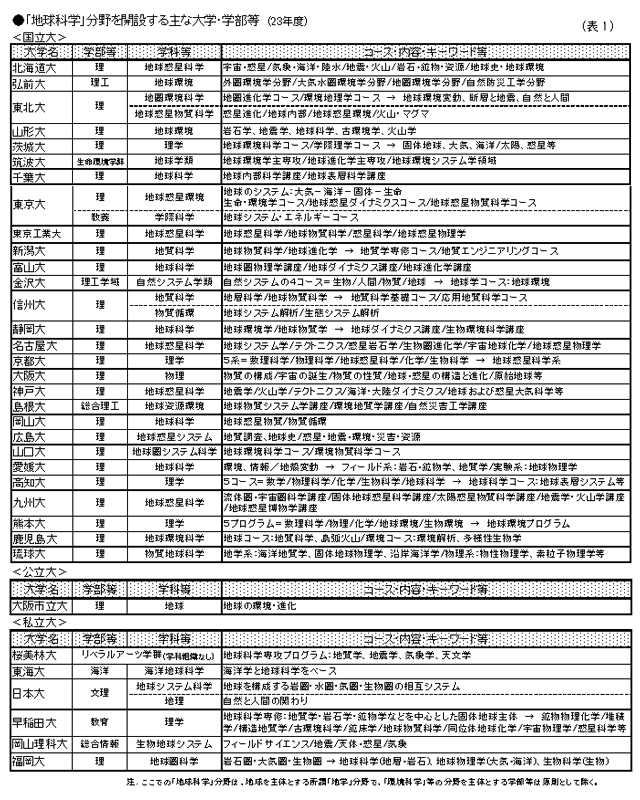
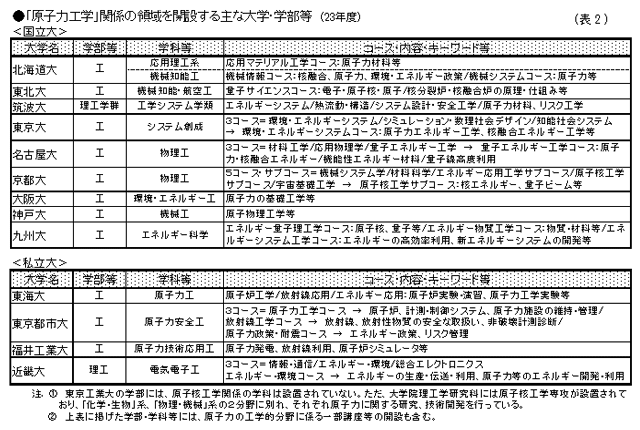
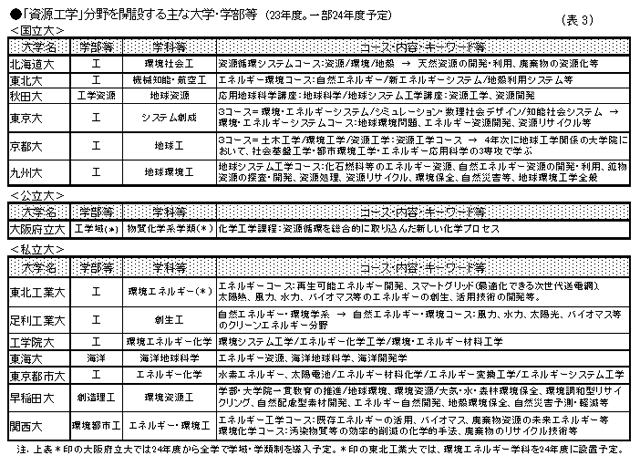
* * *
予測を超えた巨大地震、壊滅的な被害をもたらした大津波、未だ収束の目処がはっきりしない原発事故、それらの犠牲者・被災者の悲惨な状況を目の当たりにして、これまで大学が行ってきた教育・研究の「知の創造と伝承」、「人材育成」、「社会貢献」といった大学の役割、使命は十分に果たされてきたのだろうか、といった自戒の念すら大学人の間から聞かれる。
その一方で、未曽有の災厄から3ヶ月近くが過ぎ、被災地では復旧・復興、支援の取組が活発に行われている。特に、岩手・宮城・福島県内の各大学において様々な活動や取組がなされており、東北大・福島大などでは全学横断的な専門・複合領域の“災害科学”を研究する拠点づくりが始まっている。
被災地にあって世界的にも主要な研究大学である東北大では、貴重な研究機器や実験(分析)装置、教育・研究設備、建物などに多大な被害を受けた。しかし、震災後は迅速かつ精力的に復旧・復興に取り掛かり、各学部とも授業は5月9日から開始されている。
東北大では今回の大震災について、大学に関わる全ての人が、“想定外”を専門家の責任解除とすることなく、その責務としてこの不条理を克服する答えを示さなければならないという。そして、大震災を教訓に、学長を機構長とする全学横断的な組織体制システム『東北大学災害復興・地域再生重点研究事業』(仮称:図1参照)を立ち上げた(23年6月から実施予定)。当事業では、災害復旧・復興のみならず、“安全・安心な社会の創生”を目指した新たな人類社会へのパラダイムシフトに基づいて、復興・地域再生を先導する研究に既成の学問領域の枠を超えて戦略的・組織的に取り組み、その成果を政府の『東日本大震災復興構想会議』や自治体の「復興計画」等に提案、実践していくとしている。
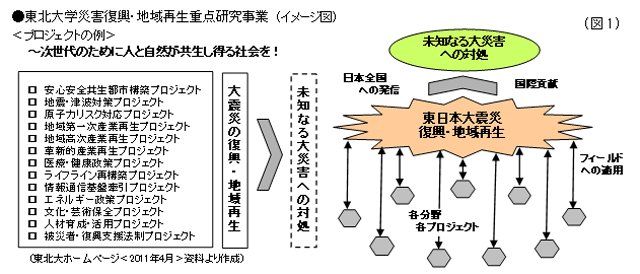
福島大は地震による建物等への損傷は大きくなかったようだが、今なお福島第一原発事故の影響に直面している。
大学では、構内の放射線量のモニタリングを行うなど安全な学習環境の確保に努めており、5月9日には新入生を迎え、5月12日から正規の授業を行っているという。
福島大では復興に向けた取組の一つとして、原発事故の後、放射線計測チームを立ち上げ、事故に伴う放射能の大気中への放出・拡散の実態を把握するとともに、今後の地域や世界に及ぼす影響を見積もり、地域の活動や復興計画の基礎資料として結果等を公表している。
大学では、この取組も含めて、学問分野や組織・機能の枠を超えた全学的な英知を集結し、新たな安全・安心な未来社会を構築するための『うつくしまふくしま未来支援センター』を創設し、“災害科学”の拠点として、災害復興の支援等を進めていくという。
ところで、東北大や福島大での取組のほか、岩手大でも岩手県の復興貢献を全学的な取組事業として組織的・継続的に実施する『岩手大学復興対策本部』を設置。都市や産業の再生に係る防災体制や復興計画の立案、地域の教育・文化の支援などを行うとしている。
☆ ☆ ☆
前述したキュリー夫人 (マリー・キュリー)は1898年、夫ピエールとともにピッチブレンド(瀝青ウラン鉱)から放出される放射線を測定して放射性元素ポロニウム(マリーの祖国ポーランドに因む)とラジウム(ラテン語の「放射」に因む)を発見し、放射線を放出して感光作用や蛍光作用を示す能力を「放射能」と命名した。
さらにマリーは4年後の1902年、不屈の精神力と忍耐力から元倉庫の劣悪な実験室の中でついに純粋ラジウムの分離(結晶化)に成功し、その存在を明らかにした。
キュリー夫妻が、暗夜の実験室で点々とほのかに光を放つ純粋ラジウムを目にしたときの喜びは、如何ばかりであったことか。マリーは、科学には偉大な“美”が存在し、研究室にいる科学者はただの技術者ではなく、おとぎ話のような感動を与える自然現象に向かっている子どもでもある、などと述べたという。
マリーは1903年に夫ピエールとともに放射現象に対する研究でノーベル物理学賞を、1911年にはラジウムとポロニウムの発見とラジウムの研究などでノーベル化学賞をそれぞれ授与され、2度のノーベル賞受賞者となった。キュリー夫妻の放射能やラジウムなどの発見は、がん治療などの医学分野をはじめ、物理学などの発展に大きく貢献している。
キュリー夫妻をはじめ、偉大な科学者の足跡をたどると、「科学」とは詰め込む知識ではなく、自然現象に感動するトキメキや未知の世界への興味・関心を出発点に、その秘密(メカニズム)を探究することであり、そこに「科学」の“美”がある、といえよう。
我が国は地震・津波・火山噴火、台風といった自然災害の脅威に常に晒されているうえに、少子・超高齢化社会、経済不況と財政難など、さまざまな国家的課題を抱える中、大震災の復旧・復興、原発事故の収束、エネルギー政策の再検討などに速やかに取り組まなくてはならない。
こうした課題に対処するために、「科学」の果たす役割は大きい。経済の安定していた一時期、“理科離れ”“文高理低”などといわれ、大学進学志望者の間で文系志望者の伸び率が理系志望者のそれを大きく上回っていたが、不況と雇用の悪化で最近は“理高文低”の傾向が強まっている。今回の災厄をバネに、「科学」の“美”を求める理系志望者のさらなる躍進を期待したい。
