我が国観測史上最大のマグニチュード(M:地震の規模を表す)9.0の巨大地震、大津波、そして最悪の事故評価「レベル7」の福島第一原子力発電所の事故。23年3月11日、太平洋三陸沖の深さ約25㎞で発生した「東北地方太平洋沖地震」は、その後も続いている大きな余震と誘発地震の引き金となっており、震盪するプレ-ト(岩板)に載っかる“地震列島・日本”の宿命と、人知の及ばない自然の威力を見せつけている。
他方、原発事故では原子炉の安定化と放射能管理の難しさを思い知らされている。
この二つの災厄は、災害時における未知のリスク情報の伝達の在り方をはじめ、これまでの自然観や社会観の転換までも我々に突きつけている。
ともあれ、「東日本大震災」と原発事故の災害に遭われた方々に報いるためにも、先ずは原発事故の処理、安定化に英知を結集して取り組むとともに、巨大地震や大津波の解明を一層深化させ、防災の教訓に、科学の進展に資する事例として後世に伝えていくべきである。
* * *
今回の震災と原発事故では、壊滅的な被害を受けた被災地や破壊された原子炉建屋の映像などとともに、目に見えない放射性物質の放出・拡散の状況、放射線量の数値などが繰り返し伝えられていた。
こうした映像や発表される放射線量の数値を見聞きし、先の定まらない放射能汚染とそのリスク評価などの不確実な不安定情報を一方的に、しかも見解や安全性の根拠の異なる複数の情報を受けると、福島第一原発の周辺地域に限らず、少なくとも東日本地域では誰しもがこれまでの日常生活では経験したことのない暗然とした未知の世界に突然放り出されたような重苦しい不安感に襲われたであろう。
一般市民にとって、原子力や放射能に関する正確な知識はほとんど持ち合わせていない。様々な情報を一方的に受けても自身の判断基準で読み解くことが難しく、適切な自己管理や行動がとれず、ただ徒に恐怖感や悲壮感、無力感だけを抱いてしまう場合も少なくない。
放射能汚染などに関する“風評被害”や“不要な買占め”、被曝に対する“偏見”には、こうした事情も背景にあるとみる。
特に原発事故に係る情報の発信には、当然のことであるが、原発の推進、反対の立場に偏ることなく、科学的根拠に基づいた客観的で正確な情報を的確に、丁寧に“わかりやすく”伝えることが重要である。
文部科学省では4月下旬、『放射能を正しく理解するために』と題する、教育現場及び保護者向けの資料を作成。教育委員会等を通して、全国の学校現場や保護者に対し、放射能の正しい理解と不安解消に努めている。
なお、当資料は文科省のHPに掲載されており、そのURLは下記のとおりである。
★『放射能を正しく理解するために』(文部科学省:23年4月20日)
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/04/21/1305089_2.pdf
★『保護者の皆様へ』
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/04/21/1305089_1.pdf
ところで、21世紀はグローバル化の進展とともに、知識・情報・技術が社会のあらゆる領域で基盤となる、所謂「知識基盤社会」の時代であるといわれている。
「東日本大震災」と原発事故は、正にこの「知識基盤社会」で起きた災害であり、そこで発信される情報を理解し、適切な行動をとるには、とりわけ「地震」や「津波」、「原子力」、「原子力発電」などについての基礎的な知識も一定程度必要となろう。
「地震」や「原子力」などについての基本的な学習は小・中学校の「理科」を中心に行われ、高校では「地学」や「物理」分野の科目、及び「科学と人間生活」で扱われる。
小学校では23年度から完全実施されている新学習指導要領(中学校では24年度から完全実施、高校では「理科」「数学」が24年度から先行実施)における理科の学習は、科学的な概念の理解など基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る観点から、「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」といった科学的領域の基本的な見方や概念を柱として、小学校、中学校、高校を通じて学習内容の構造化が図られている。
小・中学校、及び高校で、「地震」や「原子力」に関してどのように学習するのか、その学習項目等の概要を以下に紹介しておく。
なお、「原子力発電」「エネルギー問題」などについては、小・中学校の「社会」(中学校は「公民分野」)、及び高校の「公民」(「現代社会」の「環境」等)でも扱われている。
また、防災教育に関しては、小学校の「社会」(3年生~6年生)/中学校の「社会」(地理的分野)、「理科」(第2分野)、「保健体育」(保健分野)/高校の「地理歴史」(「世界史B」、「地理A」)、「理科」(「地学基礎」、「科学と人間生活」)などでも扱われている。
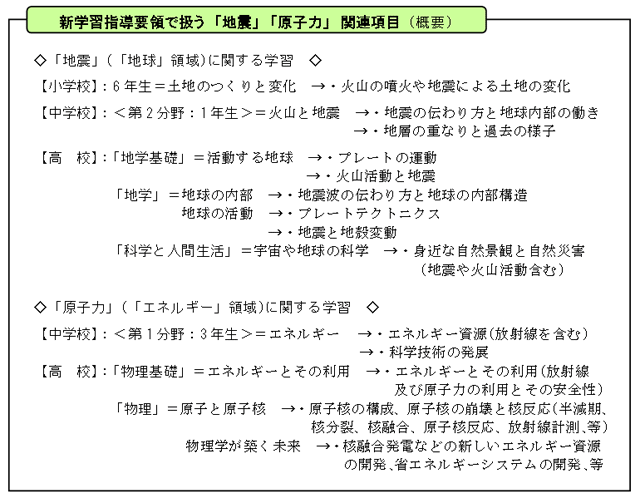
* * *
これまでの地震学の“予測”をはるかに超えた巨大地震と大津波。その発生のメカニズムや地震“予知”の実情などを探ってみる。
マグニチュード(以下、M)9.0の巨大地震「東北地方太平洋沖地震」は、宮城県牡鹿半島沖約130km、深さ約25 kmの海底で発生、宮城県栗原市で最大“震度7”を観測した。
東日本の太平洋側では、日本海溝付近から地球内部へもぐり込む「マントル対流」(深さ約100km以上の粘弾性をもつマントル<固体:岩石>内で起こる熱対流)に伴い、その上に載る「太平洋プレート」(地殻と上部マントルからなる岩板)の沈み込みによって、陸側と海洋側のプレートの境界付近に“歪み”がたまり、その弾性反発力によって、岩盤が破壊されてずれる(=断層)。これが、陸と太平洋のプレートの境界付近で起こる震源の比較的浅い地震の大まかな仕組みで、今回の巨大地震もこうしたメカニズムで起きた。
ただ、こうした海溝付近での「プレート境界型」の地震では、“M9”級の巨大地震は起きにくいとみられていたようだ。海溝付近では、海底堆積物によってプレ-ト深部に比べて軟らかく、陸側のプレートと太平洋プレートとの境界付近の歪みは“巨大地震”を引き起こす程、大きくならないと予測されていたようだ。宮城県沖では、M7級の地震は繰り返されていたが、連動して起きてもM8級と予測されていたとみられる。
また、今回の巨大地震で海底が大きく(5m以上)持ち上げられて海水が押し上げられたため、高さ10m前後から20m近くにも達する“大津波”が東北地方を中心に太平洋沿岸の各地を襲い、岩手県宮古市では標高約40mの内陸部まで津波が駆け上がった痕跡が認められたという。「東日本大震災」では特に津波による壊滅的な被害を受けたが、東北地方では貞観11(869)年に1,000人以上の犠牲者を出した「貞観の大津波」の記録もあり、最近は研究が進められていた。
今から88年ほど前の大正12(1923)年9月1日の正午前、京浜地帯を中心に関東地方一帯はM7.9の激しい地震に襲われ、大火災が発生して死者・行方不明者10万5千余人の大震災となった。
この「関東大震災」を契機に地震学のさらなる研究の必要性が認識され、大正14年には東京大に地震研究所が設置され、その後、全国に地震観測網が張り巡らされたり、地震学会が創設されたりして日本の地震研究や地震観測は進み、最近は平成7(1995)年の「阪神・淡路大震災」以降、急速に進歩してきた。
ところで、「地震の予知」では、発生する「時」、「場所」、「大きさ」の3要素を“高精度”に限定して予測することだといわれる。そのためには、様々な観測機器を設置して、常時監視体制を整えておく必要がある。現在、そうした体制が整い、“予知の可能性”があるのは、駿河湾付近からその沖合(地震予知のモデルフィールド)を震源とする(=場所)、M8級(=大きさ)の、所謂「東海地震」だけであるとされる。
地震学では、過去に起きた“痕跡”(地質構造や歴史的な史料など) を基にして解析、予測することも少なくない。限定された範囲の数十年程度の精密観測で、数百年~千年程前に起きた地震の状況を解析し、将来を予測することは難しいという。
とはいえ、今回の巨大地震を様々な学問的領域から多面的に分析・解明し、できるだけ精度の高い予知を確立し、防災に生かすことが求められる。
これまでの“安全神話”が一気に崩れた原発事故と放射能汚染。以下に、原子力発電の基本的な仕組み、事故発生直後から4月末までの状況などについて、ざっと整理してみた。
原子力発電の仕組みは、火力発電の「ボイラー」を「原子炉」に置き換えるとイメージしやすい。原子炉内(原子炉格納容器)にある「原子炉圧力容器」(以下、圧力容器)内の核燃料(「燃料棒」の中にある)が起こす“核分裂”(エネルギー<熱>や核分裂生成物<放射性物質など>を放出)の熱で湯を沸かして蒸気をつくり、その蒸気で「発電用蒸気タービン」を回して発電する(沸騰水型:福島第一原発)。タービンを回した蒸気は復水器で冷却されて水に戻され、再び「圧力容器」内で蒸気になり、タービンを回す。原発の運転中は、この循環を繰り返している。
福島第一原子力発電所では、3月11日の地震直後、原子炉の「圧力容器」内に核分裂を制御する「制御棒」を挿入し、原子炉を“緊急停止”させた。
しかし、地震で外部電源が喪失したうえ、高さ“14m以上”の津波に襲われて複数の非常用発電機も停止してしまった。
そのため、原子炉の停止後も「燃料棒」の中にある放射性物質から放出される熱を冷却するための水を「圧力容器」内に送り込むことができなくなった。つまり、原子炉を安定した「冷温停止」状態に保てなくなったのである。
因みに、稼動中の原子炉で事故が起きた場合、原子炉を「止める」、「冷やす」、そして放射性物質を「閉じ込める」ことが基本である。
加えて、福島第一原発では、使用済みの「燃料棒」を「原子炉建屋」上部にある「貯蔵プール」に入れて冷却していたが、ここでも給水ポンプが使えず、使用済み「燃料棒」を冷やせなくなった。
事故当初は、このように「核燃棒」を冷却することができなくなったり、十分に冷やせなかったりしたため、「燃料棒」の被覆管が破損して被覆材と水蒸気(水)とが反応して水素が発生。その水素が「原子炉建屋」の上部にたまって“水素爆発”を起こしたとみられている。この爆発で複数の「原子炉建屋」の屋根や外壁が破壊されるなどして、大量の放射性物質が広範囲に放出、拡散してしまった。
この一連の事故は後に(4月12日)、放出された放射性物質の量や範囲、複数の原子炉や「貯蔵プール」の事故状況などから、「国際原子力事象評価尺度」(INES)で最悪の「深刻な事故」とされる“レベル7”に相当するとされた。
事故発生後、様々な方法で各原子炉内の「圧力容器」と使用済み「燃料棒」の入っている「貯蔵プール」への水の注入が行われ、4月下旬現在、事故発生当初のような放射性物質の大気への大量放出は見られないという。
なお、4月末には、高温状態にある「圧力容器」を冷やして原子炉の安定化を図るため、「圧力容器」を覆う「原子炉格納容器」を水で満たす“水棺”の措置が試みられている。
依然として予断を許さない深刻な状態にある福島第一原発の事故収束に向けた「工程表」が、去る4月17日に発表された。
「工程表」では、「原子炉」と使用済み核燃料の「貯蔵プール」の安定化、放射能汚染対策を図ることなどを目標に、“原子炉を「冷温停止」の安定状態”とすることなどに“6~9か月”かかるとしている。
ただ、高濃度の放射能汚染水の処理や、破壊された原子炉建屋内の高い放射線量の下での作業など、安定化への道は険しい。
福島第一原発事故の最初の引き金となったのは、前述のように、地震による外部電源の喪失と津波に襲われた複数の非常用発電機の停止であったようだ。
福島第一原発では、“想定した”津波の高さを“5.4 m ~5.7m”としていたことが伝えられている。その2.5倍ほどの高さの津波に襲われたことになる。
そもそも津波を引き起こす海底地震の規模の“想定”を見誤ったことが津波の被害を招き、深刻な原発事故に至ったといえる。
非常用発電機の設置場所、“全電源喪失”後に続く一連のトラブルへの認識と対処などをみると、今回の巨大地震が我が国観測史上最大であったにせよ、地球上では巨大地震、大津波はこれまでにも起きており、原発の“安全性”を謳うのであれば、最大級の地震、津波を想定し、その対策に万全を期すべきであった。単に“想定外”として片付けられるものではなかろう。
* * *
我が国の発電電気量の電源別の推移をみると、昭和38(1963)年度に初めて火力発電が水力発電を上回り、“火主水従”になった。その後、火力発電は石炭から石油へ転換されて大容量、高効率化が進められたが、昭和48(1973)年度の第一次オイルショックを契機に、電力供給の増大とともに原子力や天然ガス等の電源の多様化が図られてきた。(図1参照)
現在、電力供給の多くは、海外からの化石燃料(石油・石炭・天然ガス)に依存している。しかし、化石燃料の安定供給の確保については、産地国の政治情勢に大きく影響されるなどの課題に加え、近年はエネルギー問題に伴う環境問題、特に地球温暖化問題への強い対応が世界的に求められている。
こうした状況において、原子力発電は、燃料となるウランの外国からの供給が石油などに比べ安定的である、発電時に二酸化炭素を排出しない、使用済みの核燃料は再処理することで再び使用できる、などの点から国内の発電電力量の“約3割”を担っている。(図2参照)
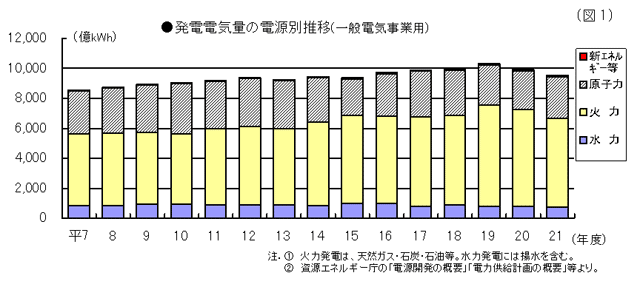
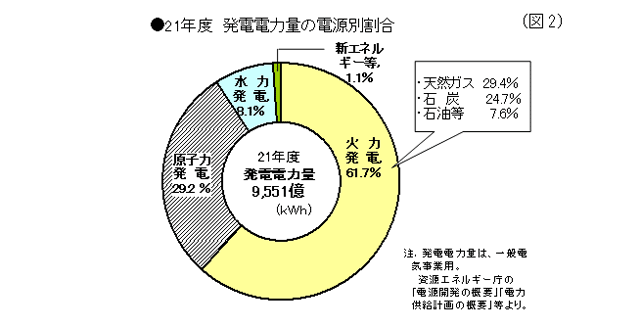
国は我が国の資源・エネルギー事情や地球温暖化対策の強化等を踏まえ、2030年に向けたエネルギー政策の方向性を示した『エネルギー基本計画』(22年6月閣議決定)を提示。
この基本計画では、原子力及び太陽光、風力、地熱、バイオマス(再生可能な生物由来の有機性の資源、エネルギー)などの、所謂「ゼロ・エミッション電源」の比率を現状の34%から2030年には約70%に高めることを目標に掲げ、特に原子力発電所については、「立地地域を始めとした国民の理解及び信頼を得つつ、安全の確保を大前提」として、現在の54基を2030年までに「少なくとも14基以上新増設する」ことなどを明記している。
しかし、菅総理は23年3月末、今回の福島第一原発事故を受けて「原子力、エネルギー政策は事故の検証を踏まえ、改めて議論する必要がある」と指摘し、政府の『エネルギー基本計画』の見直しを検討する意向を表明したと伝えられている。
菅総理は23年5月下旬に開催が予定されている主要国首脳会議(G8サミット)で、原子力対策を含めたエネルギー政策の新構想を国際社会に示す考えだという。
また、ロシアのメドベージェフ大統領は旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(事故評価尺度:レベル7)から25周年を迎えた4月下旬、原発推進の立場から、福島第一原発事故を受け、原発利用国の安全義務を国際的な法規定で裏打ちするなどの安全向上に向けた具体的な方策をG8サミットで提唱すると伝えられている。
原発事故を受け、原子力を含めたエネルギーの在り方についての問題意識が高まっている。原子力や化石燃料に替わる「自然エネルギー」へのシフト、「省エネ・節電」対策など、持続可能な様々なエネルギー論議が活発に議論されることを願いたい。
* * *
3・11の“震災・原発ショック”は、これまでの「自然」に対する見方・考え方、及び産業・経済から日常生活まで、成長と繁栄、暮らしの快適さや豊かさを追求してきた「社会」の在り方を見直す転機になるのではないか。
我々は「東日本大震災」によって、人知の未だ及ばない自然の力による「自然作用」(自然現象)の災害と、人の手による「人為的作用」の災害とを同時に受けてしまった。
地球の温暖化等に伴う気候変動(熱波、旱魃、局地的なゲリラ豪雨、洪水などの異常気象)、土地の開発・利用による地形変化などがもたらす災害(土砂崩れ、地すべり等)は、一見「自然作用」による“自然災害”ともみられるが、その災害を引き起こす原因の一端(当然、災害の内容等で人為的な関わりの度合いは異なる)は人や社会の活動による「人為的作用」によるものも少なくない。
一方、地震や津波、火山活動、台風(一部には異常気象に関連した「人為的作用」も)、磁気嵐(太陽活動に起因して通信障害等をもたらす)などは、「人為的作用」とは関係なく、「自然作用」によって起きる災害といえる。
翻って、福島第一原発の事故は、引き金としては前述したように、“津波”という「自然作用」がきっかけになったともいえようが、自然災害へのリスク評価を見誤ったことや事故後の深刻な放射能汚染を招いた一連のトラブルは「人為的作用」による災害といえよう。
地震や津波のような「自然作用」による災害にしろ、異常気象などにみる「自然+人為的作用」による災害にしろ、あるいは原発事故にみる「人為的作用」の災害にしろ、それぞれの災害に対する我々が抱える“脆弱性”を精査して、「災害リスク」を高精度に評価し、その安全性(安全基準:危険度ともいえる)を明確に示して防災や事故防止に生かしていくべきである。そのためには、自然科学、社会科学におけるさらなる教育・研究の深化や科学技術の一層の進歩が求められる。その過程で、既成の「自然観・社会観」の見直し論議も起きてくるのではないか。
ところで、巨大地震の起きるメカニズムで前述したプレートの動きと、その基になる「マントル対流」を引き起こしている“熱対流”のエネルギー(熱源)は、マントル内にあるウラン、トリウム、カリウムなどの「放射性同位元素」が崩壊する際に発する“崩壊熱”などによるとされている。
つまり、地球は内部(マントル)に巨大な“原子炉”をもち、そこで放出される熱エネルギーによって、地震や津波、火山活動などの地球活動(地殻変動)が起きている。
人は「自然」である「地球」を文明の発達とともにどれだけ侵してきたことか。
例えば、18世紀の蒸気機関の発明以降、地球が数億年にわたってつくりあげてきた「化石燃料」をわずか数百年の間で枯渇が懸念されるほど大量消費(化学産業等の原材料の消費も含め)、しかも温暖化、環境破壊など“負の副産物”を地球に蓄積させている。
さらに、地球の産物である「ウラン鉱石」等を使った原子力発電も起し、“電力基盤社会”を築いてきた。
しかし、ここでも、放射能汚染という“負の副産物”を撒き散らしてしまった。
地震や津波といった地球の営みによる自然現象も、人の手で作られた原発(原子炉)が放出する熱や放射性物質も、元を質せば地球内部の放射能を持つ物質のエネルギーが形を変えて我々の前に現れているに他ならない。
科学技術の進歩によって手に入れた「原子力」さえも、その振舞いを制御し、管理することが非常に難しいことが露になり、ましてや自然のメカニズムによって振舞われる「地震」や「津波」に至っては、その解明に現代の科学では未だ不十分であることがはっきりと突きつけられた。
特に、原発事故では、科学技術の飛躍的な進歩の一方で、エネルギー資源の乏しい我が国の繁栄が人為的な科学技術に拠って立ってきた“脆弱さ”をまざまざと見せつけられている。
人の手を加えない、“自ずから然あること”(おのずからそうであること)の「自然」と、人はどう向き合い、どう関わっていくべきなのか・・・・・。
今回の災厄を、未来を見据えた持続可能な「自然」と「社会」との在り方を再考する転機としたい。
