財務省は27年10月下旬、国立大の基盤的経費である運営費交付金の「今後15年間毎年1%削減」案などを示した。政府は12月下旬、28年度予算(案)で運営費交付金を27年度予算と同額の1兆945億円にすることを決めたが、国立大などの間に波紋が広がっている。
国立大の運営費交付金は法人化以降、既に1,470億円(11.8%)削減されており、更なる削減は国立大の財務基盤を脆弱化させ、授業料の引上げなどにもつながりかねない。
ここでは、財務省の財政制度等審議会(財政審)が示した国立大の運営費交付金見直しの建議と、それに対する文科省の考え方、及び財務省における国立大財務運営の考え方や運営費交付金削減案がもたらす授業料への影響などを探った。
* * *
財務省の財政制度等審議会(以下、財政審)は27年6月初め、国の財政健全化計画の基本的な考え方を『財政健全化計画等に関する建議』(以下、『財政審建議』)として取りまとめた。この『財政審建議』は国の教育に係る公財政に関し、「義務教育の教職員定数」と「国立大学法人運営費交付金」(以下、運営費交付金)の見直しなどを提言している。
運営費交付金に関しては次のような点を指摘し、国立大の財務基盤見直しを求めている。
『財政審建議』はまず、大学進学者の大部分を占める18歳人口は平成4年度(約205万人)をピークに減少に転じ、今後も減少傾向が続くとの予想を記している。
他方、国立大の在籍者数(24年度以降、61万人台)は近年横ばいで推移しており、教員数は18年度の6万712人から26年度の6万4,252人へと年々増加していると指摘。
一方、国立大の財務基盤は、16年度の法人化以降、27年度までに運営費交付金が約1,470億円(予算ベース)減額されて硬直化が進んでいるとされるが、国立大全体の収入額・事業規模は年々増加しており、25年度の国費負担額(運営費交付金と補助金等収入の合計)は16年度に比べて約1,500億円(決算ベース)も増加していると指摘。国からの財源措置は、厳しい財政事情の中で十分に手厚く行われているとみるべきであるとしている。
大学全入時代といわれ、高等教育の水準低下が懸念される中、国立大の研究力、教育水準の維持・向上のために、大学間・大学内の大胆な再編・統合/重点化による入学定員の見直し/教員規模の適正化/大学教育内容の質的転換等の取組とともに、学内資源の再配分や収入源の多様化による一層の効率的・効果的な大学運営が求められるとしている。
『財政審建議』は、国立大全体の収入構成について、運営費交付金と補助金等収入による国費負担が総収入の半分程度を占めていると指摘。法人化以降、研究収入や寄附金については一定の増収がみられるものの、世界トップレベルの大学における収入源の多様化と比べれば、国立大はなし得る財務基盤強化を十分に進めているとは言い難いと断じている。
今後、教育研究環境の改善を進めるためには、国費に依存しない財務基盤の強化が必要であるとしている。
具体的には、研究収入の積極的な獲得の推進、機能強化のための運営費交付金の3つの「重点支援」枠(後述)による客観的評価に基づいたメリハリある配分などを求めている。
◆ 「授業料」引上げの検討
『財政審建議』は、国立大の基盤を支える重要な収入の一つである授業料の引上げについても積極的に検討すべきであるとしている。
大学が学生に提供する教育によって、その卒業生は高度な専門知識を活用し、平均的により高い賃金を得ることが可能であるという。学生が在学中に要する費用と比べて、生涯を通して大学教育から受ける恩恵は大きく、特に、国立大の場合は私立大に比べて授業料の水準が6割程度になっていると指摘している。
◆ メリハリの利いた学生支援
当『建議』は、教育の機会均等は国の基であり、大学教育についても「教育格差」拡大を否定している。授業料を引き上げて収入の増加を図りつつも、その収入を財源として、意欲と能力がありながらも経済的に困難な学生層に対する経済的配慮が必要であるという。
更に、特に卓越した学生に対する戦略的な投資、学生の多様なニーズ・価値観に応えた教育・研究環境の一層の整備を求め、所得と能力に応じて教育費負担の調整を行うメリハリの利いた学生支援が重要であるとしている。
文科省は上述のような『財政審建議』に対して、『財政制度等審議会の「財政健全化計画等に関する建議」に対する文部科学省としての考え方』(以下、『財政審建議に対する文科省の考え方』)を直ちに取りまとめ、公表した(27年6月初旬)。
文科省は、『財政審建議』における国立大の「収入額・事業規模の拡大」と「授業料の引上げ検討」の2つの指摘事項について、それぞれ次のように反論している。(以下の『財政審建議に対する文科省の考え方』で、太字と下線は当方で付記)
◆ 財政審の指摘 (1)
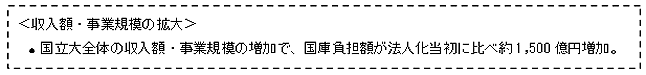
① 国立大は法人化以降、国費負担額は増加しているものの、その内訳は、国立大が獲得する競争的研究費の増加であり、国立大が本来行う教育研究を支える基盤的経費である運営費交付金は減少している。
② 運営費交付金の減少により、次のような問題が生じ、国立大が行う基盤的・持続的な教育研究の機能の遂行に影響をきたしている。
● 国立大が行う教育研究活動を支える常勤教員の人件費が10年間で大幅に減少。特に若手研究者の常勤雇用が減少し、そのキャリアが不安定化している。
そのため、優秀な人材の確保に支障が生じる恐れがある。
● 教育の質的向上に対応するための教育経費や、基盤的な研究に当てるための経費、学長が戦略的に使用する改革経費などを捻出することが困難である。
③ 法人化以降、国立大を取り巻く環境の大きな変化で、国立大はグローバル化、イノベーションの創出、地方創生などの課題に対する人材育成や新たな教育研究ニーズへの対応が求められている。
④ このようなニーズに応えるため、国立大が社会に対してより積極的に期待される役割を果たせるよう国立大学改革を進める中、運営費交付金において、改革に取り組む大学に対しメリハリある重点支援によるインセンティブを付与することが必要である。
⑤ 国立大が獲得する競争的研究費の増加は、特定の研究目的のために配分されるものであり、運営費交付金に代わって国立大の基盤的な機能強化を図るための恒常的な財源となるものではない。
国立大が教育研究機能を発揮し、これまで以上に国の成長を支え、科学技術イノベーションによる社会を牽引していくためには、むしろ、競争的研究費の更なる充実が必要である。
⑥ 以上のようなことから、国費負担額全体が増加しているから十分であるという指摘は、適切ではないと考える。
⑦ なお、文科省としては、国費による財務基盤の充実を図るだけではなく、自己収入の拡大など財源の多様化の取組も含めて、財政基盤を強化することが必要と考えている。
国立大の自己改革・新陳代謝を進め、その機能の強化に取り組むことにより、社会から求められる役割と責任を確実に果たしていくことのできる国立大学改革を引き続き推進していく。
◆ 財政審の指摘 (2)
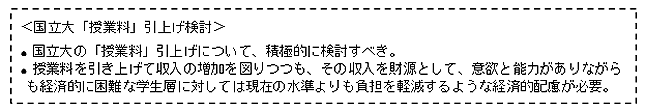
① 意欲と能力のある学生等が経済的理由で進学等を断念することのないよう、安心して学ぶことのできる環境を整備することは極めて重要と考えている。
② そのため、文科省としては、基本的には学生等に対してできるだけ教育費負担をかけないようにしていくことが重要であり、まず、国立大の授業料値上げありきという考え方は適当でないと考える。
③ しかし、厳しい財政状況において、いまだ経済的に困難な学生等への支援は十分とはいえず、その更なる拡充が求められる。そのため、外部資金の導入促進など財源の多様化のための取組も含め、必要な財源確保に最大限努力していくことが必要である。
④ それでもなお、既存の財源では対応が困難な場合には、例えば一部の裕福な高所得世帯の学生に対する授業料値上げによる財源を活用し、経済的に困難な学生等の支援に充てることなども一つの考え方としてはあり得る。
ただ、そのような一部の家計の教育費負担増による支援策などが社会や国民の理解を得られるかも含め、慎重な検討が必要である。
文科省は27年6月中旬、国立大の第3期中期目標期間(28年度~33年度)を控え、知識基盤社会の中核的拠点として全国に配置されている国立大が「社会変革のエンジン」として「知の創出機能」を最大化していくことを基本とする「国立大学経営力戦略」を策定した。
当「戦略」では、学長のリーダーシップによる経営力の強化を図り、文科省でも各大学の強み・特色をより発揮できる機能強化の取組を支援するため、運営費交付金に3つの「重点支援」枠を設置してメリハリある予算配分を行うなどの改革を進めている(後述)。
このほか、国立大の自己収入拡大を促進するための規制緩和/外部資金獲得へのインセンティブ拡大/寄附金収入の拡大/国際的な研究・人材育成や知の協創拠点となる国立大の形成として「指定国立大学(仮称)」(「特定研究大学(仮称)」の名称変更:27年12月)の創設などを提起している。
前述したような運営費交付金を巡る『財政審建議』と『財政審建議に対する文科省の考え方』、及び「国立大学経営力戦略」などが示されている状況の下で、財務省は27年10月下旬、財政審の財政制度分科会において、運営費交付金に関する国立大学法人運営の長期的な試案を示した。その主な内容は、次のとおりである。(枠内の太字は原文による)
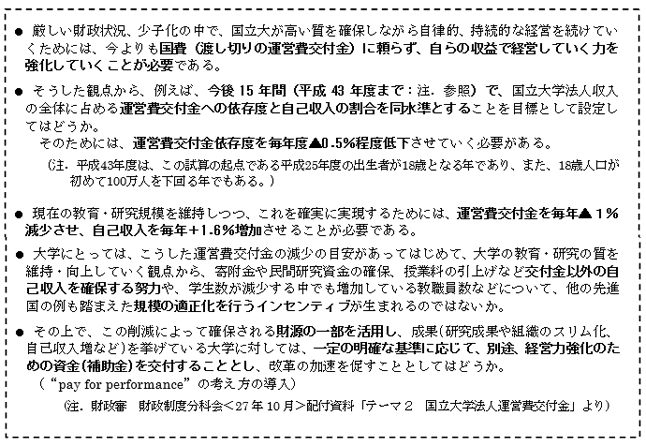
財務省が示した上掲のような「運営費交付金」削減等のポイントは、次のとおりである。
◆ 今後15年間(28年度~43年度)に、「運営費交付金の依存度」(運営費交付金÷国立大学法人の全収入)と「自己収入の割合」(自己収入÷国立大学法人の全収入)を“同水準”にする。
◆ 運営費交付金を毎年“▲1%”減少させ、自己収入を毎年“+1.6%”増加させる。
◆ 25年度(決算ベース)の運営費交付金=1兆1,774億円/補助金=3,548億円/自己収入=7,370億円を基に、財務省案に従って43年度までの各年度の運営費交付金や自己収入などを試算した(補助金は各年度とも3,548億円で設定。図1参照)。
● 運営費交付金:
・25年度=1兆1,774億円 ⇒ ・32年度=1兆974億円 ⇒ ・43年度=9,826億円(対25年度:1,948億円減、16.5%減)
● 自己収入:
・25年度=7,370億円 ⇒ ・32年度=8,236億円 ⇒ ・43年度=9,807億円(対25年度:2,437億円増、33.1%増)
運営費交付金と自己収入について、財務省案に従って試算し、25年度と43年度のそれぞれの額を比べると、運営費交付金は1,948億円(16.5%)減少し、自己収入は2,437億円(33.1%)増加する。これにより、43年度の「運営費交付金の依存度」(42.4%)と「自己収入の割合」(42.3%)はほぼ同じ水準になる。
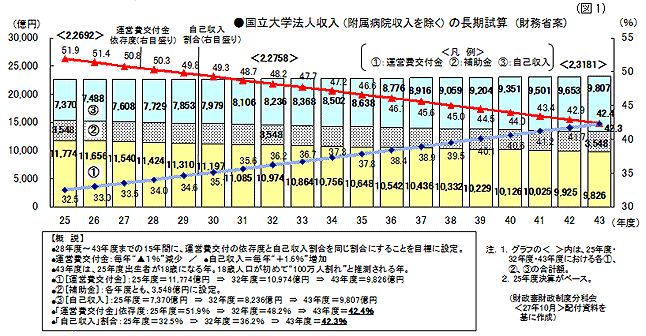
国立大の運営費交付金を今後15年間毎年1%減少させ、自己収入を毎年1.6%増加させたり、授業料の引上げ等で自己収入の確保を図ったりするなどの財務省提案に対して、中教審や国大協、各国立大などは直ちに反対声明を出した。
中教審は『高等教育予算の充実・確保に係る緊急提言』(27年10月下旬)、国大協は『財政制度等審議会における財務省提案に関する声明』(同)において、国立大が現在全力を挙げて取り組んでいる改革の実現を危うくするとともに、経済状況による教育格差の拡大につながるなどと強い危惧を示し、高等教育への投資を削減することは将来に対し禍根を残すものであるとしている。
そして、国立大が教育や研究、社会貢献といった諸機能を強化し、目指す改革を確実に実行していくためには、運営費交付金等を充実・確保すべきであるとしている。
* * *
国立大の事業収入は、運営費交付金や施設整備費補助金等の「国からの収入」/附属病院収入、受託研究など競争的資金、授業料など学生納付金等による「自己収入」/借入金等の「その他の収入」などである。
国立大学法人等(90法人:25年度)の経常収益をみると、運営費交付金収益と附属病院収益がそれぞれ30%台前半で両者合わせると全体の3分の2を占める。このほか、学生納付金収益と競争的資金がそれぞれ10%強となっている。
ただ、国立大学法人ごとにみると、運営費交付金への依存度や競争的資金等の外部資金の獲得状況など、財務構造の違いが顕著になっている。
一般的に運営費交付金の経常収益に占める割合が高いのは、教員養成系や文科系中心の大学、逆に低いのは医科系の大学などで、全体としては収入の3~4割を占めている。
また、受託研究収益や寄附金収益、研究関連収益などの外部資金収益の割合が高いのは、大規模な総合大学や理工系中心の大学などである。(図2・図3参照)
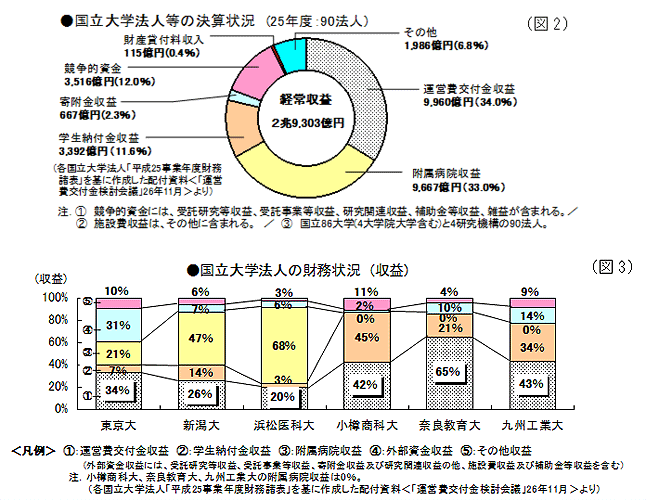
◆ 運営費交付金:11年間で1,470億円(11.8%)削減
国立大等(国立全86大学・4研究機構の90法人)が法人化された16年度と27年度の運営費交付金(予算ベース)を比べると、26年度を除き毎年1%程度交付金が減額されてきたため、法人化以降11年間(16年度~27年度)で1,470億円、11.8%削減されたことになる。
◆ デュアルサポートシステムの限界
国立大の教育研究活動は一般に、基盤的経費である「運営費交付金」と、各種の競争的資金である「自己収入」とを組み合せた“デュアルサポートシステム”によって支えられてきた。
しかし、上記のように運営費交付金が毎年1%程度削減される厳しい財政事情の下では、「自己収入」への依存度が高まっている。
因みに、最近の「競争的資金」等の獲得状況(受入額ベース)をみると、20年度の4,854億円から25年度の6,776億円と、5年間で1,922億円、36.6%増加している。(図4参照)
ただ、目的や使途が限られている競争的資金の獲得で得られた教育研究のさまざまな成果を、基盤的経費である運営費交付金によって各国立大の中で組織化し、持続・発展させていくことが難しくなっている。つまり、緊縮財政の下、デュアルサポートシステムは限界に達し、基盤的経費と競争的資金の適切なバランスを維持することは難しいようだ。
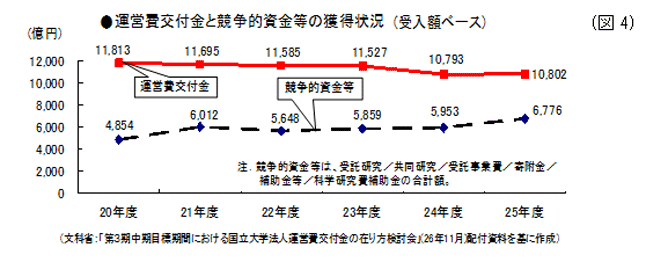
文科省は第3期中期目標期間における各国立大の機能強化の方向性に応じた取組をきめ細かく支援するため、予算上、次のような“3つの重点支援の枠組み”を新設した。
各大学は1つの重点支援枠を選択して取組構想を提示。その取り組みの成果は、運営費交付金の配分に反映される。つまり、運営費交付金の“3類型”化である。
主として、人材育成や地域課題を解決する取組などを通じて地域に貢献する取組とともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界ないし全国的な教育研究を推進する取組等を第3期の機能強化の中核とする国立大を重点的に支援する。
● 対象校(28年度。以下、同):55大学(全86国立大の64.0%)。北海道教育大/旭川医科大/宮城教育大/埼玉大/滋賀医科大/山口大/高知大/熊本大/鹿児島大など。
主として、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で地域というより世界ないし全国的な教育研究を推進する取組等を第3期の機能強化の中核とする国立大を重点的に支援する。この枠組みについては、当該分野に重点を置いた人材育成や研究力の強化の取組を推進できるような支援を行う。
● 対象校:専門分野における強み・特色が強い15大学(同17.4%)。筑波技術大/東京医科歯科大/東京芸術大/電気通信大/鹿屋体育大/総合研究大学院大など。
主として、卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に世界で卓越した教育研究、社会実装を推進する取組を第3期の機能強化の中核とする国立大を重点的に支援する。
● 対象校:全学的に卓越した教育研究等の取組を中核とする16大学(同18.6%)。北海道大/東北大/筑波大/東京大/東京工業大/一橋大/名古屋大/京都大/大阪大/広島大/九州大など。
「運営費交付金」配分の3類型化については、国立大の機能強化のほか、競争的資金の獲得促進や国立大学間の財政的な格差是正などにも資するとされる。
例えば、「世界水準の教育研究型」(重点支援③)の大学は競争的資金の一層の獲得を目指し、デュアルサポートシステムの競争的資金の割合を高める。その結果、競争的資金を獲得した研究機関(大学)や研究者が当該研究のためにのみ使える「直接経費」に加えて、研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能向上に活用できる「間接経費」(直接経費の最高30%を措置。措置されていないものもある)も原則的には交付されることになる。
こうしたことから、緊縮財政下における国立大の財政的格差を是正するためには、競争的資金に「間接経費」を確実に措置する代わり、より多くの競争的資金を獲得する大学の基盤的経費(運営費交付金)を縮減してまでも、その分を「地域貢献型」(重点支援①)の大学など基盤的経費の削減で困窮しているところに回すなどの施策もあるようだ。
* * *
財務省が提案した「運営費交付金」削減と「自己収入」増加は、国立大の自己収入の20%程度を占める授業料や入学料などの学費引上げにつながらないか、その影響が懸念される。
そこでまず、国立大の学費の現状、国立大と私立大の授業料の推移などをみてみる。
◆ 10年間据え置きの「授業料」標準額:53万5,800円
国立大の授業料、入学料、及び入学に係る検定料は、16年度の法人化以降、国が定める「標準額」(下記の枠内参照)の120%(16年度~18年度は110%)の範囲内において、各大学が設定する(「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」)。
法人化された16年度の授業料(標準額。以下、同)は、法人化前の15年度と同額の52万800円であったが、17年度に53万5,800円に引き上げられ、(対前年度1万5,000円、2.9%増)、以後、27年度まで改正されていない。
因みに、国立大の27年度の初年度納付金(昼間部)は、国の定めた「標準額」である授業料53万5,800円、入学料28万2,000円の合計81万7,800円が基本で、大学・学部(文系・理系)を問わず一律(標準額と同額)である。
ただし、実習費や災害傷害保険料、学友会費などによって、所謂「学費」は大学や学部(学科)で異なる場合がある。
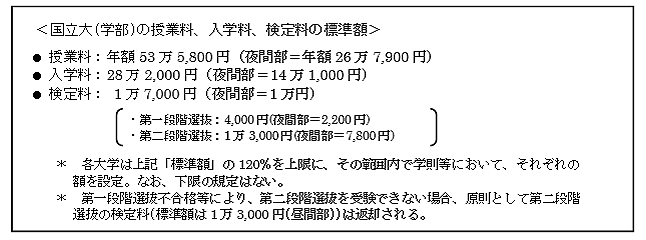
国立大と私立大の授業料について、これまでの金額、及び国立大と私立大との格差の推移をたどってみる。
◆ 国立大「授業料」:昭和50年度~平成17年度の30年間で約15倍に!
国立大の授業料(年額。以下、同)は、新制大学発足当初の昭和24(1949)年度は3,600円、27年度6,000円、31年度9,000円、38年度~46年度1万2,000円、47年度~50(1975)年度3万6,000円であった。
しかし、翌年の昭和51年度には一気に2.7倍に引き上げられて9万6,000円になった。
その2年後の53年度には14万4,000円に値上げされ、その後も1年おき(昭和60・61年度は据え置き)に2割前後ずつ引き上げられ、昭和62(1987)年度には30万円に達した。
2年後の平成元(1989)年度には33万9,600円となり、以後、授業料は3%~10%程度の値上げ幅で1年おきに引き上げられた。5(1993)年度は41万1,600円であったが、15・16年度には52万800円となり、前述のように法人化の翌年である17年度には「標準額」として53万5,800円に設定され、現在に至っている。
昭和50年代以降の国立大の授業料は、昭和50年度から平成17年度までの30年間で14.9倍に引き上げられたことになる。(図5参照)
◆ 私立大「授業料」:昭和50年度~平成26年度の39年間で約5倍に!
私立大の授業料(年額、全平均。以下、同)は昭和50(1975)年度の18万2,677円から12年後の昭和62(1987)年度には51万7,395円と50万円台に突入。平成元(1989)年度は57万584円、5年度は68万8,046円、10年度は77万24円となり、14(2002)年度には80万4,367円で80万円台に達した。20年度は84万8,178円、26年度は86万4,384円となった。
私立大の授業料は、昭和50年度から平成26年度までの39年間で4.7倍に引き上げられた。(図5参照)
◆ 国立大・私立大「授業料」格差:昭和50年度“5.1倍”⇒ 平成7年度以降ほぼ“1.6倍”!
昭和50(1975)年度、国立大授業料は3万6,000円、私立大授業料(平均)は18万2,677円で、私立大の授業料は国立大の5.1倍(私立大授業料÷国立大授業料。以下、同)であった。翌51年度には前述のような国立大の大幅な値上げによって、国立大・私立大の授業料格差は2.3倍に縮まった。
その後は昭和56年度まで、国立大・私立大の授業料格差は2倍台を推移した。
さらに、昭和57年度の1.9倍、昭和58年度の2.0倍を経て、昭和59年度以降は1倍台後半(昭和61年度は2.0倍)を推移。特に平成初期は1.7倍前後であったが、7(1995)年度以降は8年度の1.7倍を除き、26年度まで1.6倍を維持している。
つまり、昭和50年度~平成7年度までの20年間で、国立大・私立大の授業料格差(国立大授業料 < 私立大授業料)は5.1倍 ⇒ 1.6倍に縮小し、現在に至っている。(図5参照)
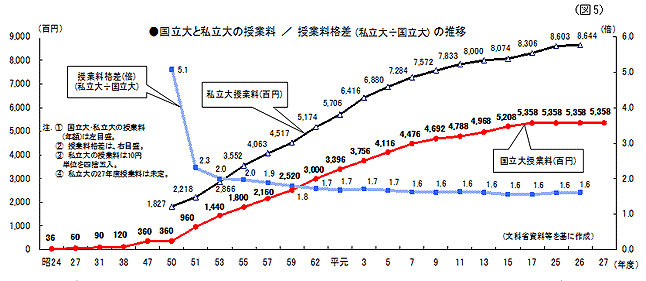
財務省が27年10月下旬に提案した平成43(2031)年度までの「運営費交付金」削減と「自己収入」増加について、全て「授業料」で対応した場合、43年度の授業料はどのくらいになるのか。
文科省は27年12月初めの衆議院文部科学委員会(閉会中審査)での質問に対し、約93万円になるという“試算”を示したことが報じられた。
各国立大の財政状況によって「授業料」引上げの試算額は異なるが、国大協や個別の大学、関係組織などでも授業料引上げの影響などで試算を公表し、危機感を訴えた。
具体的な試算例として、次のような引上げ額が示された。
◆ 平成43年度まで「自己収入」を毎年1.6%増加し、約2,400億円の増収分を全て「授業料」で対応する場合の43年度の「授業料」の試算:
● 学生数を約61万1,000人に設定(27年度『学校基本調査速報』より)。
● 増額幅や増加率は、「授業料」標準額=53万5,800円をベース。
⇒ 43年度「授業料」=約93万4,800円。
⇒ 27年度「授業料」に比べ、39万9,000円(74.5%)引上げ。
国立大の授業料は、国立大が創設された当初から昭和40(1965)年代までは所謂「設置者負担」(当時の国立大は国の行政組織の一つであり、国の政策的な目的、人材育成等の観点による)主義的な色彩が強く、比較的安価であった。
しかし、高度経済成長期を迎え、中教審答申『今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について』(『四六答申』:昭和46<1971>年6月)の「受益者負担」主義の考え方などから、昭和50(1975)年度に入ると国立大の授業料も私立大と同じように引き上げられていった。(図5参照)
他方、平成16年度からの法人化を迎えるに当たり、当時の文科省は、国立大の役割は法人化によって変わるものでなく、その役割に鑑みて、今後とも必要な財源措置を行い、授業料は国として標準額を示して適切なものになるよう努めていくとしていた。
国立大の授業料(標準額)は、大学・学部等の規模や文系・理系といった教育研究分野等に関係なく、一律かつ抑制的に設定され、高等教育の機会均等に資するものであるといえる。
国立大の授業料は法人化後、この10年ほど変わらず、私立大に比べて“一律低額”策がとられている。
一方、大学進学率50%を超える高等教育のユニバーサル段階に入り、国立大と私立大との役割や機能が明確に区別できなくなっていることや、両者の学生の経済力に必ずしも明確な違いがあるわけでなく、国立大の学生も中高所得者層で構成されている場合もあるなどとして、国立大の授業料(標準額)の設定水準を見直すべきとする議論も聞かれる。
国立大の授業料は私立大に比べ、“一律低額”策が講じられているとはいえ、高止まり状態ともいえる。家計の経済状況が厳しい折、今後の成り行きが注目されている。
こうした中、政府は27年12月下旬の28年度当初予算編成で、28年度の運営費交付金を27年度予算と同額の1兆945億円(概算要求は対前年度420億円増の1兆1,365億円)とすることを閣議決定。また、今後は運営費交付金の一部を大学ごとの研究成果や改革努力に応じた補助金として配分するなどの方針も決まったようだ。
ともあれ、今後、国立大の授業料などを見直す際には、奨学金制度の改善策などと併せ、学生への経済的な配慮を幅広く行っていくことが必要である。因みに、平成17年5月の参議院文教科学委員会の「国立大学法人法の一部を改正する法律案」(可決)の附帯決議に、次のような事項が盛り込まれている。
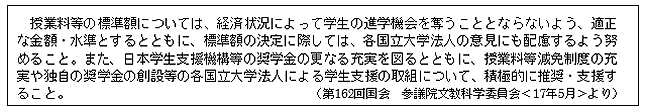
本稿はここまで、国立大財政に対する財政審や財務省の政策方針、及び国立大財政の状況などをみてきた。我が国全体が厳しい財政状況にあるにせよ、財務省の交付金政策案は国立大にとって厳しい内容で、特に地方の中小規模大学への影響はより深刻のようだ。
各国立大は「ミッションの再定義」や「国立大学改革プラン」、「国立大学経営力戦略」などによって、各大学の強み・特色を最大限に生かし、知識基盤社会における知の拠点として更なる進展を目指し、28年度からの第3期中期目標期間に向けて機能強化を図っている。
また、政府の掲げる地方創生の基本方針でも地方大学の活性化が期待され、運営費交付金に係る3つの「重点支援」枠の1つに地元貢献型の国立大への支援策が盛り込まれている。
こうした国立大の大きな改革・転換期において、基盤的経費である運営費交付金を長期にわたって削減することは、国立大の財務基盤を一層逼迫させ、国立大が担うべき基本的な機能までも低下させてしまうことが懸念される。
国立大が自己収入の確保に努力することは必要であるが、全ての国立大が運営費交付金の削減分を競争的資金や寄附金などで補うには限界があり、難しいとみられる。今後、自己収入への依存度が高まれば、授業料等の引上げ検討もあり得よう。
ただ、学費引上げは学生に直接影響して進学率の低下や中退率の上昇を招き、世帯所得の格差が今以上に教育格差となって表れ、社会にとっても大きな損失である。我が国の教育機関への公財政支出の対国内総生産(GDP)比は国際的にみて低い。教育財源を当事者のみに求めるのでなく、「教育は未来への投資」という認識で公財政支出の拡充が求められる。
