18歳人口の約半数が大学(学部)に進学する高等教育の発達段階にあって、大学の「学費」を含めて教育の私費負担は、厳しい経済・雇用情勢の下で家計に重くのしかかっている。
幼稚園~大学卒業までの教育費は、高校まで公立、大学が国公立で770万円、すべて私立で2,230万円かかる(22年度調査)。我が国は教育機関への公財政支出の割合が低く、特に高等教育予算の国内総生産(GDP)に占める支出割合は、OECD(経済協力開発機構)平均の半分程度で、家計負担の重さが課題となっている。
学生の経済的支援を検討している文科省の検討会は、給付型奨学金の制度設計も視野に、貸与型の無利子奨学金の拡充等を提言している。
* * *
国民の「教育」を受ける権利や義務教育の無償については、憲法及び教育基本法で次のように明確に“保障”されている。
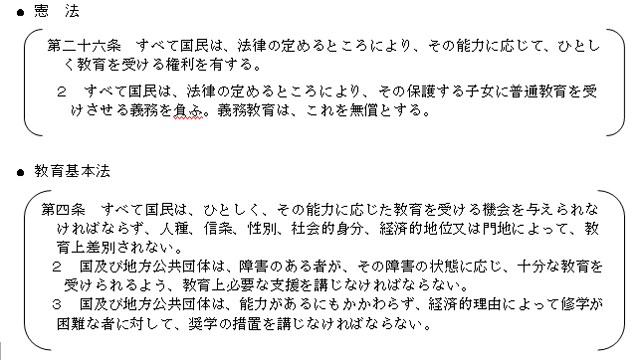
国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として条約化したもので、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものであるという。
同規約(社会権規約と自由権規約)は、1966(昭和41)年の第21回国連総会で採択され、1976年に発効。日本は昭和54(1979)年に批准したが、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)の第13条第2項の(b):中等教育の漸進的無償化の導入/(c):高等教育の漸進的無償化の導入の規定の適用に当たり、これらの規定にいう「(中略)・・特に、無償教育の漸進的な導入により・・(中略)」に拘束されない権利を留保していた。
◆ 大学等の“無償教育の漸進的導入”を追求
平成24年9月、日本は上述の留保を撤回する旨を国連に通告した。これにより、日本は上記の規定の適用に当たり、「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されることになった。我が国は大学等の“高等教育の無償化”に向け、漸進的にその導入を目指すことが求められている。中等教育については、高校授業料無償制度が22年度から実施されている。
高校への進学率98%超の現在、高校教育はいまや準義務教育化している。そうした状況において、高校生等が家庭の経済状況にかかわらず、安心して就学できるよう、公立高校の授業料無償制・私立高校等の就学支援金制度が創設され、実施されている(22年4月~)。
● 公立高校の授業料“不徴収”
公立高校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部含む)においては、25年度現在、授業料を原則“不徴収”としている。国は、地方公共団体に対して授業料収入相当額を国費により負担する。
● 私立高校等の就学支援金
私立高校等の生徒については、高等学校等就学支援金として授業料について一定額(25年度の年間標準額:11万8,800円)を助成する(学校設置者が代理受領)。
◆ 高校授業料無償制度の見直し ~「所得制限」導入等 ~
● 高校等授業料無償制度に関する法律
「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金制度の支給に関する法律」(22年4月1日から施行)の「附則」第2項及び「附帯決議」には、次のような制度見直しに関する文言が盛り込まれている。
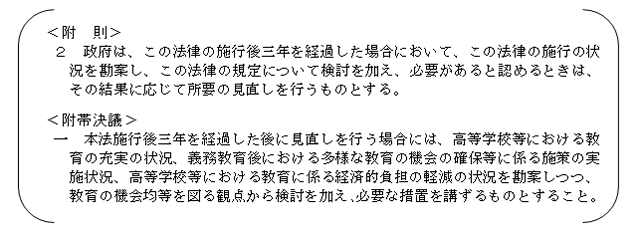
● 自民・公明両党、年収“910万円未満”の「所得制限」で合意
施行から3年経った高校授業料無償制度の見直しを検討、協議していた自民・公明両党は25年8月下旬、給付対象の世帯年収額を“910万円未満”に限定することなどで合意した。また、両党は所得制限で捻出した財源を低所得者向けの給付型奨学金制度の創設に充てたり、私立高校への就学支援の拡充に充てたりするとしている。
政府・与党は制度改正の関連法案を今秋の臨時国会に提出し、26年度導入を目指すもよう。ただ、新制度成立の場合でも、実施態勢の整備や関係者等への周知などに一定の時間を要することから、来年度実施は難しいとする自治体からの申入書も出されている。
25年度の高等教育機関への入学状況(文科省『25年度学校基本調査速報』。既卒者含む)をみると、大学(学部)進学率49.9%、短大進学率5.3%のほか、高等専門学校(4年次)0.9%、専修学校専門課程(専門学校)21.9%を合わせると、高等教育機関への進学率は77.9%に及ぶ。つまり、18歳人口の8割近くが高等教育機関に進学し、大学・短大への進学者は5割を超えている。
文科省は、これら大学等に進む意欲と能力のある学生等が安心して修学できる環境を整えるために、独立行政法人「日本学生支援機構」(JASSO:以下、「支援機構」)の大学等奨学金事業、国立大・私立大の授業料減免等の支援(公立大の授業料減免は地方財政措置で支援)、大学院のTA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)への給与型の経済的支援等を実施している。
◆「支援機構」の奨学金事業
大学等の奨学金制度は各自治体や各大学等のほか、民間の育英団体等で実施されているが、公的奨学金事業を担っている「支援機構」(文科省所管)の事業規模が最大である。
「支援機構」の奨学金制度は貸与型で、「第一種」(無利息)と「第二種」(利息付:年利3%を上限。在学中は無利息)があり、いずれも学力基準や家計基準など一定の条件がある。
また、家計の厳しい世帯(給与所得が年収300万円以下相当)の学生等が返還の不安から奨学金の貸与を躊躇することのないよう、無利子奨学金(第一種)の貸与を受けた本人が卒業後に一定の収入(年収300万円)を得るまでの間、返還期限を猶予する「所得連動返還型無利子奨学金制度」が24年度から導入されている。
25年度の「支援機構」における大学等の奨学金事業は、事業費総額1兆1,982億円(前年度より719億円増)、貸与人員144万3,000人(同8万8,000人増)で、いずれも増加傾向にある。貸与人員の内訳は、無利子貸与人員が42万6,000人、有利子貸与人員が101万7,000人となっている。(図1参照)
● 高校等の奨学金事業
高校等への奨学金事業は、以前は「支援機構」で実施されていたが、17年度入学者から各都道府県に移管されている。高等学校等奨学金事業交付金(25年度予算135億円)は、「支援機構」を通して各都道府県に交付される。
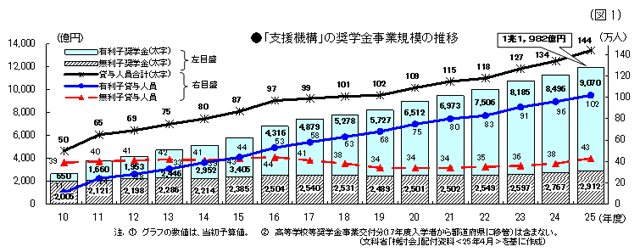
◆ 国立大・私立大の授業料減免の取扱い
● 国立大の授業料減免等
国立大では、経済的理由により授業料等の納付が困難な者に対し、授業料等減免など経済的負担の軽減を図るために、次のような規定(文科省令)が設けられている。
ただし、具体的な仕組みについては、各大学が設定するとしている。
◎ 国立大等の授業料その他の費用に関する省令
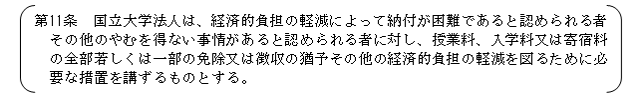
25年度の国立大授業料減免等の予算は291億円(復興特別会計11億円含む)で、前年度より8.6%増となっている。減免対象人数は、前年度より約4,000人増の約5万4,000人(学部・修士:約4万6,000人、博士:約6,000人、被災学生分:約2,000人)である。
また、1人当たりの平均減免額(学部:昼)は、約32万3,000円(23年度の授業料減免の実績額を減免者数で除した金額)である。
● 私立大等の授業料減免
各私立大が授業料減免を行った場合、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)が、学校法人に対し「私立大学等経常費補助金」の「特別補助」によって1/2(東日本大震災による被災学生に対しては2/3)を補助する。補助要件は、給与所得者の場合、841万円以下である。
25年度の私立大授業料減免等の予算は120億円(復興特別会計50億円含む)で、前年度より1.7%増となっている。減免対象人数は、前年度より約5,000人増の約5万9,000人である(ワークスタディ、被災学生分約1万6,000人等含む)。
1人当たりの平均減免額は、約32万円である。この金額は、24年度の大学の減免総額(自己財源含む)を補助対象人数で除した数で、国庫補助の対象とならない減免分は除く。
現下の厳しい経済環境や家計状況を反映し、奨学金や授業料減免などによる支援学生等は増加している。
* * *
教育は憲法や関係法で保障されているが、その教育を実効あるものとするためには、教育に必要な全ての費用、つまり「教育費」の充実が必要である。
教育費の負担は、国や自治体等による「公的負担」と、家計(学納金・通学費等の学費)や学校(寄附金・大学等の産学連携収入等)、民間企業、団体等の「私的負担」がある。とりわけ、家計における教育費は、幼稚園から大学までの就学者を抱える世帯にとって“重い負担”となっている。家計を圧迫する重い私的教育費を軽減するための公的な経済支援として、前述した「支援機構」の奨学金事業(大学等)や国費による国立大・私立大の授業料減免事業、高校の授業料無償化、高校等の奨学金事業などがある。(図2参照)
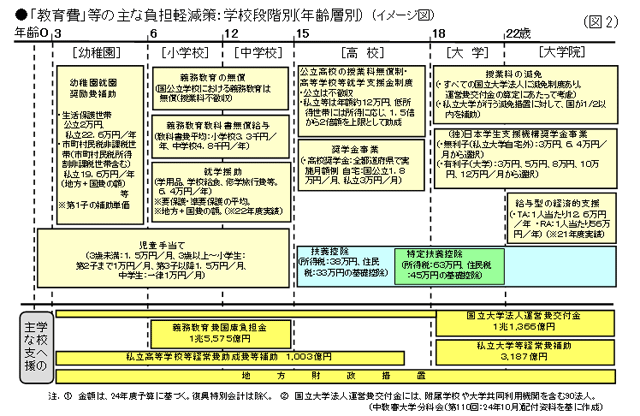
~ すべて公立(国公立大)=770万円 / すべて私立=2,230万円 ! ~
ところで、幼稚園から大学卒業までの教育費は、いくらかかるのか。教育費の私的負担(保護者が支出した経費)の実態、及び家計の負担感が重い大学の「学費」についてみてみる。
表1と図3は、幼稚園から大学(学部・昼間部)卒業までにかかる平均的な教育費を、学校段階ごとに国・公・私立別に区分して算出したものである(文科省『子どもの学習費調査報告書』/「支援機構」の『学生生活調査報告』。いずれも22年度調査)。
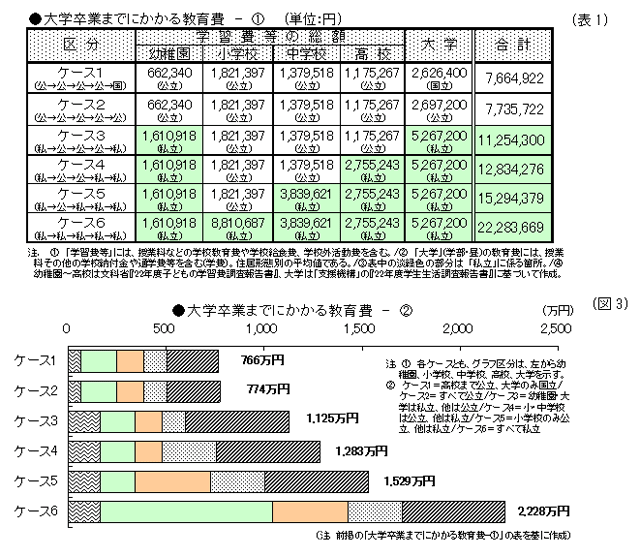
ここでの教育費の内容としては、子ども1人当たりの幼稚園~高校(全日制)卒業までの15年間の「学習費総額」(授業料等の学校教育費、学校給食費、学習塾費等の補助学習費を含む学校外活動費)、及び大学(学部:昼)4年間の「学費」(授業料等の学校納付金、課外活動費、通学費等)の平均額の合計である。
● 高校「授業料無償化」で、高校の「教育費」軽減
22年度調査の幼稚園から高校までの「学習費総額」の推移をみると、高校を除く各学校種ともほぼ横ばい状態であるが、高校は公立高校の授業料無償制と私立高校等就学支援金の経済支援によって減少している。
また、公立学校における「補助学習費」は、高校受験準備のための支出額が中学生の学年を追って多くなり、中学3年生が最も多い。一方、私立学校では中学受験準備のための支出額が小学生の学年を追って多くなり、小学校6年生が最も多くなっている。
● 「教育費」の公私格差
幼稚園(3歳)から高校3年生までの15年間、すべて公立に通った場合の教育費は503万9,000円、すべて私立の場合は1,701万6,000円(公立の3.4倍)である。さらに、大学卒業まで4年間の教育費を加えると、幼稚園から高校まで公立、大学は国立大で766万5,000円、公立大で773万6,000円かかる。また、幼稚園・大学が私立、小・中・高校が公立で1,125万4,000円となり、大学まですべて私立だと2,228万4,000円かかる。(表1・図3参照)
こうした教育費の実態をみると、厳しい経済状況等を踏まえ、低所得者層への更なる経済支援の充実や公(国)・私立間の教育費格差の是正が求められる。
「学費」には、授業料や入学料などの学納金のほか、通学費や図書費なども含まれるが、ここでは授業料や入学料を中心にみてみる。
◆ 国立大の授業料・入学料等
国立大の授業料、入学料などは、16年度の法人化以降、国が定める「標準額」の120%の範囲内において、各大学が設定する(国立大等の授業料その他の費用に関する文科省令)。
国立大の25年度の初年度納付金(昼間部)は、国の定めた「標準額」である入学料28万2,000円、授業料53万5,800円の合計81万7,800円(文系・理系の別なし)が基本である。
ただし、実習費や災害傷害保険料、学友会費等により、大学や学部(学科)で異なる場合がある。また、夜間部は、授業料・入学料とも昼間部の半額となっている。
◆ 公立大の授業料・入学料等
公立大の財源は、主に授業料や入学料等による学納金と、地方公共団体からの拠出金に大別される。最近急増している公立大学法人に対する地方公共団体からの拠出については、運営費交付金が充てられ、それ以外の公立大にはそれぞれの地方公共団体の予算において措置される。そして、地方公共団体の主な財源は、地方税と地方交付税である。
こうしたことから、公立大の授業料や入学料等は地方公共団体によって異なるが、授業料は概ね国立大の「標準額」に準じている。
入学料はほとんどの場合、大学の地元出身者(地域内)と地元以外(地域外)の出身者とで異なる。「地域内」の場合は、国立大の「標準額」とほぼ同額か、それよりも低額であるが、「地域外」の場合は、「地域内」より一般に高額である。
◆ 私立大の授業料・入学料等
私立大の授業料や入学料、施設設備費などの「学費」は、大学や学部系統でかなり異なる。
私立大の24年度(昼間部)授業料、入学料などの平均額は、次のとおりである。
授業料は、医歯系で約280万3,000円、理科系で約103万6,000円と高額であるが、文科系では約74万2,000円で、全平均では約85万9,000円と、国立大の約1.6倍である。
入学料は医歯系学部の約103万5,000円を含め、全平均では約26万8,000円となり、国立大より低額である。
施設設備費は医歯系が約88万3,000円と高額であるが、全平均では約18万9,000円となる。このほか、実験実習料やその他の納付金の平均額を加えた総額、つまり24年度私立大入学者(1人当たり)に係る初年度納付金総額の平均は約144万3,000円で、23年度より約1万円(0.7%)の減額となっている。なお、授業料は23年度より約1,600円(0.2%)増額、入学料は約1,900円(0.7%)減額である。
◆「学費」の格差:国立大 VS.私立大
● 国・私立大の「授業料」格差は、38年前の5.1倍から1.6倍に“縮小”
昭和50(1975)年度、国立大授業料は3万6,000円、私立大授業料(平均)は18万2,677円で、私立大の授業料は国立大の5.1倍であった。翌51年度には国立大の大幅な値上げ(9万6,000円)によって、国立・私立の授業料格差は2.3倍に縮まった。
その後は昭和56年度まで、国・私立の格差は2倍台を推移してきた。
さらに、昭和57年度の1.9倍、昭和58年度の2.0倍を経て、昭和59年度以降は1倍台後半(昭和61年度は2.0倍)を推移し、平成9(1997)年度以降は24年度まで1.6倍を維持している。(図4参照)
● 国・私立大の「入学料」は、16年度以降、国・私立“逆転”
昭和50年度の入学料は国立大5万円、私立大9万5,584円(平均)で、私立大は国立大の1.9倍であった。その後、昭和57年度まで私立大の入学料は国立大の2倍以上であったが、昭和58年度に1.8倍となって以降、入学料の格差は縮小していった。
そして、平成16年度の入学料が国立大28万2,000円、私立大27万9,794円となったことで、それまでの「国立大 < 私立大」の入学料格差は“逆転”現象を起こし、現在に至っている。
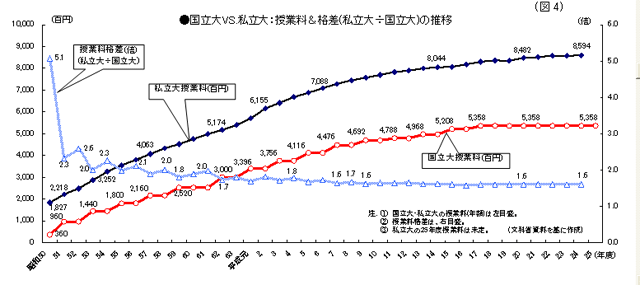
景気は一部、回復基調にあるともいわれるが、厳しい経済状況の下、大学への進学を断念せざるを得ない高校生も少なくないとみる。24年の勤労者世帯(2人以上のサラリーマン世帯)の1か月の平均収入(実収入)は1世帯当たり約51万9,000円で、その12年前に当たる平成12年の約56万3,000円に比べて約7.8%減額している(総務省「家計調査」)。
他方、大学の授業料を12年度と24年度で比べると、私立大は約7万円(8.8%)増、国立大は5万7,000円(11.9%)増となっている。
また、首都圏の私立大では、受験から入学までの費用負担(受験費用や初年度納付金、家賃、生活用品費等)について、9割以上の家庭が“重い”と感じている調査結果もみられる。
ところで、25年の18歳人口と高卒者数(中等教育学校後期課程卒業者含む)はともに3%以上増加したにもかかわらず、大学(学部)入試の「現役志願率」(現役志願者数<実数>÷高卒者数)は前年より0.1ポイント低下の54.9%で、「現役進学率」(現役の大学<学部>入学者数÷高卒者数)も0.3ポイント低下の47.4%である。特に大学進学適齢期である18歳人口の「大学(学部)進学率」(既卒者等含む大学<学部>入学者数÷18歳人口)は前述したように、24年より0.9ポイント低下の49.9%で、5年ぶりに“50%割れ”となっている。
その一方で、専門学校への「現役進学率」は前年より0.2ポイント上昇の17.0%で4年連続上昇している(文科省『25年度学校基本調査速報』)。
こうした大学進学率の下降と専門学校進学率の上昇は、大学進学の経済的な負担や将来の就職などを見据えた結果とみられる。
* * *
学生等への経済的支援は、前述したように憲法や関係法で保障されており、大学等の高等教育の「無償教育の漸進的な導入」を目指すことが国際人権規約で求められている。
全国の大学生(学部・昼間部)のうち、「支援機構」や各大学等の奨学金を受給している学生の割合は、22年度で50.7%(20年度より7.4ポイント増加)である。そして、学生1人当たりの年間総収入約199万円に占める奨学金は約40万3,000円(20.3%)で、6割以上(約123万円)は家庭からの給付による(「支援機構」の『22年度学生生活調査報告』)。
こうした状況の下、文科省は25年4月、学生への経済的支援の在り方等を検討する有識者会議「学生への経済的支援の在り方に関する検討会」(主査=小林雅之・東京大教授。以下、「検討会」)を設置した。
文科省の「検討会」ではこれまで、学生の置かれた経済状況や経済的支援の目指すべき方向性、「支援機構」の奨学金制度の改善方策などを検討し、次のような提言を盛り込んだ『学生への経済的支援の在り方について』(中間まとめ案:25年7月末)を提示した。
学生等への将来目指すべき経済的支援の方向性としては、ステップとして、①授業料減免等の“給付的支援”の充実による負担軽減、②現行の「支援機構」の貸与奨学金制度の改善をそれぞれ図ることを挙げている。
②の「貸与型奨学金」については、“奨学の観点”から、進学が経済的に困難な学生等に必要な学資を確実に提供するとともに、卒業後は所得に応じた月額の返済方式(経済的困難度に応じた免除も含む)にして将来の返済への不安を払拭すること/“育英の観点”から、「貸与型奨学金」の受給生のうち、特に成績優秀者へのインセンティブとして、奨学金の返済を免除すること、などの仕組みの構築・充実を図っていくことが必要であるとしている。
◆ 貸与型支援の在り方
● 無利子奨学金の拡充
意欲や能力のある学生等が経済的事情で進学を断念することないよう、教育機会を保障するという奨学金の本来の趣旨に立ち返れば、「支援機構」の「貸与奨学金」は“無利子奨学金”が本来の形であり、有利子奨学金はその補完的な役割を果たすべきであるという(「日本育英会法案に対する附帯決議」<衆議院文教委員会:昭和59年7月>等による)。
そして、奨学金の需要に対応するために有利子奨学金の拡大を図ってきた近年の施策を改め、本来の趣旨に立ち戻り、無利子奨学金を基本とすることを目指すべきであるとしている。また、奨学金の支給対象層の不断の見直しや貸与基準の検証も求めている。
こうした方向性を踏まえ、まず、次のような具体的な改善方策を挙げている。
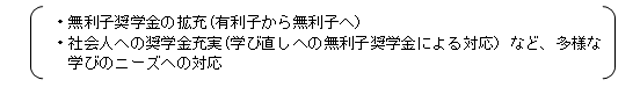
◆ 経済状況に応じた返還方法
● 所得連動返済型奨学金制度
「支援機構」では前述したように、24 年度から「所得連動返還型無利子奨学金制度」を導入している。当制度は卒業後の年収が300
万円を下回っていること/当制度の対象者の貸与時の世帯年収が300万円以下であること/無利子奨学金であること、といった限定的な範囲で返済が所得に連動する制度である。
当制度をより柔軟な制度にすることなども含め、返済者の経済状況に応じた返還方式の改善策として、次のような事項を挙げている。
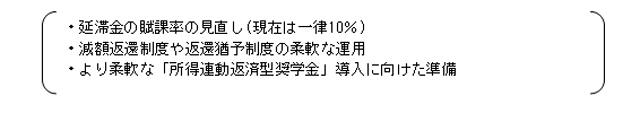
◆ 給付的な支援 ~ より手厚い支援として ~
● 家計と進路選択
高校等の後期中等教育段階から大学等の高等教育段階への進学時において、国による“給付的な経済支援”としては、前述したような大学等の“授業料減免”が行われているが、「給付型奨学金」は現在導入されていない。一方、国際的には、ほとんどの先進国で給付型奨学金制度が実施されている。
大学等への進学には様々な要因が関連しているが、家庭の経済的状況(家計)が進学あるいは就職といった若者の進路選択に大きな影響を与えていることは間違いない。
◎ 給付的支援の方向性
「検討会」では、保護者の経済的格差が、子の教育格差として次の世代に引き継がれることのないよう、前述した“高等教育段階の無償教育の漸進的導入”を理念とし、「給付的な支援」の充実は、高等教育における重要な課題であると断じている。
「給付的な支援」には様々な形態が考えられることから、「検討会」では次のような点を検討のうえ、制度設計を行うことを求めている。
◎ 給付目的と受給のタイミング
・ 事後給付:在学中の学修のインセンティブを高める観点からは、卒業時に返還免除する“事後給付”が効果的であるという。
・ 事前給付:将来の予見性をもって安心して進学できることも極めて重要な課題である。この観点から、入学時又は進学前に受給の可否が判断できる「給 付型奨学金」や「授業料減免」の“事前給付”が効果的であるという。
事後給付、事前給付のいずれの政策目標を重視した制度設計にするのか。
◎ 制度のターゲットと支給基準
“家庭の経済状況”を重視した基準とするのか、“学業成績”をどの程度重視した要件とするのか。
また、様々な主体が実施する経済的支援との関係(併給の可否等)についても整理することが必要であるとしている。
◎ 給付すべき内容
修学に必要な全額を給付するのか、一部を貸与奨学金で賄うことを前提とする場合にはどの程度の金額を給付することが適切か。
◎ 実施方法
・ 受給対象者の選定(特に成績要件等の評価):給付的な支援では、貸与以上に、受給者の選定の公平性が厳しく問われる。
選定には学校、「支援機構」又はその他の機関がどのように関与すべきか/大学等で判定する場合には、複数の学校が連携して実施することが適切ではないか/選定基準や受給者についてオープンにすれば、透明性の確保により公平性が担保され、また受給者への意識付けにもつながることから、効果的ではないか。
・ 現行の貸与奨学金と同様に「支援機構」を通じた支給が適切か、あるいは各大学等を通じた支援が適切か。
・ 教育や研究と連携した取組として、学内のワークスタディやTA・RA等としての学生等の活用は、当該学生等に対する教育研究上の効果のみならず大学等の機能の充実にも資する点で意義が大きく、このような取組の活性化も同時に考えていくべきではないか。
◎ 給付的支援の具体的な取組
給付的な支援の具体的な取組として、以下のような事項を挙げている。
・ 授業料減免等の拡充
現行の授業料減免制度は、公的支援の在り方が異なること/特に私立大では、大学によって学生が受けられる経済的支援に差があること/公立大については地方公共団体あるいは公立大学法人の裁量により実施されていること/専修学校専門課程(専門学校)における授業料減免措置は公的支援の対象とされていないことなどに鑑みれば、授業料減免制度も含めた給付的な支援策全体の制度設計について整理し直すことにも留意する必要がるという。
・ 奨学金を含め、その他の経済的支援の制度改善
奨学金を含めた経済的支援の制度改善については、目的・ターゲット層に応じた制度改善を求めている。改善の検討事例として、次のような事項を挙げている。
* 特に経済的困難(児童養護施設入所者、生活保護世帯等)で優秀な層に応じた給付的支援の充実についての検討。
* 卒業時の返還免除について、現行の大学院在学中の業績に応じた免除の他に、大学の学士課程等免除対象とすべき層がないか、対象や分野などを検討。
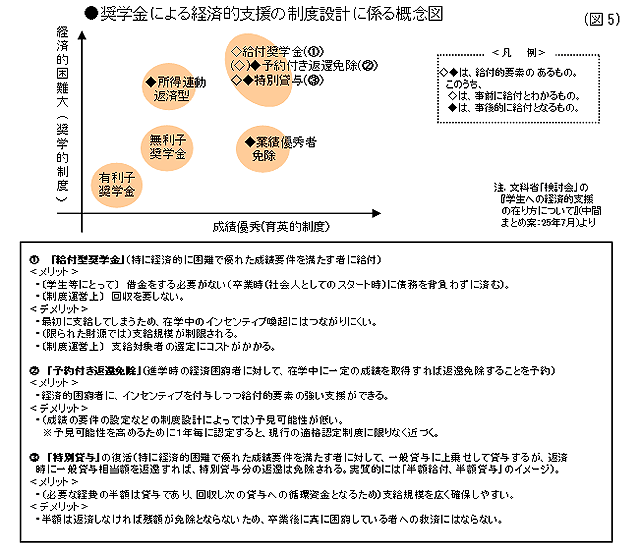
* * *
大学は、国立、公立、私立を問わず、本質的に公共性を有する高等教育機関である。大学教育で育成された人材は、幅広い教養と専門的な知識・技能を備えて様々な分野で活躍し、社会の発展に貢献している。
つまり、大学教育は、学生個人に生じる私的便益だけでなく、大きな社会的便益も有している“公共財”である。
我が国では教育費に対する根強い“受益者負担”論などから、教育機関への公財政支出の対国内総生産(GDP)比は国際的にみて低い。OECD(経済協力開発機構)の『Education at a Glance2012:図表でみる教育 2012年版)』によると、21年度の我が国の全教育段階における教育機関への公財政支出の対GDP比は3.6%、OECD平均5.4%で、比較可能なデータのあるOECD加盟国のうちで最も低い。
また、高等教育機関への公財政支出の対GDP比は0.5%で、OECD平均の1.1%を大きく下回っている。(図6参照)
さらに我が国は、教育支出に占める私費負担の割合が高い。特に我が国の高等教育機関への教育支出の「公私負担」割合は、公財政支出35.3%(OECD平均70.0%)に対し、私費負担64.7%(同30.0%)である。私費負担のうち、家計負担は教育支出全体の50.7%と極めて高い。(図7参照)
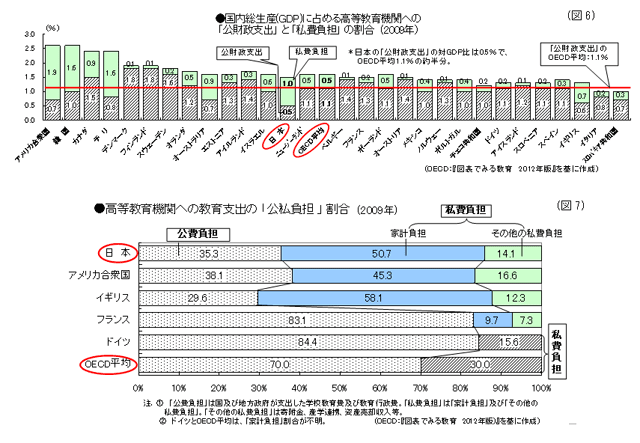
文科省は25年8月末、26年度の「概算要求・要望」総額、5兆9,035億円(25年度より5,477億円、10.2%増)を財務省に提出した。
このうち、安倍政権が重視する政策は「新しい日本のための優先課題推進枠」という「特別枠」において、“要望額”として合計8,402億円を計上している。「特別枠」には、教育再生の実現、科学技術イノベーションの推進、スポーツ立国・文化芸術立国の実現といった取組が盛り込まれている。
大学等奨学金事業としては、事業費1兆2,301億円(25年度より320億円増)で、海外留学のための無利子奨学金制度の創設などによる無利子奨学金貸与人員の大幅増や、真に困窮している奨学金返還者の救済措置の拡充などが盛られている。
教育は個人のみに帰属するものでなく、社会に還元される公共財である。したがって、教育への投資は、個人と社会の発展の基盤となる“未来への投資”といえる。
そして、教育政策を確実に実行していくためには、公財政支出の確かな裏打ちが必要だ。
25年度~29年度の国の教育振興に関する総合計画の中教審答申『第2期教育振興基本計画について』(25年4月)では、教育機関への国際的に低い公財政支出を「将来的には恒久的な財源を確保し、OECD諸国並みの公財政支出を行うことを目指す」としていた。
しかし、25年6月の“閣議決定”では、教育予算をOECD諸国並みにするには約10兆円の引き上げが必要だとする財務省の反発などで、「OECD諸国など諸外国における公財政支出など教育投資の状況を参考として、真に必要な教育投資を確保していく」などと、後退した表現になっている。
いずれにしろ、「教育立国」「科学技術立国」を標榜し、グローバル人材の育成を掲げる我が国にとって、“人材=教育”が貴重な資源であり、教育は国を支える“公共財”であることを改めて認識しておくことが大事だ。
その上で、少子・超高齢社会と厳しい経済・財政状況などを踏まえつつ、社会の発展に寄与し、将来を担う次世代への教育費の「私費負担」(受益者)と「公財政支出」(国、自治体)とのバランスを考えるべきである。
