24年2月に入り、先月多大な混乱を招いてしまったセンター試験の後、大学の一般入試が本番を迎えている。24年は、大学受験生約66.6万人(旺文社推定)が740校余の国公私立大に挑み、4月には60万人ほどの大学生が誕生するとみられる。今や、大学受験生の9割強が入学を果たす所謂“全入”時代であり、18歳人口の5割強が大学に進学するという、高等教育発達段階の最終ステージである“ユニバーサル”段階に達している。
その一方で、小規模校を中心に私立大の4割弱が“入学定員割れ”状態にある。
昨冬行われた政府の行政刷新会議では、少子化傾向の中での大学の数や規模の拡大、入学定員割れによる学力低下や赤字経営の増加などの問題点が提起された。
ここでは、少子高齢化の進展と大学の適正規模に係る大学の在り方などを探ってみた。
* * *
21世紀は「知識基盤社会」といわれる中、急速に進展する情報化やグローバル化等で社会のありようが複雑化している。大学には、そうした社会の多様なニーズに応えうる高度な教育研究の質保証が求められている。
他方、我が国は少子高齢化が進む中、世界的な金融経済危機や円高、31年ぶりの貿易収支の赤字など厳しい経済状況にあって、公的債務残高1,000兆円に迫る巨額の財政赤字を抱えている。加えて、23年3月11日の東日本大震災、福島第一原発事故は未曽有の災厄をもたらし、科学技術から社会生活まで、これまでの既成概念をも一変させた。
こうした昨今の社会環境の厳しく激しい変化の中で、大学の今後の進むべき基本的方向性を探る前に、「バブル経済崩壊」以降現在に至るまでのほぼ20年間の大学進学の変遷をたどってみよう。
まず、平成3(1991)年前後の「バブル経済崩壊」以降、23年までの18歳(大学進学適齢期)人口の推移をたどると、4年の204.9万人(第2次ベビーブーマー)を直近のピークとし、途中一時的な微増(13年、22年)がみられるものの、ほぼ“右肩下がり”で減少している。
高卒者数や大学(学部。以下、同)受験生数(実数)もこうした減少傾向にほぼ沿った形で減少してきた。因みに、23年の18歳人口は120.2万人で4年(204.9万人)の6割弱、高卒者数も106.4万人(「23年度学校基本調査速報」において、24年1月現在、東日本大震災の影響で岩手・宮城・福島県の23年の高校関係データが除外されているため旺文社推測。以下、同)で4年(180.7万人)の6割弱、大学受験生数は67.6万人で4年(92.0万人)の7割強まで減少している。
上記のような18歳人口・受験生数の減少傾向に対し、受験生の受け皿となる大学入学定員(国公私立大)は、4年の47.2万人から23年の57.8万人へと“右肩上がり”の増加をたどっている。その結果、大学の「収容力」(入学者数<外国の学校卒等含む全ての入学者>÷志願者数<志願した受験生数:実数>)は4年の約59%から23年の約91%へと、所謂“全入”状態を呈している。(図1・図2参照)
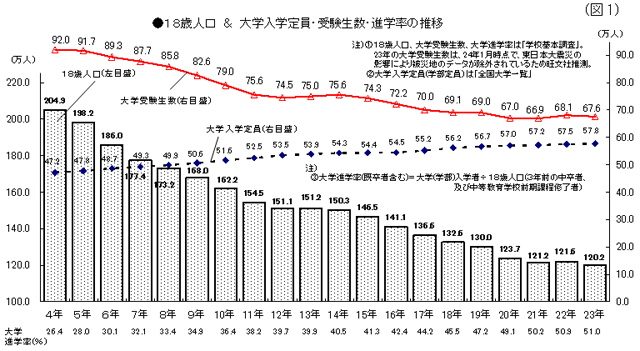
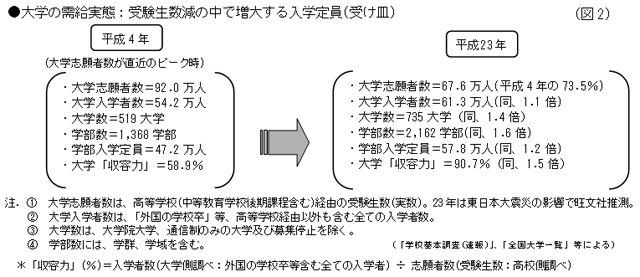
また、高校から大学への進学意欲は生徒・保護者とも年を追って高まりをみせ、この5年ほどの大学への現役志願率は、19年51.8% → 20年53.5% → 21年54.9% → 22年55.7% → 23年55.5%(推測)と、23年に若干の低下が推測されるものの、5割台半ばを維持している。
高等教育研究の第一人者マーチン・トロウ(アメリカ)は、高等教育制度の発達段階を、大学・短大への既卒者を含む進学率(大学・短大入学者数÷進学適齢者数<18歳人口>)を基に“エリート”段階(進学率15%まで)/“マス”段階(同15%超~50%まで)/“ユニバーサル”段階(同50%超)の3段階に区分している。
我が国の大学・短大への進学率(既卒者含む。以下、同)は、昭和38(1963)年に“エリ-ト”段階の上限指標である15%を突破して以降、昭和48(1973)年~平成4(1992)年30%台、5年に40.9%に達した後も毎年上昇を続け、11・12(2000)年49.1%(同率) → 13・14年48.6%(同率) → 15年49.0% → 16年49.9%と、“マス”段階を一気に突き進んできた。そして、17(2005)年には51.5%となり、進学率50%超の“ユニバーサル”段階に達した。
また、大学(学部)への進学率においても、21(2009)年に50.2%に達し、“ユニバーサル”段階に入っている。(図1参照)
因みに、23年の進学率は、大学・短大56.7%、大学51.0%である。
ところで、マーチン・トロウは高等教育システムの発達段階とその特徴について、例えば、エリート段階では「高等教育の機会」は“少数の特権”で、「大学進学の要件」は“制約的”であるとし、ユニバーサル段階ではそれぞれ“万人の義務”となり、“開放的”になるなどと例示している。こうした状況は、我が国の高等教育、とりわけ大学進学がたどった実態と重なってくる。
大学等(短大を含む)の高等教育の量的規模に関しては、文部省(当時)が18歳人口の増減や大学等への進学動向などを踏まえ、昭和51(1976)年度以降、平成16(2004)年度まで5回にわたって「高等教育計画」(平成12~16年度は「高等教育の将来構想」)を策定、実施してきた。
特に平成5年度以降は18歳人口の急減等を踏まえ、大学等の新増設や定員増は“原則抑制”の方針が採られた。
一方、政府の「総合規制改革会議」の「高等教育における自由な競争環境の整備」(大学・学部設置等の認可に対する抑制方針の見直し:13年12月)や、中教審答申『大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について』(14年8月)における“量的規制の撤廃”及び“設置認可の弾力化”(15年4月から実施)などに加え、14年7月には「工業(場)等制限法」(首都圏と近畿圏の一部区域での大学等の新増設を制限)が“撤廃”(15年4月から実施)された。文科省はこれらを踏まえ、「高等教育の将来構想」における大学等の全体規模及び新増設についての“抑制的対応”の基本方針を“撤回”へと舵を切ることになる。
18歳人口の減少傾向の中、大学の量的規模が拡大してきた背景には、大学への進学意欲の高まりに加え、前述のような一連の規制緩和や規制撤廃によって大学間の競争的環境を醸成し、大学の個性化・特色化を促進してきた高等教育政策の影響があろう。
もちろん、大学の量的規模の拡大には、その時々の社会の仕組みや産業構造、特定分野における人材養成、地域の高等教育需要などへの対応、短大から大学への改組・転換(短大=縮減、大学=拡大:スクラップ&ビルド)といった要因もある。
私立大は、戦後の新制大学への転換で自主性と公共性を柱とし、建学の精神や特色を尊重する学校法人として昭和24(1949)年度には92校(23年度に11校)が誕生している。因みに、国立大は24年度から70校、公立大は23年度1校、24年度17校で発足している。
そして、昭和30(1955)年代~40年代の高度経済成長期には、増大する大学進学志望者(第1次ベビーブーマー<団塊世代>に代表される)の受け皿として、また国公立大とは異なる分野への進出などで私立大の量的規模は急増した。
昭和50年代に入り、大学・短大への進学率が40%近く、大学への進学率が30%近くの“マス”段階に達すると、教育研究の質の維持・向上と量的規模との関係等が問題視され、前述した「高等教育計画」によって大学の計画的な整備が実施されることになった。
その結果、私立大においても、それまでの私学助成をさらに発展、充実させた「私立学校振興助成法」が制定され(昭和51年4月から施行)、「国は私立大等の経常的経費について、その“二分の一以内”を補充することができる」とされ、加えて定員の適正管理などの量的規制や質的水準の確保といった教育研究水準の向上が図られるようになった。
平成期に入ってからは私立大を取り巻く環境も前述したように推移し、23年度時点で、私立大学数599校(大学院大学含む、通信教育のみの大学除く)、私立大学生数約212万6,000人である。国公私立大に占める私立大の割合は、大学数で76.8%、学生数で73.5%に達している。
私立大の量的規模は上記のような状況にあるが、23年度において「入学定員割れ」(以下、定員割れ)となった私立大は223校、39.0%(集計数572校)に達し、全私立大(集計校)の「入学定員充足率」(以下、充足率)は106.4%で22年度より低下している。
ここで注目されるのは、大学の入学定員規模と充足率との関係である。
大学規模別の充足率の動向をみると、過去数年間、「入学定員(以下、定員)600人以上800人未満」の定員区分が定員割れの大きな分岐点となっていた。つまり、「定員800人未満」の中小規模大学では、“定員割れ”状態であった。
しかし、22年度に「地方」の中小規模大学を中心とした充足率の改善がみられ、これまで定員割れの分岐点となっていた「定員600人以上800人未満」の大学が16年度以来、6年ぶりに“脱・定員割れ”を果たした。この状況は23年度にも受け継がれ、23年度は「定員100人未満」(4年ぶりに“脱・定員割れ”)を除く、「定員600人未満」の小規模大学で“定員割れ”状態となっている。(図3参照)
なお、23年度の場合、「入学定員3,000人以上」の大規模大学23校(全校数の4.0%)の志願者数は約150万5,000人(全志願者の46.9%、志願倍率11.5倍)に達し、充足率も110.4%で“強い大規模校の寡占化”が浮き彫りになっている。
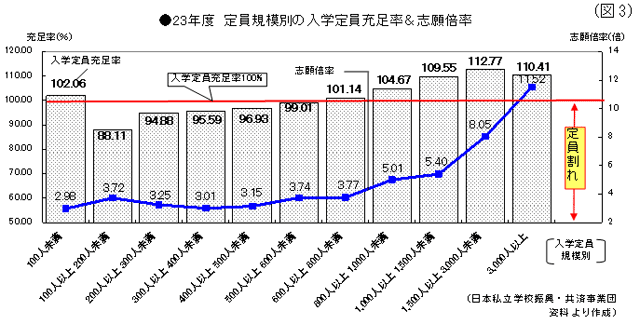
私立大では帰属収入の7割以上を入学金・授業料等の学生納付金が占めており、“入学定員割れ”状態が進むと、帰属収入で消費支出を賄えない“赤字”(帰属収入-消費支出=「帰属収支差額」がマイナス)に陥る可能性がある。
22年度の場合、赤字に陥った私立大は227校、39.2%(集計数579校)で、21年度(586校中、230校が赤字)と同率である。こうした深刻な経営状況は地方の中小規模校を中心にみられ、私立大の「収支」状況も「定員充足率」状況と同様、“地方・小規模校”と“都市・大規模校”といった“二極化”が伺える。(図4参照)
ところで、私立大等に対する国の助成については前述のとおり、経常経費の“50%以内”を補助することができるとされている。しかし、補助割合のこれまでの推移をみると、昭和55(1980)年度の29.5%をピークに年々低下し、最近は11%を割っている。
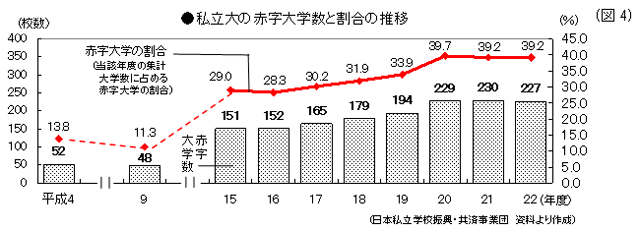
我が国は今後、これまで経験したことのない少子高齢化が進み、人口構成や社会構造、産業構造が大きく変化し、グローバル化もますます進むとみられる。そうした中、大学はこれまでの既成概念にとらわれない大きな構造改革に迫られよう。
これからの大学の役割・使命などを探るうえで、人口構成の変化は重要な要素である。
◆ 今後の18歳人口の推移
現行では一般的な“大学進学適齢期”である「18歳人口」(当該年の3年前の中卒者、及び中等教育学校前期課程修了者)は、平成24年~平成32(2020)年頃までの8年間は後半に漸減するものの、21年から続く120万人程度のほぼ横ばい状態で推移するとみられる。しかし、平成33年頃からは再び減少傾向を示し、平成39(2027)年頃には103万人程度、24年の87%ほどまで減少するとみられている。(図5参照)
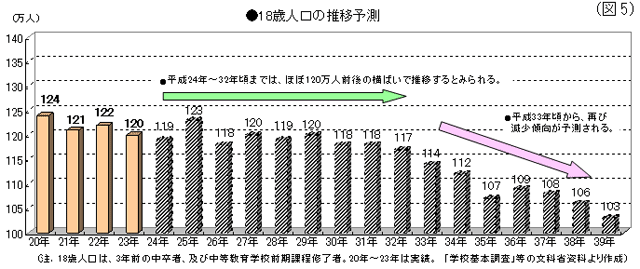
◆ 高齢化の進展
我が国の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合(高齢化率)は、平成21(2009)年で既に23%弱の“超高齢社会”であるが、2030年は約32%、2055年は40%超で、“2.5人に1人が高齢者”であると推定されている。一方、15~64歳の割合は平成21年約64% → 2030年約59% → 2055年約51%と、減少傾向が見込まれている。(図6参照)
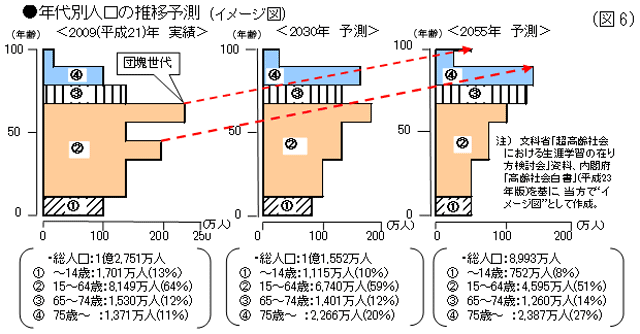
現行の大学入学者の年齢層は18歳に偏っているが、前記のような18歳人口の減少や超高齢社会の進展を踏まえるならば、入学者や学習者層の新たな開拓が必要である。
大学入学者の年齢層については、OECD(経済開発協力機構)平均では入学者のうち25歳以上の割合が22%であるのに対し、日本は2%に留まる(2009年)。
現在、大学では主に社会人向けの教育として、通信教育課程、高度専門職業人の養成課程(専門職大学院等)、科目等履修生制度(学生向けの授業科目を履修して、単位認定される)、履修証明制度(学生以外の者向けに開設された履修証明プログラムを修め、履修証明書が交付される)などのほか、各種の公開講座なども設置されている。ただ、こうした社会人向け教育の取組は最近拡大傾向にあるようだが、まだ社会的な関心や要請は活発とはいえず、大学の取組事業の割合としてもさほど大きくないのが実態といえよう。
とはいえ、今後、急激に進展する少子化、超高齢社会、長寿社会といった人口構成や社会・産業構造の変化に、大学はどう対応していくべきなのか。
大学は18歳に的を絞った“入り口”だけに学生獲得を求めるのではなく、“いつでも、どこでも、多様な就学形態”が可能な“ユニバーサル・アクセス”にシフトした社会人等の獲得が必要だ。これまで以上に「生涯学習」や「リカレント教育」などに積極的に取組み、社会に向けた“門戸開放”を推進していくことは、これからの大学の重要な役割・使命の一つであるといえる。
* * *
本稿ではここまで、大学進学の変遷や量的規模の拡大の背景、私立大の厳しい現状、及び超少子高齢社会と大学の役割などについて述べてきた。
そこで、大学を取り巻くそれらの状況を踏まえ、大学の“適正規模”に改めて視点を当て、大学の今後の行方を探ってみる。
政府の行政刷新会議は23年11月下旬、国会議員(4名)と民間有識者(6名)からなる10名の評価者らによって、大学改革に関する「提言型政策仕分け」の議論、提言を行った。
会議では5つの論点について議論されたが、その中で大学の規模拡大や赤字経営の増加など、下記のような2つの論点が取り上げられた。それらの論点については、次の枠内に再録したような評価者の意見等が出され、改革の方向性が提言された。
◆ 論 点
◎ 少子化の傾向にも関わらず、大学数や入学定員、教職員数が増えているのではないか。
◎ 定員割れによる学力低下等や赤字経営の大学の増加等をどう考えるか。
◆ 評価者の意見、提言等
教育の質の確保と安定的な経営に資するため、大学の数や規模はどうあるべきか。
(1) 大学の数や規模は過大になっており、適正化が必要。 10名
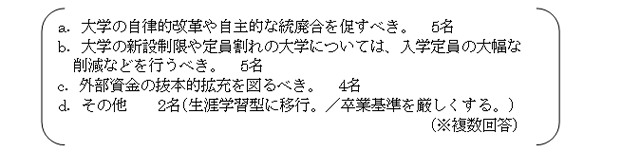
(2) 大学の数や規模は過大とはいえない。 0名
◎ 評価者の提言内容
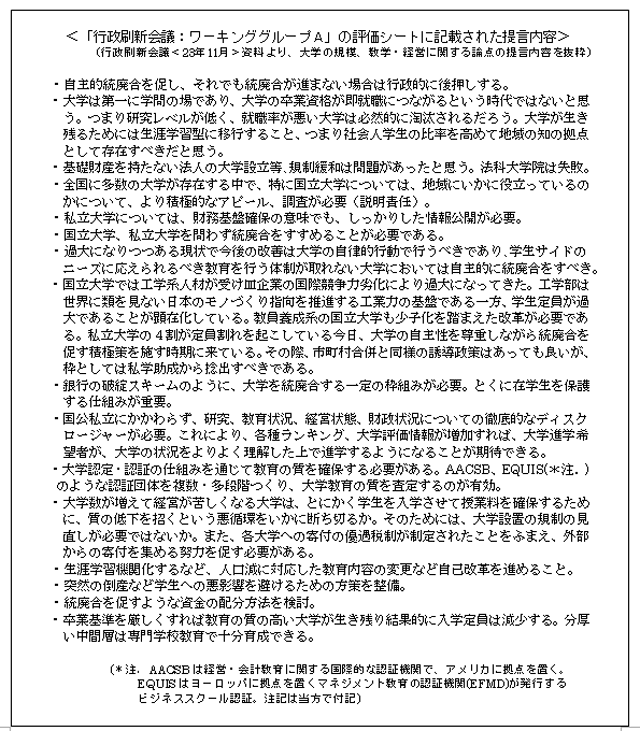
◆ 改革の方向性(取りまとめ提言)
教育の質の確保と安定的な経営の確保に資するため、大学の教育の内容、例えば、生涯教育の拡充などへの転換を含む自律的な改革を促すとともに、寄付金税制の拡充等自主的な財源の安定に向けた取組を促す仕組みを整備する。
今回の行政刷新会議(内閣府)の提言型政策仕分け「教育(大学):大学改革の方向性のあり方」における評価者の意見、改革の方向性(取りまとめ提言)については、これまで中教審などでも議論、提言されており、文科省は関連する様々な施策を講じてきた。
文科省としては今後、この提言を受け、省内での大学改革の共通認識を図りつつ、大学教育の一層の質の確保と安定的な経営の確保に向けた施策を進めていくものとみられる。
大学の量的規模については、行政刷新会議の評価者全員(10名)が「過大であり、適正化が必要」であるとしている。
こうした“大学過剰論”は、定員割れや赤字経営、学力不問とまでいわれる一部の推薦・AO入試、受験生の9割以上が入学を果たす“全入”状態、学生の学力低下などの実態をみれば、一般には当然とも思われる意見であろう。
ただ、大学の量的規模については、こうした大学のいわば“負”の側面だけを捉えて議論すべきなのか。受験生や保護者の大学進学意欲、社会や産業界などからの大学教育に対する需要なども量的規模に関わる重要な要素である。
また、量的規模をみる場合、“質保証”の観点も不可欠である。
◆ 中教審の認識
◎ 『学士課程答申』
大学の“量”と“質”の関係については、中教審答申『学士課程教育の構築に向けて』(20年12月。以下、『学士課程答申』)でも提言されている。
中教審は『学士課程答申』で、大学教育が量的に拡大する中で質の維持・向上を図るという、重大な課題に直面しているとの認識を示している。その上で、大学教育の社会的意義や効用、その可能性を過度に低く評価して大学教育の規模を論ずることは“失当”であるとしている。そして、大学教育の規模等を「量か、質か」といった二者択一で議論することには否定的である。
ただし、大学の在り方について、大学教育の質の維持・向上に向けた努力を怠り、社会からの負託に応えられない大学は、“淘汰”を避けられないと断じている。
◎ 大学分科会での審議
中教審の大学分科会では20年9月に諮問された『中長期的な大学教育の在り方について』を引き続き審議しており、これまでに『第一次報告』(21年6月)~『第四次報告』(22年6月)を提言している。文科省ではそれらの提言を踏まえ、これまでに関連する法令改正も含め、様々な施策を講じている。
大学分科会の現在の主要な審議事項は、①大学教育の質保証・向上/②機能別分化と大学間連携の促進/③大学の組織・経営の基盤強化である。 これらの審議内容は、いずれも大学の“量”と“質”の問題に関わってくる課題であるが、前述の『学士課程答申』の提言趣旨を継承している。
文科省としても『学士課程答申』や前記の中教審『報告』などを踏まえ、大学の量的規模を直接的に削減するといった“手荒な方法”ではなく、設置認可の厳格化、認証評価の改善・強化、機能別分化と大学間連携の促進、定員割れと定員超過に対する改善促進に向けた補助金の減額・不交付措置、私立大の「自立・発展」、「連携・共同」、「撤退」に対する支援、「教育情報」公表の義務化・促進(「大学ポートレート(仮称)」構想)など、大学教育の質の保証・向上及び経営基盤の確立などの観点から、関連施策を講じつつ、大学の取組を支援している。
大学は、こうした文部行政と超少子高齢社会及びグローバル化の中にあって、今後、どんな道を進んでいくべきなのか。
ところで、大学の役割・使命は、設置形態によっても異なる。
国立大は国からの財政措置に大きく支えられ、国家的見地に立った人材養成、教育研究の国際競争力の強化、国家戦略上の中長期的な教育研究、最先端技術の研究開発、大規模施設・設備(経費)を要する教育研究などを担う。公立大は主に地方自治体の公的資金に依存しており、地域社会の特質に応じて、地域医療や看護・福祉の充実、産業の活性化などに対応している。私立大は、受益者負担を前提にしつつ、建学の精神に基づいて多様な教育研究を展開し、大学教育の7割以上を担っている。
こうした設置形態によって大学の役割・使命はそれぞれ異なるものの、その共通理念は教育基本法(大学条項)や学校教育法などで裏打ちされている。
いずれにしろ、これからの大学は前述したように、脱18歳、門戸開放、生涯学習、高齢者・市民教育、及びグローバル化対応などをキーワードに、それぞれの大学の機能と特色にあわせて、受験生や学生、社会から期待される多様なニーズに対応し、教育研究の質の維持・向上とそれを支える組織・経営基盤の強化に努めていくことが重要である。
そして、大学は自校の機能的な特色(機能別分化と個性化)を発揮すべく、改革を不断に行い、それらを大学の外に向けて積極的に分かりやすく発信していくことが大事だ。
他方、社会は、入試難易度に基づく大学の“入り口偏重型”の「評価尺度」だけでなく、大学の“中身”(カリキュラム編成、開設科目のシラバス、単位制度の実質化<学習時間>等)や“出口”(学習成果<学士力>、学位授与、就職、進学等)なども視野に入れた多元的な「評価尺度」で大学を評価すべきである。
大学の存亡は、環境変化への対応、教育研究の質保証、財務の健全化などの取組や成果が社会にどう評価されるか、大学としての存在価値が認められるかどうかに掛かっている。
つまり、大学の“適正規模”は、社会の“評価”と“選択”によって決まってくるといえよう。
