23年センター試験(以下、セ試)は1月15・16日(本試)に実施され、52万人程が受験した。大学・短大受験生の約7割が受験するセ試は、入試制度の基盤として定着し、高校教育にも多大な影響を与えている。セ試がここまで根を下ろし、拡大してきたのは、全ての国公立大参加に加え、私立大の参加増による。
24年の私立大セ試新規参加校の一部はすでに公表されており、最終的には全体で509大学・1,459学部以上が参加、私立大全体の9割近くに達するとみられる。(図1参照)
しかし、その一方で、2年のセ試開始時から参加し(初回の私立大参加16大学・19学部)、21年間、私立大セ試参加の“シンボル”的存在であった慶應義塾大が、24年から撤退する。
国公立大のみの共通第1次学力試験(以下、共通1次試験)を引き継いだ私立大参加のセ試開始当初の経緯、慶應義塾大のセ試参加と撤退の背景、セ試の抱える課題などを探った。
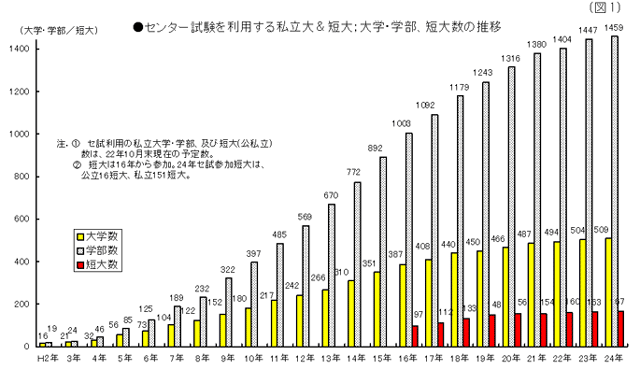
* * *
大学入試の改革・改善はこれまで、大学側主導の下で行われてきたことは否めないが、高校教育と大学教育とのつながりの観点から、それぞれの時代における文教政策、社会の要請・批判等を背景に、螺旋階段を上るように試行錯誤を繰り返しながら行われてきた。
まず、昭和40(1965)年代、団塊世代による18歳人口の激増、大学進学志望者の増加(大学志願率の上昇)などに対し、難問・奇問の入試問題、合格率の低下、大学「収容力」の低下など、“受験戦争”とまでいわれるほど、大学入試の過酷さが社会問題化していた。
そうした中、中央教育審議会(以下、中教審:当時の文部大臣の諮問機関)答申『今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について』(昭和46<1971>年6月:『四六答申』)は、大学入試制度の改善方策として、「調査書」の活用とともに、“広域的な共通テスト”を開発し、高校間の学力評価水準の格差を補正することなどを提言した。
このように当初、高校間の「調査書」の評価水準の格差補正を想定した“広域的な共通テスト”構想は、後に国立大学協会(国大協)の入試改善の検討過程において「高校における一般的・基礎的な学習の達成度を共通尺度で評価するための試験」として位置づけられ、入学者選抜の“第1段階試験”としての性格が明確化された。
当時、国立大の間では、学力試験を第1次試験(客観式)と第2次試験(論述式)とに分け、両者を組み合わせる選抜方法が提唱されていた。
この“第1段階試験”が「共通1次試験」の創設へとつながり、共通1次試験は大学志願者の高校における一般的・基礎的な学習の達成度を測ることを目的に、入学者選抜に利用する“選抜試験”として位置づけられたのである。
共通1次試験は昭和54(1979)年1月、公立大も参加して第1回が実施され、平成元(1989)年までの10年間、合計11回、国公立大の間で利用された。(図2参照)
・ 国立大「1期・2期校制」廃止と試験期日の“一本化”
共通1次試験の実施に伴い、それまでの国公立大の入試制度が大きく変わった。
国立大では、新制大学発足時の昭和24(1949)年から第1回共通1次試験実施前年の昭和53(1978)年までの間、試験期日を2分していた「1期・2期校制」を廃止した。1期・2期校制では、まず1期校の試験日が3月初旬、2期校の試験日は1期校の合格発表後の3月下旬に設定(公立大は3月初旬から各大学で定める)されていたことなどから、国立大の間で“差別観”を招いた。この制度の廃止で、国立大の試験期日は“一本化”された。
・ 受験機会の“複数化”と“猫の目”入試
国立大の試験期日が一本化された昭和54年~61(1986)年まで、国立大及びほとんどの公立大の2次試験日は3月初旬に統一されたため、受験生への措置として「自己採点方式」(共通1次試験の自己採点結果に基づいて出願先を選択)が導入された。
この試験期日の“一本化”は大学の“序列化”や進路指導の“輪切り”現象(後述)に拍車をかけたとされ、昭和62(1987)年からは受験機会の“複数化”
(連続方式:国立大は昭和62年~平成8<1996>年まで、公立大は10年までそれぞれ実施/分離分割方式:平成元<1989>年~)が図られるとともに、大学への出願を共通1次試験実施前に行うことになり(事前出願)、「自己採点方式」は一旦廃止された。
しかし、大学への出願期間を63年から再び共通1次試験実施後としたり、出願方法(連続方式と分離分割方式との併願の仕方)を変更したり、国公立大入試制度の度重なる変更は当時、“猫の目”入試などといわれ、入試改善のための“試行錯誤”そのものであった。
・ 臨教審の「共通テスト」提言
共通1次試験は難問・奇問を排し、良質な出題の確保などの点で評価を得た。
しかし、国立大試験期日の一本化時代、単一の受験機会と、国立大の共通1次試験の受験が一律に5教科7科目(昭和62年~平成元年は5教科5科目が主流)課せられたこととが相俟って、大学(学部)の序列化が顕在化し、これによる輪切りの進路指導が行われていた。加えて、共通1次試験の利活用が、私立大を除外した国公立大のみに留まっていたことも問題視されていた。
こうした状況の中、共通1次試験の問題点を改善すべく、当時の臨時教育審議会(以下、臨教審:総理大臣の私的諮問機関)は『第1次答申』(昭和60<1985>年6月)の『大学入学者選抜制度の改革』において、偏差値偏重の受験競争の弊害を是正し、受験生の個性・能力・適性等の多面的な判定や、“国公私立大”を通じて各大学が自由に利用できる「共通テスト」の創設を提言した。
・ 「共通テスト」提言 →「新テスト」(仮称) →「センター試験」へ
臨教審の「共通テスト」提言を受けた文部省(当時)は昭和60(1985)年7月、国公私立大、高校関係者等からなる「大学入試改革協議会」を設け、提言の具体化に向けて検討・協議を重ね、63
(1988)年2月、共通1次試験に代わる「新テスト」(仮称)の実施概要を盛り込んだ最終報告『大学入試改革について』をまとめた。
「新テスト」(仮称)の検討・協議の過程では、共通1次試験の延長線上を想定する国公立大側、“脱・共通1次試験”を前提に新たな試験システムを想定する私立大側、実施時期等で学校現場に大きな影響を与えないよう求める高校側と、それぞれの立場で様々な角度から検討、議論されたという。
結果的に「新テスト」(仮称)は大筋として共通1次試験を引き継ぐが、最大の相違点は、私立大の参加促進、及び偏差値による輪切りの進路指導と大学の序列化の解消等を狙い、教科・科目等の利活用は各大学(学部)の特色等に応じて自由に任されたことである(「アラカルト方式」の採用)。これは、臨教審答申の大学入試改革の趣旨を活かしたものといえる。
また、「新テスト」(仮称)の名称を巡り、「基礎基本テスト」「利活用テスト」「自由テスト」「選択テスト」等が俎上に載ったようで、それぞれの立場による「新テスト」(仮称)の構想がうかがえる。「新テスト」(仮称)は63年8月、文部省によって「大学入試センター試験」と命名され、平成2(1990)年1月、私立大も参加して第1回が実施された。(図2参照)
* * *
共通1次試験を衣替えしたセ試の成否は、私立大の参加如何にかかっていたといえる。
私立大は建学の理念に基づいて自主的、個性的な教育を行っており、入試も単一で画一的な「共通テスト」には馴染まず、各大学(学部)で「独自試験」(自前入試)を行っていた。
とはいえ、私立大でも、受験生の基礎学力の到達度を共通的・客観的にみる“尺度”への期待、自前入試の負担(経費)軽減や作題能力等の点から、セ試への参加が検討された。
ただ、共通1次試験にみるように、セ試の出題水準は国公立大志願者の平均的学力を相当程度意識したレベルになるとみられていたため、私立大の中小規模校(自前入試の負担率が高い傾向)などでは、出題レベルや内容等への懸念も少なくなかったようだ。これについては、前述の「新テスト」(仮称)の実施概要で、「テストの水準については、当面は現在(当時)の共通1次試験の水準を超えないようにし、高校教育における基礎的・基本的な内容の学習の達成の判定に必要な限度において行うこととする」と、一定の歯止めをかけている。
また、私立大も参加しやすいように、セ試の利活用についても、総合的な利活用のほか、特定の教科・科目のみ/教科・科目内の特定の分野のみ/面接、小論文等の前段階として/推薦入学の資料として/入学定員の一部についての利活用などを例示し、各大学の判断と創意工夫により自由に利用すべきものであることを謳っている。
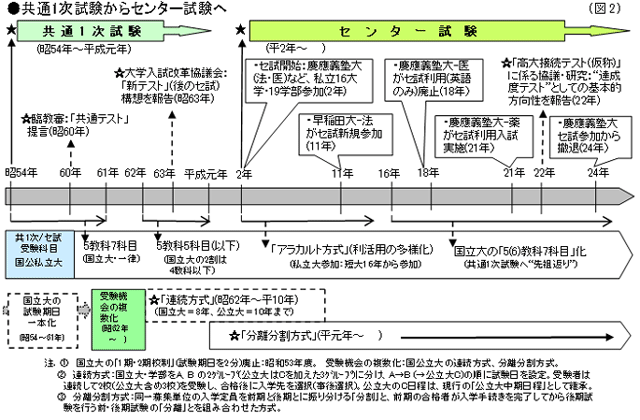
私立大のセ試参加は当初、50校程度が前向きに検討していると伝えられていた。
しかし、第1回セ試には、八戸大-商/足利工大-工/白鴎大-経営/桜美林大-文・国際/慶應義塾大-法・医/昭和女子大-文/東京理科大-基礎工/日本歯大-歯・新潟歯/東邦大-理/武蔵工大-工/福井工大-工/愛知工大-工/松阪大-政治経済/松蔭女学院大-文/流通科学大-商/産業医科大-医の16大学・19学部、全私立大の約4%に留まった。
初回の私立大セ試参加の顔ぶれをみると、難関大である慶應義塾大の文系(法)・理系(医)双方からの参加が目を引き、私立大参加の“シンボル”的存在として注目された。
慶應義塾大のセ試参加の背景には、当時、慶應義塾塾長であり、先述の臨教審会長代理、大学審議会(現・中教審大学分科会)会長等を歴任した故・石川忠雄氏が進める、入試も含めた大学改革への取組があったとみられる。
慶應義塾大-法はセ試参加当初、一般入試をA、Bの2方式に分割。A 方式(当時)の第1次試験は「セ試4教科(国語・社会・数学・外国語)と調査書」、第2次試験は「面接」を課した。B方式(当時)の第1次試験は大学独自の「社会・外国語・論述力テストと調査書」、第2次試験は「面接」を課した。
A 方式に“セ試4教科”を導入した背景として、当時の法学部では旺文社の取材に対し、セ試参加以前の入試(B方式に相当)における外国語重視(配点が社会・論述力テストの2倍)による外国語の受験学習の激化や、そうした受験学習に特化した合格者などに見られがちな入学後の勉学意欲の喪失などに対する方策、及び社会科学分野における数学的知識の必要性や学生の理数アレルギーの解消などを挙げていた。
また、セ試導入のA 方式によって、地方も含めた全国の高校生を対象に、多方面の教科に興味・関心・学力を備えた“万能型受験生”にも合格の機会を開くことによって、法学部学生の多様な個性・才能がさらに進むことを期待するとしていた。
ただ、セ試参加に際しては、問題の内容・レベル、セ試「自己採点」結果の出願で第1志望でない受験生が、真に入学意欲の高い受験生の合格の機会を奪う可能性、難関国立大との併願による“序列化”への組み込まれなど、様々な懸念の声もあがったようだ。
しかし、入試の多様化を図り、少しでも受験戦争の過熱化解消に協力すべきであるとし、懸念を解消する方策を一つ一つ講じて参加に踏み切っていったようだ。
法学部では以後、23年セ試まで21年間にわたって私立大セ試参加の“シンボル”的存在として、22回の「セ試利用入試」を続けることになる。ただ、医学部は17(2005)年セ試(セ試の英語のみを独自試験の英語と合算して利用)を最後に、18年に撤退している。
なお、20年4月に開設された薬学部(共立薬科大が慶應義塾大へ統合)は、21年セ試から「セ試利用入試」を実施(共立薬科大時代、既に実施)しているが、24年から法学部のA方式とともに廃止される。これで、慶應義塾大はセ試参加から完全に撤退することになる。
因みに、難関大である早稲田大のセ試参加は11(1999)年の法学部(セ試5教科と小論文)が最初で、23年は全13学部中、教育学部と基幹理工・創造理工・先進理工学部の4学部以外で「セ試利用入試」を行っている。(図2参照)
慶應義塾大-法はこの程、平成2(1990)年のセ試開始時から実施してきた「セ試利用入試」(以下、A方式)を24年から廃止し、新たな入試方法を導入すると発表した。
新しい方法では、既存のAO入試(現行のFIT入試:法律学科、政治学科それぞれ最大30人、計60人)にA方式の募集人員100人(法律学科、政治学科それぞれ50人)を充て、全国を6ブロック(九州・沖縄/中国・四国/近畿/東海・北陸/関東・甲信越/東北・北海道)に分け、学科ごとに各ブロック最大10人ずつ、計120人をAO入試の「地域ブロック枠」で募集する。
今回の入試方法の変更について、大学側は「地方からの学生を求めてセ試利用入試を行ってきたが、最近は都市部の学生が多くなっている。セ試参加当初、セ試利用入試における関東・甲信越以外の入学者割合は約8割であったが、22年では5割を下回った」という。
A方式の廃止を含めた今回の入試改革の背景には、上記のような入学者の地域的な偏向に加え、受験生のセ試を介した難関国立大(学部)との“併願”問題(帰属意識、入学意欲等)もうかがえる。
そこで、22年の法学部「一般入試」結果をみると、およそ次のとおりである。
|
■法律学科 志願倍率(志願者数÷募集人員)=24.2倍 実質倍率(受験者数<セ試利用では志願者数に同じ>÷入学許可者数)=3.8倍 募集人員に対する入学許可者数の倍率=6.3倍 ・B方式(大学独自入試。募集人員230人): 募集人員に対する入学許可者数の倍率=1.6倍 募集人員に対する入学許可者数の倍率=4.2倍 ・B方式(募集人員230人) 募集人員に対する入学許可者数の倍率=1.4倍 |
上記の結果から、法律、政治学科とも、「セ試利用入試」のA方式の志願倍率は、「大学独自入試」(以下、B方式)より2倍近く高く、高倍率であることがわかる。一方、実質倍率は逆にB方式の方がA方式より2倍近く高い。
さらに、A方式とB方式のそれぞれ募集人員に対する入学許可者数の倍率を比べると、A方式の方がB方式より、法律学科で約4倍、政治学科で3倍高いことも注目される。
このことから、法学部「セ試利用入試」は、「大学独自入試」に比べて他大学(学部)との“併願”が多く、入学手続き率(歩留まり率)を考慮して「セ試利用入試」の入学許可者数を相当数増やしていることがうかがえる。
こうした傾向は、慶應義塾大-法のA方式に限らず、セ試得点を出願大学(学部)にそのまま活用できる、いわば「セ試利用入試」の宿命ともいえるもので、出願者の当該大学(学部)への帰属意識や入学意欲は「大学独自入試」に比べ希薄になりがちであるといえよう。
* * *
ところで、慶應義塾大がセ試開始当初から22回にわたって利活用してきたセ試は、今や私立大(一般入試)も含め、大学進学志望者のまず出願先を決定づける重要な「共通試験」であり、50万人規模が全国一斉に受験する、いわば一つの社会的制度として定着している。
セ試志願者数が初回(平成2年)の約43万1,000人から今回(23年)の約55万9,000人までに巨大化したのは、私立大の参加増(短大は16年から参加)による。
私立大の参加が増えた要因は、前述したように、国公立大のみを対象に原則5教科7科目を課す共通1次試験から、私立大も対象に含めて各大学(学部)が利用教科・科目等を自由に利活用できる「アラカルト方式」に変えたことである。
また、セ試を単独で利用する従来型の「セ試利用入試」に加え、最近では「独自試験+セ試」といった併用型もみられ、「セ試利用入試」のバリエーションを拡大した入試方法の“複線化”も盛んだ。19年~22年の私立大「一般入試」の志願者増における「セ試利用入試」絡みの志願者数の増加率は、「大学独自入試」を凌ぐ勢いである。
このように、私立大セ試参加が拡大したことと、高校教育の多様化の進展、大学志願率の上昇などが相俟って、セ試受験者層も多様化の様相を一段と強めている。
セ試は受験生の「高校における一般的・基礎的な学習の達成度を測る」という“目的”(目標準拠型の達成度テスト=絶対評価)と、セ試を利活用する大学(短大含む)に対し「当該大学入学者を選抜するための基礎資料を提供する」という“機能”(集団準拠型の選抜テスト=相対評価)といった“二面性”をもっているといえる。そして、セ試受験者や大学側は専ら“選抜テスト”としてのセ試に着目している。
他方、現行セ試の出題(6教科28科目)は、“同一科目における難易差”がなく、すべての科目は1種類である。また、出題の難易度は、高校段階における基礎的な学習の達成度をみるというセ試の“目的”に沿って、平均得点率6割程度となることを目標に、学習指導要領の範囲内で出題されている。
このため、一部の難関国公立大(学部)や、その“併願”先の難関私立大の「セ試利用入試」では、当該大学(学部)志願者のセ試成績(5<6>教科7科目主体)は高得点域に集中し、セ試のみによる学力判定や入学者選抜は難しい状況にあるといえる。
その一方で、一部の私立大(学部)などでは「大学全入」や「入学定員割れ」などを背景に、セ試教科・科目のごく一部の利活用、あるいはセ試受験者の低得点域内での学力判定などを余儀なくされ、“実質的な選抜”とは程遠い状況にあるようだ。
セ試に関わるこうした入試状況は、大学進学志望者の多様化と私立大「セ試利用入試」の拡大・多様化に伴い、セ試受験者の“学力格差”が一層拡大していることを示している。
50万人規模の多様化した受験生を単一の「共通試験」で学力を評価したり、入学者を選抜したりすることは、もはや限界に達しているといえよう。
セ試開始から20年以上経ち、大学入試を巡る社会状況や受験環境は大きく変わっている。20数年前、「大学全入」や「入学定員割れ」、“学力不問”とまでいわれる「推薦・AO入試」など、一部とはいえ、大学入試の“機能不全”をどこまで想定できただろうか。受験生の学習教科・科目の偏りや学力の二極化、学生の学力低下や質保証の問題は深刻だ。
中教審はこうした大学入試の現状と課題に対し、『学士課程教育の構築に向けて』(20年12月答申)において、高校と大学は“選抜”だけでつながる関係から、“客観的できめ細やかな学力把握”とそれに基づく“適切な指導”で学力向上が図られるよう、共に力を合わせて取組む関係へと転換していくことを求めている。
中教審のこのような「高大接続」に係る入試改善策の答申に先立ち、20年8月に文科省の委託を受けた北海道大の所謂、「高大接続テスト(仮称)」に係る協議・研究(代表=佐々木隆生・北海道大特任教授。国公私立大、高校関係者等で構成)の『最終報告』(22年9月)は、高校段階の基礎的教科・科目についての学習の達成度を客観的に評価する“目標準拠型”の「達成度テスト」の基本的方向性を提言している。(図2参照)
「高大接続テスト(仮称)」は、高校側における生徒の学習を評価する「客観的指標」(絶対評価)としての活用が第一義とされつつも、それに留まらず、大学入試、とりわけ推薦・AO入試や初年次教育など、大学側での活用も想定されている。
「高大接続テスト(仮称)」の実現に向けては、セ試との関係が問題となろう。セ試の目的と機能の二面性を整理し、例えば、高校における基礎学力の「絶対評価」は「高大接続テスト(仮称)」(到達度テスト)が担い、入学者選抜のための学力評価の基礎資料(相対評価)の提供は「セ試」(選抜テスト)が担うなど、両者の目的・機能を整理する必要があろう。
さらに、セ試の“選抜テスト”としての機能に着目するならば、セ試受験生や利活用する大学側の多様性にも対応できる方策として、同一科目に難易度別の出題を設けることも必要ではないか。
因みに、先述した大学入試改革協議会の『大学入試改革について』(昭和63<1988>年2月)においても、「新テスト」(仮称:後のセ試)の水準について、「将来は同一教科・科目について内容の異なる複数のものを用意することも考慮する」とされ、難易度の異なる出題等についてはセ試開始当初から、将来に向けた“展望課題”として挙げられていた。
ともあれ、共通1次試験開始から32年、セ試開始から21年間、セ試にはこれまで様々な改善策が講じられ、極めて信頼度の高い公共的な「共通試験」として実施されてきており、一定の評価を得ている。ただ、単一の「共通試験」であるため、多様化した受験生や参加大学の実態に対応しきれない面も一部にあるとみる。
セ試受験生と利活用する大学側の多様化に即し、セ試による“選抜機能の実質化”を図るべく、出題内容や難易度などの一層の検討、熟議が望まれる。
